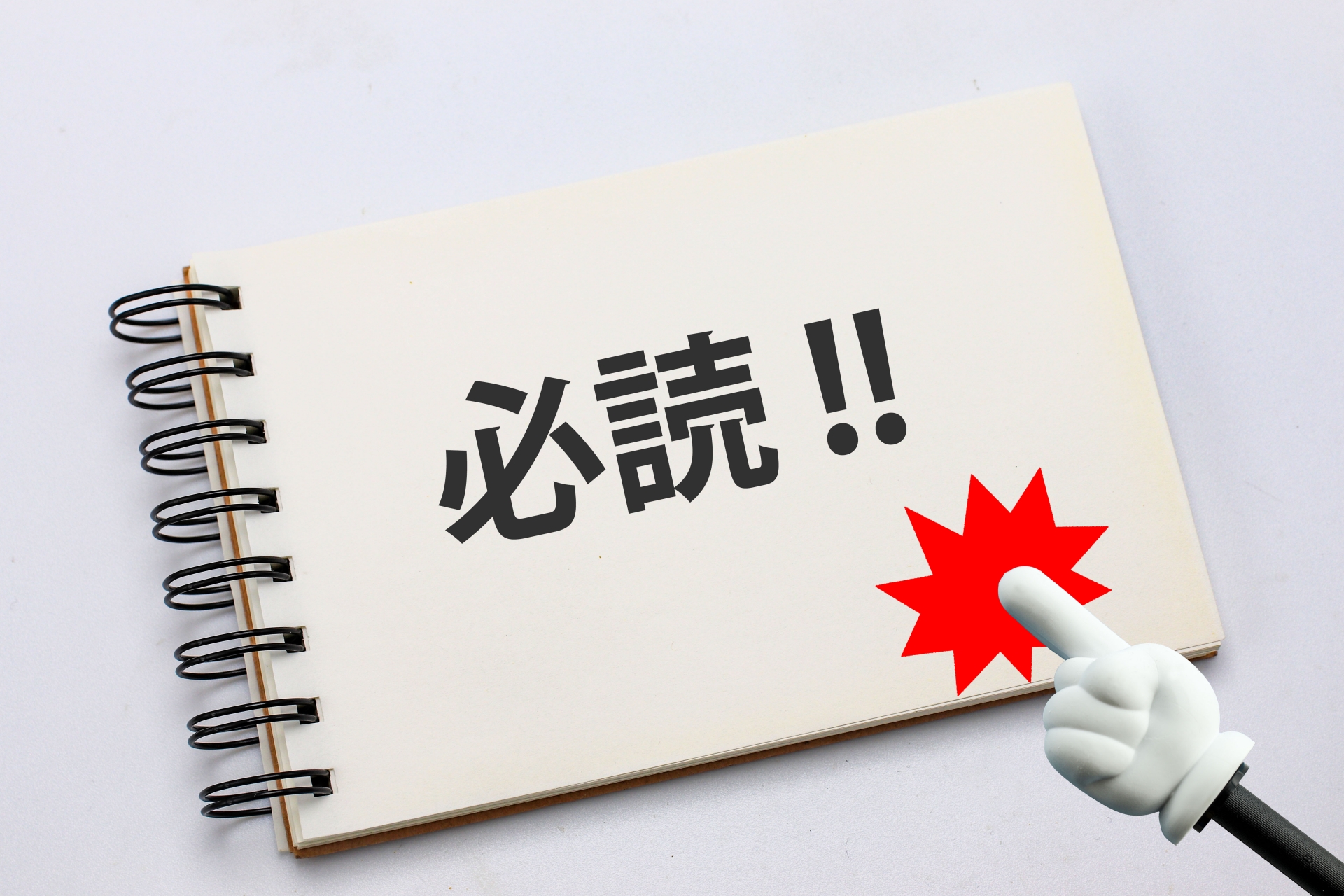はじめに:なぜ今、相続が「待ったなし」の課題なのか
「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」 「親の不動産は、いざとなったら兄弟で話し合えばいい」
かつては、相続対策とは一部の富裕層だけのものでした。しかし、時代は大きく変わりました。日本は世界でも類を見ない超高齢社会に突入し、毎年150万人以上が亡くなる「大相続時代」を迎えています。
特に不動産オーナーにとって、この変化は他人事ではありません。資産に占める不動産の割合が高いほど、相続は「争族」の原因となり、また、管理不全の「負動産」を生み出す温床ともなり得ます。
こうした社会背景を受け、国は近年、相続に関するルール(民法・不動産登記法)や税制の改正を矢継ぎ早に進めています。その多くは、不動産の所有・管理に直結するものです。
本コラムでは、不動産オーナー様が押さえておくべき**「現在進行中の主な改正点」と、今後予想される「将来的な見通し」**について、実務的な影響を交えながら徹底的に解説します。
第1部:不動産オーナー直撃!「現在進行形」の主な民法・登記改正
現在進んでいる改正の最大のキーワードは、**「所有者不明土地・空き家問題の解消」**です。価値の有無にかかわらず、不動産を「放置」することが許されない時代になりました。
1. 最大のトピック:相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
今回の改正で、不動産オーナーにとって最もインパクトが大きいのが**「相続登記の義務化」**です。
- 何が変わったか?
- これまで任意だった相続登記(不動産の名義変更)が、法的な義務となりました。
- 具体的には、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3年以内」に登記申請を行う必要があります。
- 重要なポイント:過去の相続も対象
- この法律は、施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続にも適用されます。
- 過去に相続した未登記の不動産がある場合、「施行日から3年以内(=2027年3月31日まで)」が猶予期間となります。
- 違反した場合
- 正当な理由なく登記を怠った場合、**10万円以下の過料(行政罰)**が科される可能性があります。
- オーナーへの影響
- 「親(あるいは祖父母)名義のまま」という不動産は、もはや許されません。
- 登記を放置すると、いざ売却や担保設定(融資)をしようとしても、前提となる名義変更が終わっておらず、手続きが迅速に進みません。
- さらに、相続人が増え(ネズミ算式に増える)、遺産分割協議が困難になるリスクを法的に排除する狙いがあります。
2. 義務化の「受け皿」となる新制度
3年以内の登記が難しいケース(例:相続人間で協議がまとまらない)を想定し、義務を簡易に履行するための「受け皿」も用意されました。
- 相続人申告登記
- 遺産分割協議が未了でも、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたとみなされる制度です。
- ただし、これは暫定的な措置であり、売却等のためには別途、正式な遺産分割と本登記が必要です。あくまで「過料を避けるため」の緊急避難的な意味合いが強いと認識してください。
- 土地国庫帰属制度(2023年4月施行済み)
- 「価値のない土地を相続してしまったが、売ることもできず管理費だけがかさむ」という不動産オーナー向けの、「土地を手放す」ための新制度です。
- ただし、ハードルは非常に高いです。
- 審査が厳しい:建物がない更地、土壌汚染や境界紛争がない、担保権が設定されていない等、多くの条件をクリアする必要があります。
- 費用がかかる:審査手数料に加え、承認されれば土地の性質に応じた10年分の管理費相当額(負担金)(例:宅地・田畑等は面積にかかわらず20万円、山林は面積に応じて算定)を納付する必要があります。
- 「タダで国が引き取ってくれる」制度ではないため、利用できるケースは限定的です。
3. 遺産分割ルールの見直し(2023年4月施行済み)
相続トラブルの長期化を防ぐため、遺産分割のルールにもメスが入りました。
- 遺産分割の期間制限
- 相続開始(死亡)から10年を経過すると、原則として「法定相続分」または「指定相続分」による画一的な分割しかできなくなりました。
- 「生前に親の介護を厚く行った(寄与分)」「多額の生前贈与を受けていた(特別受益)」といった個別の事情を考慮した柔軟な分割が、10年を過ぎると主張できなくなります。
- オーナーへの影響
- 不動産のように分割しにくい資産は、協議が長引きがちです。
- 「とりあえず親名義のまま実家に住み続ける」といった状態を10年続けると、いざ分割しようとした際に、最も貢献した相続人(例:親と同居し管理していた長男)が報われず、疎遠だった兄弟とも法定相続分で分けざるを得なくなるリスクが生じます。
こちらの記事も読まれています!
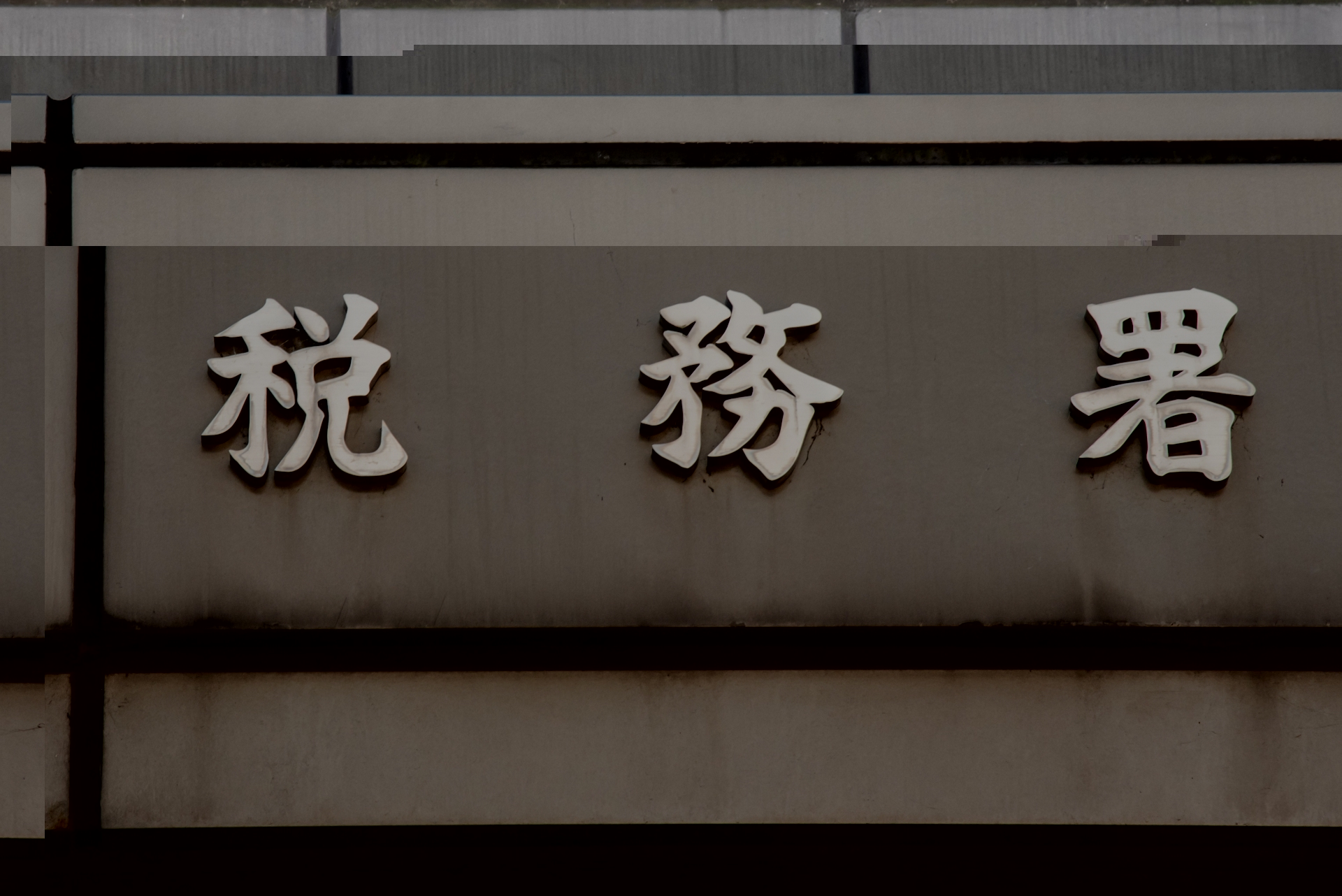
第2部:相続「税」の将来的な見通しと対策
民法改正が「管理」に焦点を当てているのに対し、税制改正は「資産移転」に焦点を当てています。ここでのキーワードは**「生前贈与と相続の一体化」**です。
1. 2024年大改正:生前贈与ルールの激変
これまで相続税対策の王道だった「暦年贈与(年間110万円まで非課税)」のルールが大きく変わりました。これは全オーナー必見の改正です。
- 改正点:「相続財産への加算期間」の延長
- これまでは、死亡前3年以内の生前贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算するルールでした。
- 2024年1月1日以降の贈与については、この持ち戻し期間が**「7年」**へと大幅に延長されました。(※延長された4年間の贈与からは合計100万円を控除)
- オーナーへの影響
- 「亡くなる直前に慌てて贈与する」という節税対策が、ほぼ無効化されました。
- 相続税対策としての生前贈与は、**「より早く、より計画的に」**行う必要が出てきました。
- 「7年」という期間は、不動産オーナーの平均的な年齢層を考えると非常に長く、早期の対策着手が不可欠です。
- もう一つの選択肢:「相続時精算課税」の使い勝手向上
- 今回の改正で、使い勝手が悪いとされてきた「相続時精算課税制度」(2500万円まで非課税で贈与し、相続時に一括精算する制度)にもテコ入れがなされました。
- 新たに**年間110万円の基礎控除(非課税枠)**が創設されました。この枠内の贈与は、相続財産への持ち戻しが不要(=贈与し切り)となります。
- オーナーへの活用法
- 例えば、「収益アパート」を早期に子へ贈与する場合。アパート自体の評価額は2500万円の枠を使い、そのアパートから生じる毎年の家賃収入(利益)を、この新しい110万円の枠を使って子に贈与していく、といった活用が考えられます。
- 暦年贈与の「7年縛り」を嫌気し、確実に資産を移転させたい場合に有効な選択肢となります。
2. 将来展望(1):タワマン節税へのメス(2024年1月施行)
不動産オーナー、特に富裕層にとって大きなトピックが、いわゆる「タワマン節税」の封じ込めです。
- 背景
- マンションは、市場での売買価格(時価)と、相続税を計算する際の評価額(路線価ベース)との間に大きなカイ離があり、これを利用した節税が広く行われてきました。
- 新ルール
- 2024年1月1日以降、相続・贈与で取得するマンションの評価額について、時価とのカイ離が大きい場合(一定の計算式に基づく)、評価額を時価に近づけるよう引き上げるルールが導入されました。
- 将来的な見通し
- これは「マンション」に限った話ですが、国税庁のスタンスは明確です。**「時価と評価額のカイ離を利用した過度な節税は、今後も厳しくチェックする」**という強いメッセージです。
- 今後、アパート一棟や商業ビルなど、他の不動産についても、何らかの形で評価方法が見直される可能性は否定できません。
3. 将来展望(2):「格差是正」のための課税強化
日本の相続税は、基礎控除(3000万円+600万円×相続人数)が2015年に引き下げられて以来、課税対象者が広がっています。
- 今後の方向性
- 「資産の再分配」「格差の是正」は、政府の重要課題であり続けます。
- 短期的には基礎控除の再引き下げは考えにくいですが、長期的には、不動産を含む「富裕層の資産」に対する課税は、より強化される方向で議論が進むと予想されます。
- 特に、路線価や固定資産税評価額といった「不動産評価」そのものの見直し(時価への接近)は、相続税だけでなく固定資産税の増税にも直結するため、常に注視が必要です。
こちらの記事も読まれています!
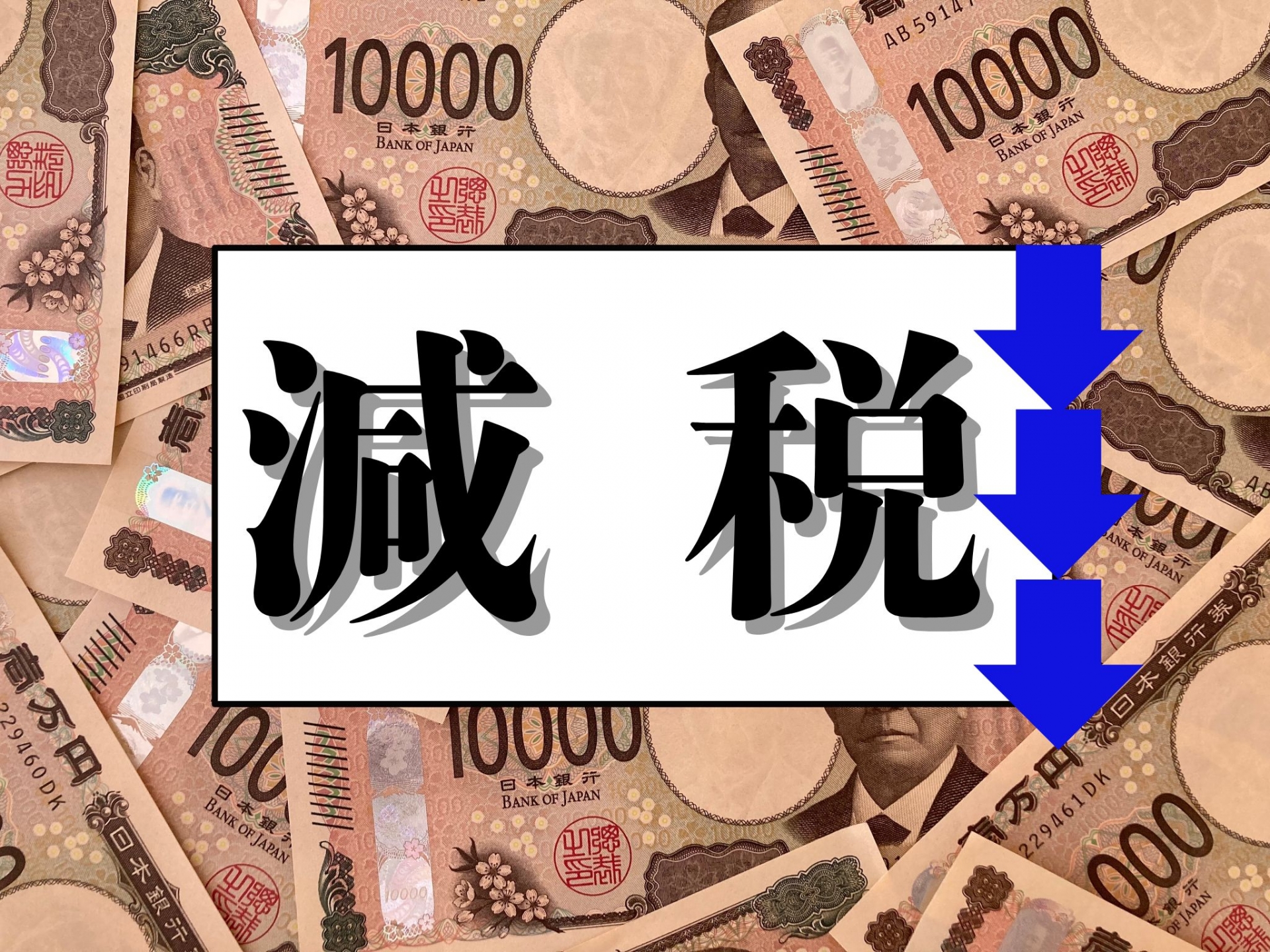
第3部:まとめ – 不動産オーナーが「今すぐ」やるべきこと
法改正と税制改正の両面から見てきた通り、相続を取り巻く環境は「不動産を放置させない」「資産移転を正確に捕捉し課税する」という2つの大きな流れの中にあります。
不動産オーナー様が、ご自身の資産を守り、円滑に次世代へ承継するために、「今すぐ」確認・実行すべきことは以下の3点です。
1. 「登記」の確認と「現状」の把握
まずは、ご自身が所有する(あるいは将来相続する可能性のある)不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を全て取得してください。
- 名義は本当にご自身のものになっていますか? 先代、先々代の名義のままではありませんか?
- 「相続登記の義務化」は、待ったなしです。未登記の不動産があれば、速やかに司法書士へ相談してください。
2. 「遺言書」の作成と見直し
不動産は現金と違い、物理的に分割できません。だからこそ「争族」の火種となります。「誰に、どの不動産を」相続させるか、明確な意思表示(=遺言書)が不可欠です。
- 特に「配偶者居住権」の活用や、特定の子供に事業用不動産を集中させたい場合など、法的に有効な遺言書の作成が必須です。
- 法務局での自筆証書遺言保管制度も普及しています。専門家(公証人や弁護士・司法書士)に相談し、現状に即した遺言書を準備してください。
3. 「税務戦略」の再構築
今回の税制改正(7年ルール)により、これまでの相続税対策は通用しなくなりました。
- 「暦年贈与」と「相続時精算課税」のどちらがご自身の家族にとって有利か、シミュレーションが必要です。
- アパート経営をされている方は、法人化(資産管理会社)の活用も含め、不動産と税務に強い税理士と共に、長期的な資産承継プランを再構築すべき時期に来ています。
「大相続時代」において、「何もしない」ことは最大のリスクです。法改正の意図を正しく理解し、専門家の知見を活用しながら、早期に「備える」こと。それこそが、大切な不動産という資産を守り抜く唯一の道となります。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい…現状の管理会社に不満がある…などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEでお問い合わせ可能です♪