はじめに
事業の未来を後継者に託す「事業承継」。それは、すべての経営者がいつかは直面する、経営における最大のテーマの一つです。しかし、多くの成功した経営者がその最終盤で直面するのが、想定をはるかに超える「相続税」という巨大な壁です。丹精込めて育て上げた会社と資産を、次世代へ円滑に、そして確実に引き継ぐために、経営者は何をすべきなのでしょうか。
本コラムでは、事業承継と資産防衛の観点から、極めて有効な選択肢となる「アパート・マンション経営(賃貸経営)」を活用した相続税対策について、その根本的な仕組みから具体的なメリット、そして見落としがちなリスクまでを徹底的に解説します。これは単なる節税テクニックの話ではありません。会社の未来と、大切な家族を守るための「経営戦略」としてお読みください。
なぜ事業承継に「相続税対策」が必須なのか?
1-1. 経営者が直面する「見えざる負債」としての相続税
中小企業のオーナーが保有する資産は、現金や有価証券だけでなく、その大部分を「自社株」や事業用の土地・建物が占めています。特に、長年にわたり利益を積み上げてきた優良企業の自社株は、オーナー自身が思っている以上に評価額が高騰しているケースが少なくありません。
例えば、相続税評価額が5億円、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、単純計算でも数千万円から1億円を超える相続税が発生する可能性があります。問題は、この納税資金を「現金」で用意しなければならない点です。
後継者である子供たちに、それだけの自己資金があるでしょうか。多くの場合、答えは「No」です。結果として、以下のような事態に陥りかねません。
- 会社の運転資金からの捻出: 会社の内部留保を取り崩し、経営を圧迫する。
- 役員退職金の活用: オーナーへの死亡退職金を納税資金に充てるが、それだけでは足りない場合も多い。
- 金融機関からの借入: 後継者が個人として多額の借金を背負うことになる。
- 資産の売却: 先代が守ってきた土地や、場合によっては自社株の一部を売却せざるを得ず、経営権が不安定になる。
- 事業の縮小・廃業: 最悪の場合、納税のために事業そのものを諦めるという悲劇も起こり得ます。
相続税は、まさに事業承継における「見えざる負債」なのです。だからこそ、経営者が元気なうちに、計画的に資産の形を組み替え、来るべき相続に備える「生前対策」が絶対に不可欠となります。
1-2「争族」を未然に防ぐための資産整理
相続の問題は、税金だけではありません。資産の分け方で親族間に亀裂が入る、いわゆる「争族」です。特に、自社株や事業用不動産のように、物理的に分割しにくい資産は争いの火種になりがちです。
賃貸アパートやマンションという形で資産を整理しておくことは、この問題にも有効です。例えば、アパートを1棟相続させることで、後継者は事業(会社)と生活基盤(家賃収入)の両方を安定させることができます。また、複数の物件があれば、子供たちにそれぞれ1棟ずつ相続させるなど、公平な分割案も立てやすくなります。計画的な資産整理は、円満な相続を実現するための第一歩でもあるのです。
こちらの記事も読まれています!

相続税評価額のカラクリと不動産が持つ「圧縮効果」
なぜ、現金や更地のまま資産を持つよりも、賃貸物件に形を変えることで相続税評価額を劇的に引き下げることができるのでしょうか。その秘密は、相続税法が定める特殊な財産評価ルールにあります。
2-1. 建物評価:「時価」ではなく「固定資産税評価額」で計算
現金を1億円持っていれば、その相続税評価額は当然1億円です。しかし、その1億円で賃貸アパートを建築した場合、建物の評価額は建築費や市場での売買価格(時価)ではなく、**「固定資産税評価額」**を基準に算出されます。
この固定資産税評価額は、自治体が固定資産税を計算するために用いる評価額であり、一般的に建築費のおおよそ50%~60%程度の水準になります。
【シミュレーション例①:建物の評価減効果】
- 現金: 1億円 → 相続税評価額: 1億円
- 建築費1億円のアパート: 固定資産税評価額が仮に6,000万円だった場合 → 相続税評価額: 6,000万円
この時点で、約4,000万円もの評価額圧縮が実現します。さらに、この建物が他人に貸し出されている場合、「借家権」による評価減が加わります。
建物の最終評価額 = 固定資産税評価額 × (1 – 借家権割合 × 賃貸割合)
- 借家権割合:全国一律30%
- 賃貸割合:相続開始時点の入居率
満室経営であれば、評価額はさらに30%減額され、6,000万円 × (1 – 30%) = 4,200万円となります。現金1億円が、アパートを建てるだけで最終的に4,200万円の評価になるのです。
2-2. 土地評価:「自用地」から「貸家建付地」へのマジック
土地も同様です。更地(自用地)の上に賃貸アパートを建てると、その土地は「入居者がいるため自由な利用が制限される土地」とみなされ、**「貸家建付地(かしやたてつけち)」**として評価が下がります。
計算式は以下の通りです。 貸家建付地の評価額 = 自用地評価額 × (1 – 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
- 借地権割合: 路線価図に定められており、都心部や商業地では60%~80%と高くなります。
【シミュレーション例②:土地の評価減効果】
- 自用地評価額1億円の土地
- 借地権割合: 70%
- 借家権割合: 30%
- 賃貸割合: 100%(満室)
評価額 = 1億円 × (1 – 70% × 30% × 100%) = 1億円 × (1 – 0.21) = 7,900万円
このケースでは、土地だけでも2,100万円の評価額圧縮が可能です。
2-3. 究極の節税策:「小規模宅地等の特例」
さらに強力なのが**「小規模宅地等の特例」**です。これは、亡くなった方の生活や事業の基盤となっていた土地について、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。賃貸アパートや駐車場などの貸付事業に使われていた土地は「貸付事業用宅地等」に該当し、200㎡までの部分について評価額を50%減額できます。
【総合シミュレーション:現金2億円の資産を組み替えた場合】
- 前提:
- 現金資産: 2億円
- この2億円で土地1億円(180㎡)、建物1億円のアパートを建築。
- 土地の自用地評価額: 1億円(借地権割合70%)
- 建物の固定資産税評価額: 6,000万円
- 満室経営(賃貸割合100%)
- 評価額の計算:
- 建物: 6,000万円 × (1 – 30%) = 4,200万円
- 土地(貸家建付地評価): 1億円 × (1 – 70% × 30%) = 7,900万円
- 土地(小規模宅地等の特例適用): 7,900万円 × 50% = 3,950万円
- 最終的な相続税評価額: 建物 4,200万円 + 土地 3,950万円 = 合計 8,150万円
驚くべきことに、現金2億円が、相続税の世界では8,150万円の資産として評価されるのです。この評価額の差が、相続税額にどれほど大きな影響を与えるかは言うまでもありません。
節税だけではない!賃貸経営がもたらす事業と家族への恩恵
賃貸経営は、相続税対策という「守り」の側面だけでなく、経営者個人や会社に様々な「攻め」のメリットをもたらします。
3-1. 安定したキャッシュフローの創出(第二の給与)
毎月の家賃収入は、会社の給与とは別の、安定した個人収入源となります。これにより、経営者は精神的な余裕を持って事業に集中できますし、将来の役員勇退後の私的年金としても機能します。事業承継後、後継者が得る家賃収入は、会社の経営を財政面・精神面で支える大きな力となるでしょう。
3-2. 所得税・住民税の圧縮(損益通算と減価償却)
不動産所得の計算上、建物の取得費は**「減価償却費」**として、法定耐用年数にわたって毎年経費計上できます。この減価償却費は、実際にお金が出ていくわけではない「帳簿上の経費」です。
特に、事業開始当初は、減価償却費や借入金利息などの経費が家賃収入を上回り、不動産所得が赤字になるケースが多くあります。この赤字は、経営者個人の給与所得など他の黒字所得と合算(損益通算)することができ、結果として所得税や住民税の還付・軽減につながります。手元のキャッシュはプラスなのに、税金は安くなるという、非常に有利な状況を作り出せるのです。
3-3. 究極の生命保険「団体信用生命保険(団信)」
金融機関から融資を受けて物件を購入する場合、通常は「団体信用生命保険(団信)」への加入が義務付けられます。これは、ローン返済中にオーナーが死亡または高度障害状態になった場合、残りのローン全額が保険金で完済される仕組みです。
これは、残された家族や後継者にとって、計り知れない価値を持ちます。相続するのは、借金のない、毎月収益を生み出す優良資産(アパート・マンション)だけ。まさに、最高の生命保険と言えるでしょう。この保険効果だけでも、賃貸経営を検討する価値は十分にあります。
3-4. インフレに強い「実物資産」としての価値
長期的に見れば、物価が上昇していくインフレの局面では、現金の価値は相対的に目減りしていきます。一方、不動産という「実物資産」は、インフレに伴ってその資産価値や家賃相場も上昇する傾向にあります。将来の経済変動に対するリスクヘッジとしても、不動産所有は有効な手段です。
こちらの記事も読まれています!
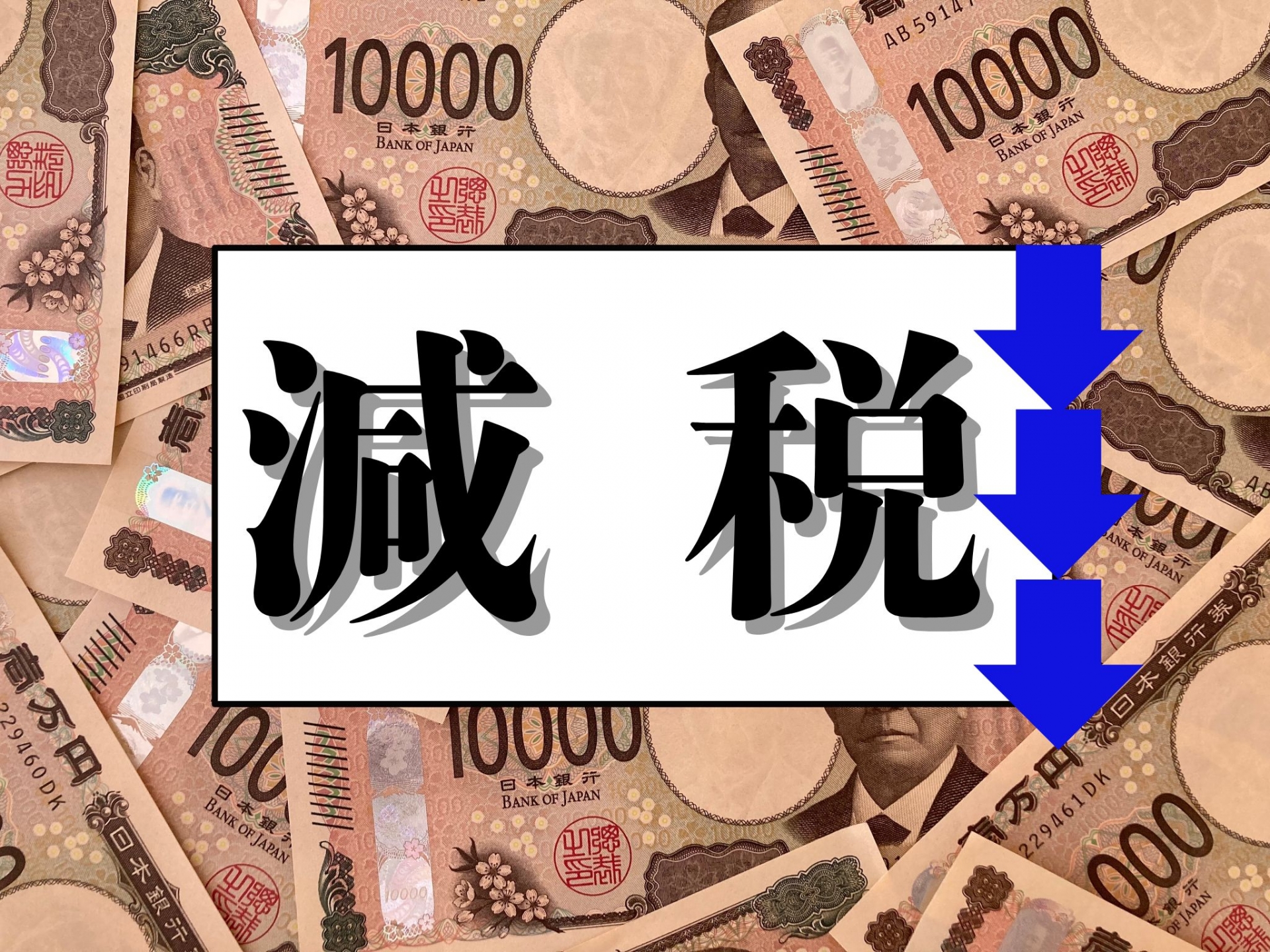
成功への鍵はリスク管理にあり!注意すべき落とし穴
これほど多くのメリットがある賃貸経営ですが、あくまで「事業」である以上、リスクは存在します。節税効果に目がくらみ、安易に始めてしまうことこそが最大の失敗要因です。
4-1. 5大リスクとその対策
- 空室リスク: 満室経営が前提の計画は危険です。
- 対策: 徹底した立地調査(駅からの距離、周辺環境、大学や企業の有無)、将来の人口動態予測、競合物件との差別化(デザイン、設備、セキュリティ)、信頼できる管理会社の選定が不可欠です。
- 家賃下落リスク: 建物は古くなれば家賃も下がります。
- 対策: 周辺相場を常に把握し、適切な家賃設定を行うこと。時代に合わせたリフォームやリノベーションで物件の魅力を維持する投資計画を立てておくことが重要です。
- 老朽化・修繕リスク: 突発的な修繕費が発生します。
- 対策: 10~15年周期で必要となる外壁塗装や屋上防水などの大規模修繕に備え、長期修繕計画を策定し、毎月の家賃収入から計画的に修繕積立金を取り分けておく必要があります。
- 金利上昇リスク: 変動金利での借入は返済額が増える可能性があります。
- 対策: 借入当初の低金利に惑わされず、金利が2%~3%上昇してもキャッシュフローが回るような、余裕を持った資金計画を立てましょう。固定金利との比較検討も必須です。
- 災害リスク: 地震、火災、水害など。
- 対策: 火災保険や地震保険への加入は絶対条件です。ハザードマップを確認し、災害に強い構造の建物を選ぶことも重要になります。
4-2. 相続税対策としての失敗例
- 収益性度外視の物件: 「節税」が目的化し、地方の利回りが低い、あるいは入居付けが困難な物件を購入。相続税は減ったが、毎年の経営が赤字で、結局資産を減らしてしまった。
- 共有名義の悲劇: 相続人が複数いるからと安易に共有名義にした結果、売却したい人、継続したい人で意見が対立。誰もが身動き取れない「負動産」と化してしまった。
- 納税資金の枯渇: 評価額を下げることばかりに注力し、手元の現金を使い果たしてしまった。いざ相続が発生した際に、圧縮されたとはいえ相続税を支払う現金がなく、結局、相続したアパートを売却せざるを得なかった。
まとめ:最良の事業承継は、専門家との二人三脚から始まる
賃貸経営を活用した資産承継は、正しく実行すれば、事業承継を円滑にし、会社の永続的な発展と、家族の未来を守るための極めて強力なツールとなります。
しかし、その成功は、税務、不動産、建築、法務といった多岐にわたる専門知識の集大成です。経営者一人の判断で進めるのはあまりに危険です。
大切なことは、事業承継や資産税に精通した税理士、そして地域の市場動向を熟知した信頼できる不動産コンサルタントといったプロフェッショナルをパートナーとして見つけ、長期的な視点で、あなたとあなたの会社にとっての「最適解」を一緒に作り上げていくことです。
事業のゴールは、次世代にバトンを渡すその日まで続きます。このコラムが、経営者であるあなたの、その長く、そして尊い道のりを照らす一助となれば幸いです。まずは、信頼できる専門家の扉を叩くことから始めてみてください。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい…現状の管理会社に不満がある…などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEでお問い合わせ可能です♪

















