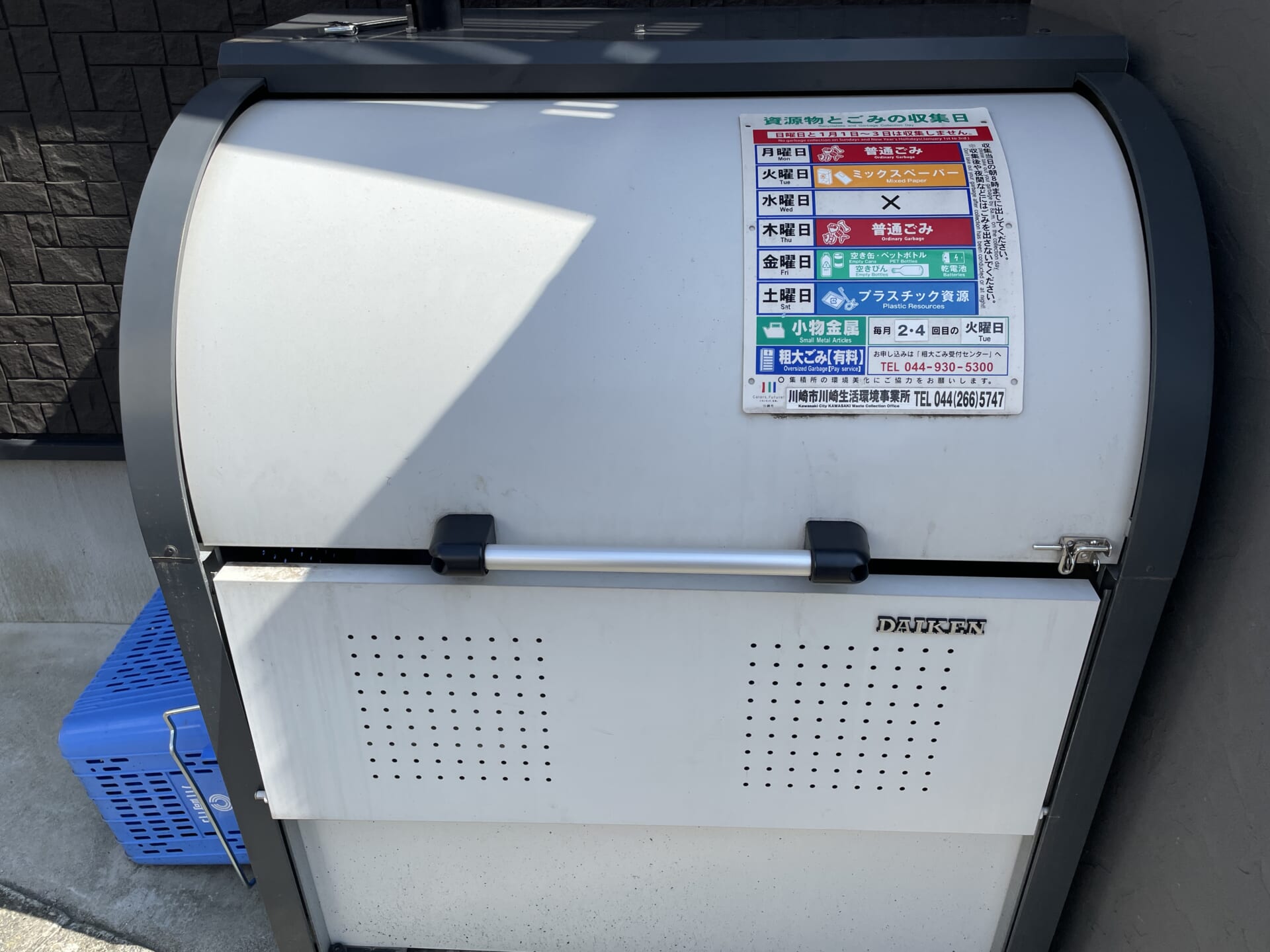~警報と緊急出動、その裏側と私たちにできる予防策~
こんにちは。不動産管理会社アブレイズパートナーズです。
今回は、とある分譲マンションで実際に起きた火災報知器の誤作動トラブルについて詳しくご紹介いたします。
「火災報知器が鳴り響く」「深夜に消防車が出動」「実は誤作動だった」
…そんな話、他人事だと思っていませんか?
実はこのようなケース、年々増加傾向にあります。
その背景には、建物設備の高機能化や生活スタイルの多様化、そして人々の「正常性バイアス」が深く関係しているのです。
今回は、「誤発報トラブル」がなぜ起きるのか? どう対処すべきか?
そして、オーナーや管理者がどのように予防策を講じるべきかを、事例をもとに深掘りしてまいります。
【事例】夜中の非常ベル!管理会社も大慌て
ある平日の10時頃。
分譲マンションの住民から、弊社管理センターに緊急の連絡が入りました。
「館内に非常ベルが鳴り響いていて止まらない」
「火の気は見当たりませんが、どうすればよいですか?」
すでにセコムが出動中で、同時に消防にも自動通報が入っている状態でした。
現地に急行したスタッフと警備員、消防隊がマンション内を隈なく点検しましたが、火元は確認されず、結果として「誤作動」であることが判明。
警報が収まり、事態が沈静化したのはおよそ1時間後。
その間、住民の皆様は不安と緊張の中、廊下や共用部に集まって状況を見守るという事態となりました。
明確な原因は「不明」…でも見えてきた可能性
今回の誤発報、実は「なぜ鳴ったのか?」がはっきりしていません。
しかし、経験上いくつかの有力な原因の可能性が浮かび上がってきます。
- 入浴中に浴室の扉を開けたまま使用し、湯気が感知器に当たった
- 深夜にキッチンで調理をしていた際に、煙が感知器に反応
- 室内で喫煙した際の煙が上昇し、誤感知を誘発
- 夏場で窓を開けていた際に、虫が感知器に侵入
火災報知器は、「煙」や「熱」に対して非常に敏感に反応するよう設計されています。
そのため、“火”でなくても“煙や蒸気”で十分に発報する可能性があるのです。
誤発報はなぜ問題なのか? その深刻な影響とは
誤作動が起きること自体は機械的には仕方のない面もありますが、以下のような重大な影響があります。
1. 住民の安心感を損なう
ベルで目が覚め、不安で外に出たのに「火災じゃなかった」…
これが2度、3度と繰り返されれば、次に本当の火災が起きても誰も避難しないという「慣れ」が生まれてしまいます。
2. 消防や警備会社への不要な出動
消防法の観点では、「火災でないことが明らかな場合」を除き通報義務があるため、結果的に毎回出動することになります。
出動回数が増えることで“悪質な誤通報”と認定されるリスクもあり、管理組合に指導が入るケースも。
3. 費用・保険・責任問題
場合によっては、緊急出動にかかる費用が請求対象となることがあります。
また、住民やオーナーとの間で責任の所在を巡ってトラブルになることも少なくありません。
感知器の種類と誤作動のリスク
火災報知器は大きく分けて以下の種類があります。
| 種類 | 説明 | 誤作動しやすい要因 |
|---|---|---|
| 煙感知器 | 煙を検知して作動 | 湯気、たばこの煙、調理中の煙など |
| 熱感知器 | 一定の温度以上で反応 | 湯気、ストーブ、調理器具など |
| 炎感知器 | 炎の光(紫外線や赤外線)を検知 | ライターの火など誤反応の恐れも |
設置箇所に合っていない感知器を使用していると、誤作動の可能性は飛躍的に高まります。
とくに浴室前やキッチンなど、温度や湿度の変化が激しい場所では注意が必要です。
誤作動を防ぐためにオーナー様ができること
分譲マンションでは、専有部の火災報知設備は基本的に所有者=オーナーの責任範囲です。
以下のような対策を講じることで、誤発報リスクを大きく軽減できます。
✅ 感知器の設置場所を見直す
換気口の近く、調理機器の真上などは避けましょう。
✅ 湯気や煙が出る際は、換気扇を積極的に使用
シャワーを使う際は浴室扉を閉め、換気扇を回すようにするだけでも効果的です。
✅ 定期的に感知器の点検・清掃を
虫の死骸やホコリが溜まって誤作動することもあります。
最低でも年に1回程度は点検・メンテナンスを実施しましょう。
誤作動が起きてしまったら? 緊急時の対応手順
いざ火災報知器が鳴ったとき、住民や管理者はどう対応すべきでしょうか?
🧍♀️住民側の行動
- 安全を最優先に避難準備(ベランダではなく共用廊下へ)
- 火の気があるか確認。煙やにおいの有無もチェック
- 管理室や警備センターへ状況連絡
🧑💼管理会社の初動対応
- 発報元の特定(受信盤で確認)
- 現場確認(火災か誤作動かを判断)
- 記録(日時・原因・写真等)
- 報告(消防、警備、オーナー、保険会社)
【豆知識】火災報知器の設置は義務?罰則はある?
実は、2006年からすべての住宅で火災警報器の設置が義務化されました。
既存住宅でも、遅くとも2011年までに対応が求められており、設置していない場合は消防法違反に問われる可能性があります。
また、誤作動が多発し、それを放置していた場合には、消防から改善命令や指導が入ることもあるため、甘く見ることはできません。
【事例】「火事かと思ったら焼き魚だった」話
少し脱線しますが、某マンションで起きた笑えない話。
「家でサンマを焼いていたら煙が出すぎて感知器が鳴った」
「外で洗濯していて気づかず、消防が来ていた」
これは実際にあった話です。
高層階の角部屋で窓を開けて煙を逃がしたつもりが、上階の換気ダクトに入ってしまい、共用部の煙感知器が作動してしまったというケースでした。
つまり、自分の部屋から出た煙でも他の部屋に影響を及ぼすことがあるということです。
周知文例(掲示板・配布用)
【火災報知器 誤作動防止のお願い】
近年、火災報知器の誤発報による緊急出動が増加しております。
次の点にご協力いただくことで、誤作動を防ぐことができます。・調理中は換気扇を使用し、煙を溜めない
・浴室の扉はシャワー使用後すぐ閉めて換気を行う
・感知器の近くでの喫煙・スプレー使用は避ける
・感知器の上に物を置かない・塞がない安心・安全な住環境の維持のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
まとめ
火災報知器の誤作動――
それは些細な生活習慣や設備不良、気温や湿度といった自然要因が複雑に絡み合って起こる現象です。
大切なのは、「自分の家は関係ない」と思わず、設備への理解と予防意識を持つこと。
マンションという“共同住宅”の特性をふまえ、
専有部・共用部がつながっていることを意識することが、安心と信頼につながる管理と言えるでしょう。
今後も私たち管理会社は、オーナー様・入居者様と連携しながら、安全な暮らしを支えてまいります。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい・・・現状の管理会社に不満がある・・・などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式ラインからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、ラインでお問い合わせ可能です♪