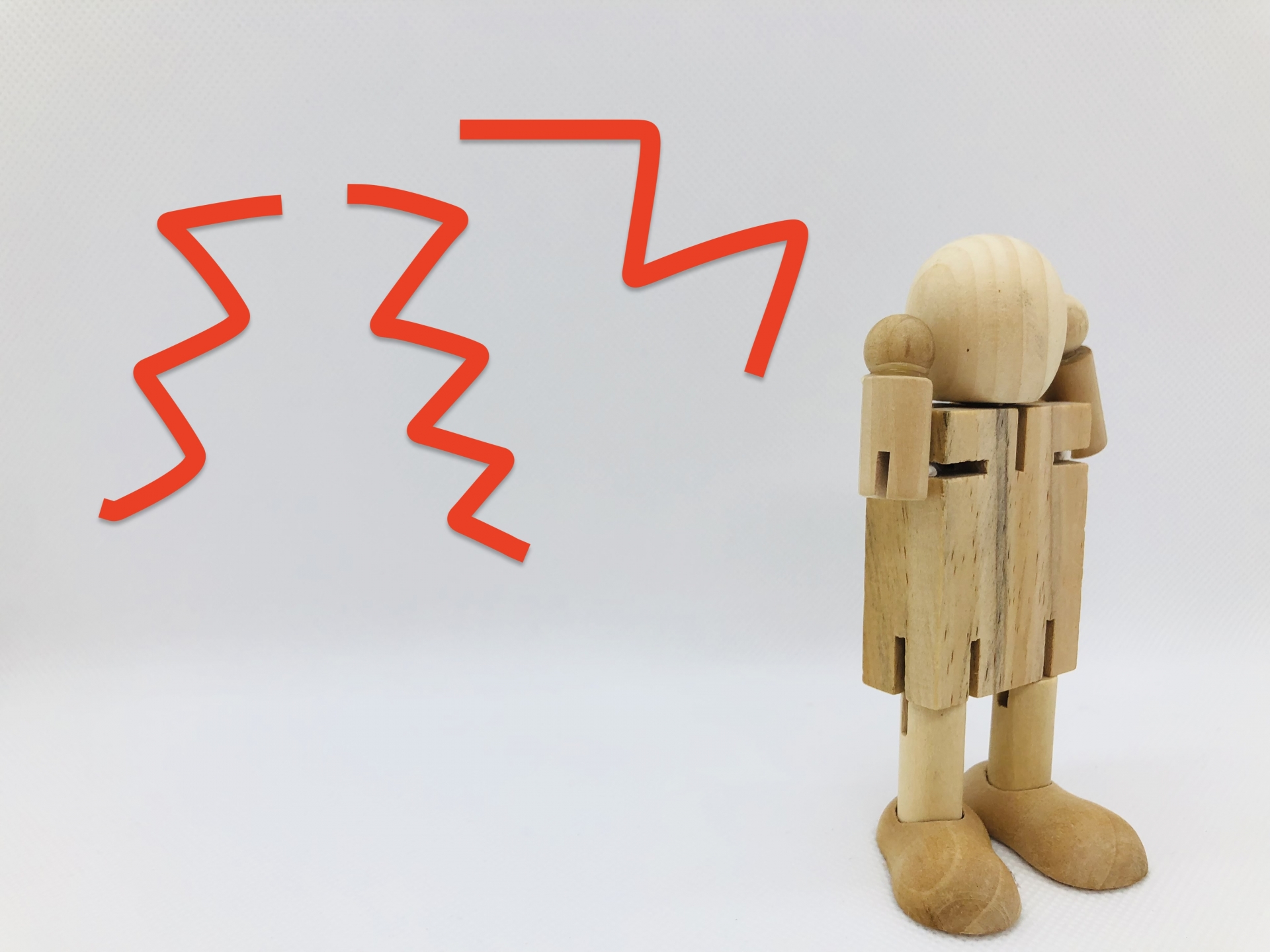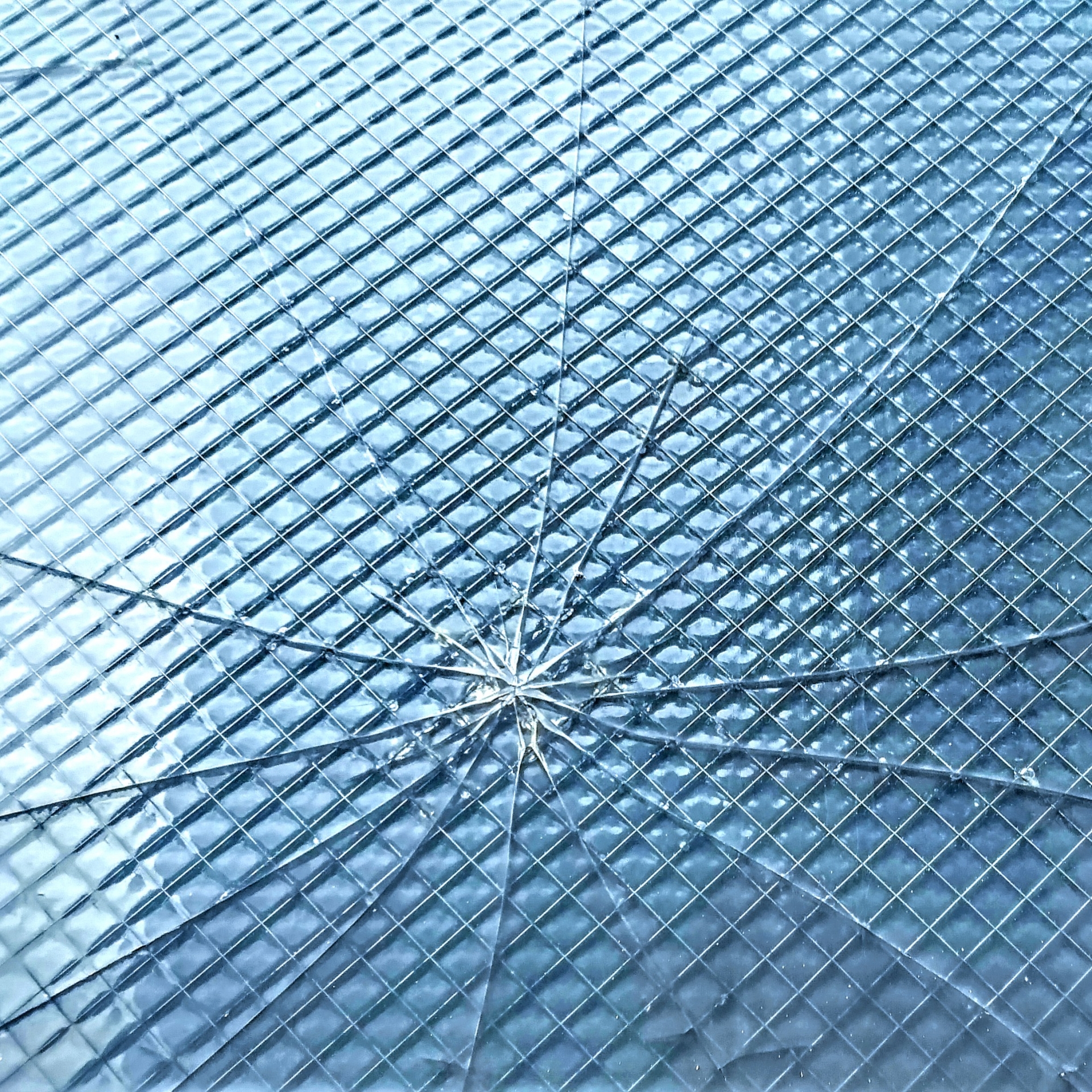集合住宅の宿命か? 賃貸物件の騒音トラブルを解決に導くロードマップ
共同生活の場である賃貸物件において、避けて通れない問題の一つが「騒音トラブル」です。
単なる「うるさい」という感覚的な問題に留まらず、時には入居者の心身の健康を脅かし、最悪の場合、退去や訴訟に発展する深刻な事態も引き起こします。
特にプライバシーが密接に関わる集合住宅では、その解決は一筋縄ではいきません。
本稿では、賃貸物件における騒音トラブルの実態、法的な基準、具体的な解決のための手順、そして入居者が自身を守るための対策までを網羅的に解説し、トラブルを未然に防ぎ、あるいは適切に解決するための道筋を示します。
第1章:騒音トラブルの実態と「受忍限度」の壁
1. 騒音トラブルの主な原因と影響
賃貸物件で発生する騒音は多岐にわたります。最も多いのは、上階からの「生活音」です。具体的には、子供の走り回る音、床への衝撃音(フットドロップ)、夜間の洗濯や掃除機の音、話し声やテレビの音量などが挙げられます。
他にも、ペットの鳴き声、楽器の演奏音、給排水の音、ドアの開閉音など、日常に存在する音が、集合住宅の構造的な防音性の低さや生活時間帯の違いによって「騒音」へと変わります。
これらの騒音は、被害者である入居者に睡眠障害、ストレス、精神的な苦痛を与え、生活の質(QOL)を著しく低下させます。
その結果、「騒音」が理由での早期退去を経験する入居者が後を絶ちません。
2. 法的な基準と「受忍限度」
「どこからが騒音なのか」という問いは、非常に難しい問題です。
音の感じ方には個人差があるため、法的な判断基準として「受忍限度」という概念が用いられます。
これは、「社会生活を営む上で、一般的に我慢すべき限度」を指し、この限度を超えた場合に、初めて法的な責任(損害賠償や差止請求など)が発生すると考えられます。
【騒音の客観的な判断基準】
環境省が定める「騒音に係る環境基準」では、一般的な住宅地において以下の数値が望ましいとされています。
• 昼間(午前6時から午後10時):55デシベル以下
• 夜間(午後10時から翌午前6時):45デシベル以下
デシベルの目安として、40dBは図書館、50dBは静かな事務所、60dBは洗濯機(1mの距離)や普通の会話程度です。
夜間に45デシベルを超える音(例:テレビの音量、子供の走り回る音)が継続的に発生している場合、騒音と認められる可能性が高まります。
しかし、この基準はあくまで行政上の目標であり、裁判での受忍限度の判断は、音の大きさだけでなく、発生時間帯、頻度、継続期間、地域の特性、建物の構造などを総合的に考慮して下されます。
過去の判例では、夜間に40〜50デシベルを常時または反復継続して超える場合、受忍限度を超える傾向が見られます。
第2章:トラブル解決に向けた冷静なステップ
騒音トラブルは感情的な対立に発展しやすく、直接交渉は最も避けるべき行為です。第三者である管理会社や大家を介することが、問題解決の鉄則となります。
ステップ1:騒音の客観的な記録・証拠収集
感情論ではない、客観的な証拠が解決への第一歩となります。
1. 日時・時間帯の特定: 騒音が発生した具体的な日付、時刻(何時何分から何時何分まで)、頻度を記録します。
2. 音の種類の特定: どのような音(足音、話し声、音楽、水音など)が、どの方向(上階、隣室など)から聞こえたかを詳細にメモします。
3. 音量の計測・録音: スマートフォンアプリや騒音計で音量を計測し、できれば録音データとして残します。ただし、アプリの数値はあくまで目安であることを理解しておく必要があります。
4. 影響の記録: 騒音によって睡眠が妨げられた、体調を崩したなど、具体的な被害状況を記録し、病院の診断書や通院記録があれば証拠として収集します。
ステップ2:管理会社・大家への相談
証拠を集めたら、まずは物件の管理者へ連絡します。
• 中立な対応を依頼: トラブルを未然に防ぐため、騒音主を特定しない形で全入居者への注意喚起(掲示板への貼り紙、書面の投函など)を依頼するのが一般的です。
• 個別対応の依頼: 全体への周知で改善が見られない場合は、管理会社・大家から騒音主とされる入居者へ、中立の立場で事実を伝え、改善を促すよう依頼します。被害者の情報(誰からの苦情か)は伏せてもらうことが重要です。
• 対応記録の依頼: 管理会社がどのような対応を行ったか、その日時や内容を記録してもらい、進捗を報告してもらうよう依頼します。
ステップ3:公的機関への相談(管理者での解決が困難な場合)
管理会社や大家が動かない、あるいは対応しても改善が見られない場合、以下の機関に相談を検討します。
1. 自治体の窓口: 地域の環境部署や生活相談窓口で、騒音規制や解決方法についてアドバイスを受けられます。
2. 警察: 騒音トラブルは基本的には民事不介入ですが、深夜のパーティーなど「著しく静穏を害する」行為や、騒音主とのトラブルが「暴力や脅迫」に発展しそうな場合は、生活安全課に相談できます。ただし、注意喚起に留まることがほとんどです。
3. 弁護士・法テラス: 騒音が受忍限度を超えている可能性があり、損害賠償請求や賃貸借契約の解除(管理者に対して)、あるいは騒音主への差止請求(裁判)を視野に入れる場合は、専門家である弁護士に相談します。
第3章:賃貸人が知っておくべき責任と対策
1. 大家・管理会社の法的責任
賃貸借契約において、大家(賃貸人)は入居者に対して、物件を支障なく使用・収益させる義務(使用収益させる義務)を負っています。
近隣の騒音によってその義務が果たされていないと判断される場合、騒音主だけでなく、適切な対応を怠った大家や管理会社も、債務不履行として損害賠償責任を負う可能性があります。そのため、管理会社や大家は、騒音トラブルに対して真摯かつ迅速に対応する責任があります。
2. 騒音主への「契約解除」の可能性
騒音主が管理会社や大家からの注意にもかかわらず改善せず、騒音が受忍限度を超えて継続する場合、**賃貸借契約の解除(強制退去)**が検討されることがあります。
ただし、これは入居者の「居住権」に関わる重大な処分であり、裁判所は「賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊された」と認められるほどの重大な迷惑行為がない限り、簡単には認めません。継続的な証拠収集と段階的な注意喚起の記録が必須となります。
3. 入居者自身でできる具体的な防音対策
被害者、加害者、いずれの立場であっても、集合住宅での生活の快適性を高めるため、入居者自身でできる対策があります。
また、音を「出す側」となる可能性のある入居者は、夜間の洗濯や掃除機の使用を避ける、大きな音の出る活動を共有部のルールで決められた時間帯に行うなど、マナー意識を持つことが何よりも重要です。
まとめ
賃貸物件の騒音トラブルは、「音」という目に見えない、非常にデリケートな問題です。解決の鍵は、感情的にならず、客観的な証拠に基づいた冷静な行動、そして管理会社・大家という第三者の適切な介入にあります。
入居者は、集合住宅での共同生活である以上、ある程度の生活音は「お互い様」として受け入れる心構えと、同時に、自身が「加害者」にならないよう配慮する意識が必要です。そして、被害に遭った際には、一人で抱え込まず、適切な手順を踏んで然るべき機関に相談することが、心身の健康を守り、快適な住環境を取り戻すための確実なロードマップとなります。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい・・・現状の管理会社に不満がある・・・などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEでお問い合わせ可能です♪