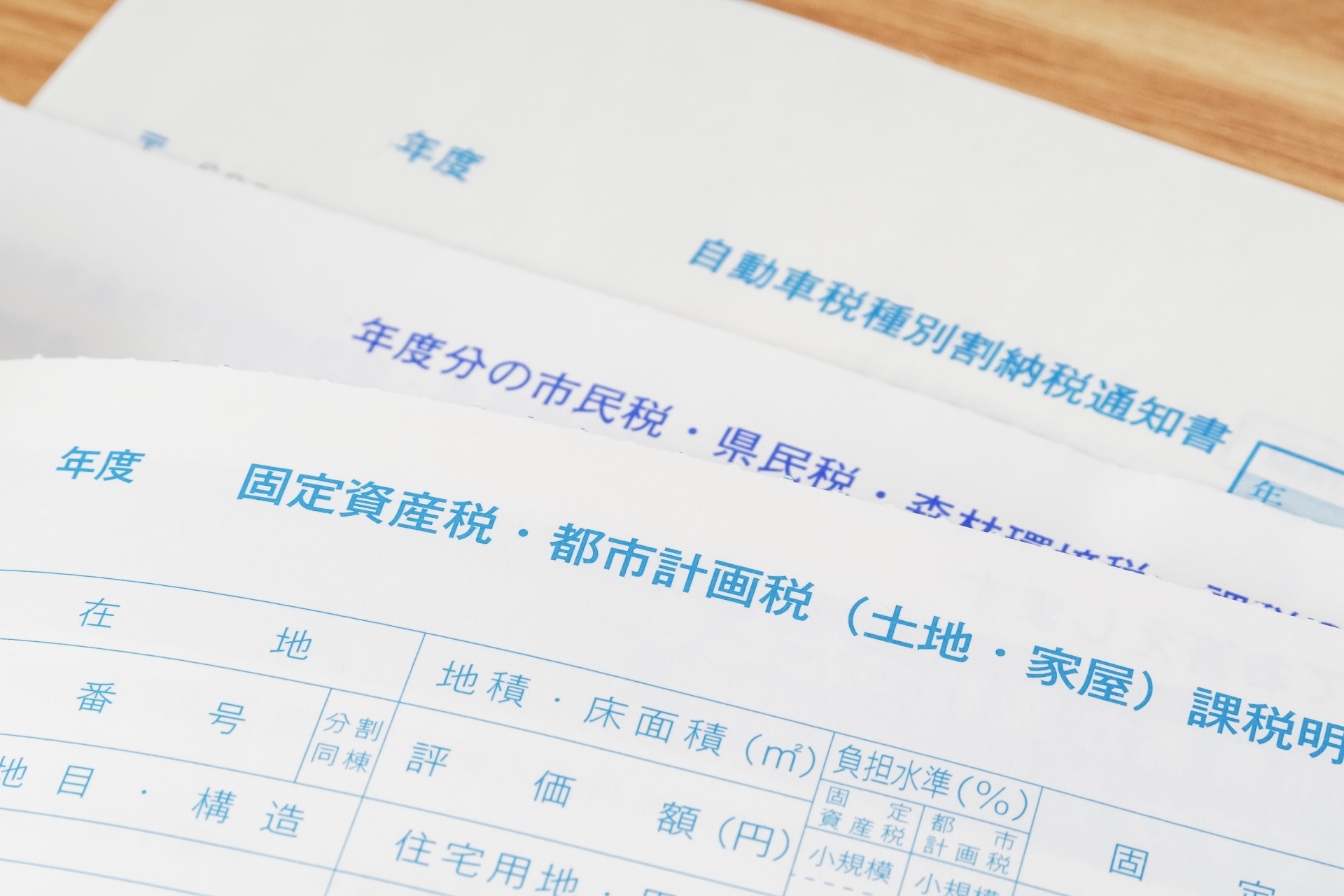不動産は、単なる資産ではなく、オーナー様の未来と次世代への責任を担う重要な資本です。しかし、その価値を決定し、税負担に直結する固定資産税評価や相続税評価の仕組みは複雑であり、頻繁に行われる評価替えや税制改正によって常に変動しています。
本コラムでは、不動産オーナーの皆様が今後直面する評価替えの動向、相続税評価の是正、そして2026年(令和8年)以降に本格化する可能性のある税制改正の焦点について、深く掘り下げて解説し、具体的な対応策を提示します。
1. 資産運用に直結する「固定資産税の評価替え」徹底分析
固定資産税は、地方自治体の重要な財源であり、その評価額は所有する不動産の価値を測る公的な基準の一つです。この評価額は、原則として3年に一度見直されます。直近の評価替えは2024年度(令和6年度)に実施されました。次の大きな見直しは**2027年度(令和9年度)**となります。
1-1. 評価替えの仕組みと地価動向の影響
固定資産税の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて行われます。評価額が決定される基準日は、評価替えを行う年の1月1日です。
土地の評価:地価公示価格との連動と「負担調整措置」
土地の評価額は、地価公示価格や都道府県地価調査価格などの7割を目途に算定されます。評価替えの際には、過去3年間における地価の変動が反映されます。
- 2027年度(令和9年度)の予測される動向: 現在、都市部や一部の地方都市では依然として地価の上昇傾向が見られます。この地価高騰が2027年1月1日時点まで継続していれば、多くのエリアで土地の評価額は上昇する可能性があります。特に、再開発が進むエリアや、利便性の高い駅周辺などは、大きな評価増となるリスクがあります。
- 負担水準と負担調整措置: 土地の評価額が急激に上昇しても、税負担が急激に増加することを緩和するために「負担調整措置」が設けられています。これは、現行の課税標準額が評価額に対してどの程度の水準にあるか(負担水準)に応じて、税額の上昇を緩やかにする仕組みです。評価替えで評価額が上がったとしても、すぐに満額課税されるわけではありませんが、負担水準が低い物件ほど、評価替えによる税額増加の幅が大きくなる傾向があるため、注意が必要です。
家屋の評価:再建築費の変動と経年減価の限界
家屋(建物)の評価額は、同じ建物を評価替えの時点でもう一度建築した場合にかかる費用(再建築費)を基準に算定されます。
- 資材価格の高騰による評価額の上昇リスク: 2020年代に入り、ウッドショックや世界的なインフレの影響により、建築資材価格が歴史的な高騰を続けています。家屋の評価は、この再建築費を基に、経年劣化による減価率を適用して計算されます。築年数が古い建物であっても、再建築費の基準が大幅に上昇しているため、経年減価を相殺し、評価額が下がりにくい、あるいは上昇するという逆転現象が各地で発生しています。
- 構造・設備の影響: 高品質な設備や高い断熱性能を備えた建物は、再建築費が高くなるため、評価額も高くなります。特に、省エネ性能の高い賃貸住宅を新築・取得したオーナーは、資産価値と引き換えに、固定資産税の負担が増える可能性があります。
1-2. オーナーの具体的対応策
オーナーは、2027年度の評価替えに向けて、以下の準備を進めるべきです。
- 地価・建築費の動向モニタリング: 所有物件のあるエリアの地価公示価格や、直近の建築単価の動向を把握し、自身の物件の評価額上昇リスクを予測します。
- 評価額に異議がある場合の準備: 評価替え後の評価額に不服がある場合、納税通知書の交付を受けた日から原則として60日以内に固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出を行うことができます。そのため、日頃から不動産の市場価格や収益性を証明できる資料を整理しておくことが重要です。
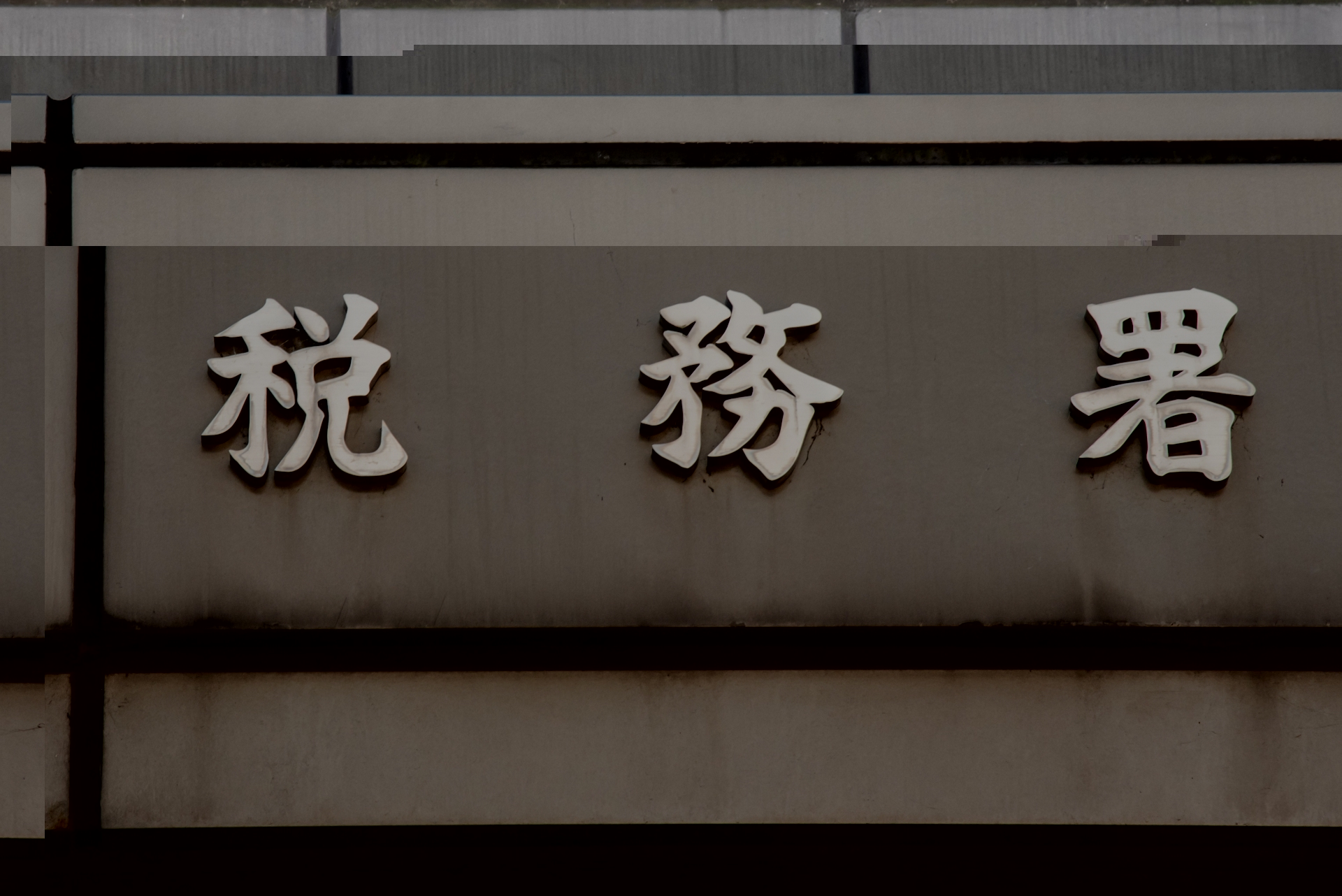
2. 相続税対策を根底から変える評価の見直しと是正の動き
相続税対策において、不動産は現金や有価証券に比べて評価額が低くなる(評価圧縮効果)ため、長らく有効な節税ツールとされてきました。しかし、国税庁は市場価格と相続税評価額の乖離是正に乗り出しており、特にタワーマンションへの対応は顕著です。
2-1. タワーマンション節税策の「封じ込め」と影響の拡大
2024年(令和6年)1月1日以降の相続から適用されているタワーマンション(超高層の居住用区分所有建物)の評価方法の見直しは、相続税評価における是正の動きを象徴しています。
- 改正の背景: 高層階の住戸は、市場では低層階より高値で取引されているにもかかわらず、従来の評価方法では専有部分の面積割合に基づいて評価され、市場価格との乖離が著しかったためです。
- 改正内容の詳細:
- 階層別補正率: 1階を100として、階が上がるごとに評価額が加算される仕組みが導入されました(およそ1階上がるごとに評価額が10%程度加算されるイメージ)。
- 築年数補正率: 築年数が古いタワーマンションは、市場価格が低下しにくいため、築年数に応じた補正も加味されます。
- 計算方法: これらの補正を施した評価額と、実際の売買事例等を参考に算出される**「乖離率」**を掛け合わせることで、市場価格に近い水準まで相続税評価額を引き上げます。
- 影響の波及: この改正はタワーマンションに特化したものですが、国税庁が「市場価格と相続税評価額の乖離」を看過しない姿勢を示したことは非常に重要です。今後は、タワーマンション以外の、極端に市場価格と評価額が乖離している不動産(例:都心の超高級戸建てなど)に対しても、同様の是正措置が検討される可能性をオーナーは念頭に置くべきです。
2-2. 賃貸不動産オーナーの生命線「小規模宅地等の特例」の見直し論点
賃貸アパート・マンションの敷地など、賃貸経営に使用されている土地は、**「貸付事業用宅地等」**として、小規模宅地等の特例の適用を受けることができ、最大50%の評価減が可能です。
- 懸念される見直し論点:
- 適用要件の厳格化: 現在、貸付事業用宅地等として特例を適用するには、被相続人が生前にその賃貸事業を営んでいたことなどが要件とされています。この「事業性」の判断基準がより厳格化され、極めて短期間の賃貸開始や、実態のない形式的な事業と判断されるケースでは、特例が適用できなくなる可能性があります。
- 評価減割合の縮小: 節税効果が非常に高い50%の評価減について、その割合が将来的に縮小される可能性も否定できません。特に、金融資産の逃避先として不動産が利用される状況が続けば、税制当局のメスが入るリスクが高まります。
2-3. オーナーの具体的対応策
相続税評価の是正は、すでに始まっています。
- 評価額の再シミュレーション: 特にタワーマンションを所有しているオーナーは、新評価基準に基づき相続税額を再計算し、資金計画の見直しを急ぐ必要があります。
- 生前贈与の活用: 相続税評価額が上昇する前に、暦年贈与(年間110万円まで非課税)や相続時精算課税制度を活用した不動産の生前贈与を検討すべきです。2024年以降の改正で、暦年贈与加算期間が3年から7年に延長されるなど、贈与税制も変化しているため、専門家との相談が不可欠です。

3. 来年以降の税制改正(2026年度以降)の動向とオーナー戦略
日本の税制は、少子高齢化、環境問題、経済成長の停滞といった複合的な課題に対応するため、常に改正が繰り返されています。2026年度(令和8年度)以降の税制改正議論で、不動産オーナーが特に注目すべきテーマを深掘りします。
3-1. 環境不動産・省エネ化に対する税制優遇の最大化
政府は「2050年カーボンニュートラル」の達成に向けて、既存住宅・建築物の省エネ化、特に**ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ゼブ:ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)**への移行を強力に推し進めています。
- 予想される優遇措置の方向性:
- 賃貸住宅の改修費用に対する優遇: 既存の賃貸アパートやマンションの断熱改修、高効率設備(給湯器、エアコンなど)導入に対する、特別償却(投資額の一部を経費として早期に計上できる)や固定資産税の減額特例の拡充が有力視されます。
- 長期的な優遇措置の創設: 短期的な優遇策だけでなく、高い省エネ性能を維持する不動産に対して、継続的な固定資産税の軽減措置や、売却時の譲渡所得の特別控除を設けるなど、資産価値向上と税制優遇を連動させる新たな仕組みが検討される可能性があります。
- オーナー戦略: 賃貸不動産の老朽化対策を検討する際、単なる修繕に留まらず、省エネ性能向上を最優先課題とすることで、将来的に税制優遇を受け、入居者へのアピールポイントを強化する二重のメリットを享受できます。
3-2. 空き家・遊休不動産に対する課税強化の可能性
全国で空き家が増加し社会問題となっている中、政府は「空き家対策特別措置法」を改正するなど、対策を強化しています。税制面からも、遊休不動産の活用を促す動きが加速する可能性があります。
- 固定資産税の「住宅用地の特例」見直し: 現在、住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により、固定資産税の課税標準額が最大6分の1に軽減されています。しかし、管理不全な「特定空き家」に指定されると、この特例が解除され、税負担が大幅に増えます。今後は、特定空き家の一歩手前の**「管理不全空き家」**に対しても、特例を解除する動きが加速することが予想されます。
- 低未利用土地の譲渡特例の拡充: 活用されていない低額な土地(低未利用土地)を売却した場合に、譲渡所得から100万円を控除できる特例がありますが、この適用要件の緩和や控除額の増額により、売却による市場への土地供給を促す可能性が考えられます。
3-3. 不動産所得(賃貸事業)に関する税制の適正化
賃貸事業を営む不動産オーナーの所得計算に関する論点も、常に税制改正の俎上に載ります。
- 減価償却制度の見直し: 現在の減価償却制度(特に定額法)は、実際の建物の価値減少スピードと必ずしも一致しないという指摘があります。将来的に、減価償却方法の選択肢の変更や、中古建物の耐用年数計算方法のさらなる見直しが検討される可能性があります。
- 必要経費の範囲の明確化: 不動産所得計算上の必要経費として計上できる範囲について、税務当局と納税者の間で争いになりやすい項目(例:自宅兼事務所の経費按分、海外不動産関連経費など)について、より詳細なガイドラインや法改正が行われる可能性があります。
4. 総括:オーナーとして取るべき「攻めと守り」の戦略
不動産オーナーは、評価替えという「守り」の視点と、税制改正を活用した「攻め」の視点の両方を持つ必要があります。
| 課題 | 視点 | 今すぐ取るべき行動 |
| 固定資産税(評価替え) | 守り(コスト管理) | 2027年評価替えに向けた評価額上昇リスクの予測と、資金繰りのシミュレーション。建築資材高騰による家屋評価額の確認。 |
| 相続税(評価是正) | 守り(資産防衛) | タワーマンション所有者は新基準での相続税額を再計算し、評価上昇を見越した**生前対策(贈与、法人活用など)**を最優先で実行。 |
| 省エネ化税制 | 攻め(投資・付加価値向上) | 老朽化した賃貸不動産の修繕計画を省エネ改修にシフトし、将来の税制優遇(特別償却、固定資産税減額)の恩恵を最大化する。 |
| 空き家対策 | 攻め・守り | 遊休地や空き家は「管理不全空き家」に指定される前に、売却や活用(リノベーション・賃貸)を進め、課税強化のリスクを回避する。 |
不動産経営の成功は、単なる賃料収入の最大化ではなく、税金という大きなコストをいかに適切に管理し、資産の総価値を将来に向けて高めていくかにかかっています。常に最新の税制動向を把握し、信頼できる税理士や不動産コンサルタントと連携して、多角的な対策を講じてください。
お名前とアドレスを入れるだけ!
大家業の常識が変わる。不動産市場の「今」を知れる、最新の資料を進呈!
聞きたいことがすぐ聞ける!
カンタンなご質問や、お急ぎの方はお電話が便利です!
家賃の滞納者がいて困っている…今の管理会社が仕事をしてくれない…
どんなお困りごとでも大丈夫!丁寧にご回答しますので、お気軽にお問い合わせください☆
お問い合わせ・ご相談はLINEでも受け付けております!
”まずは聞いてるみ”というお気持ちでも大丈夫です。お気軽にお問い合わせください☆