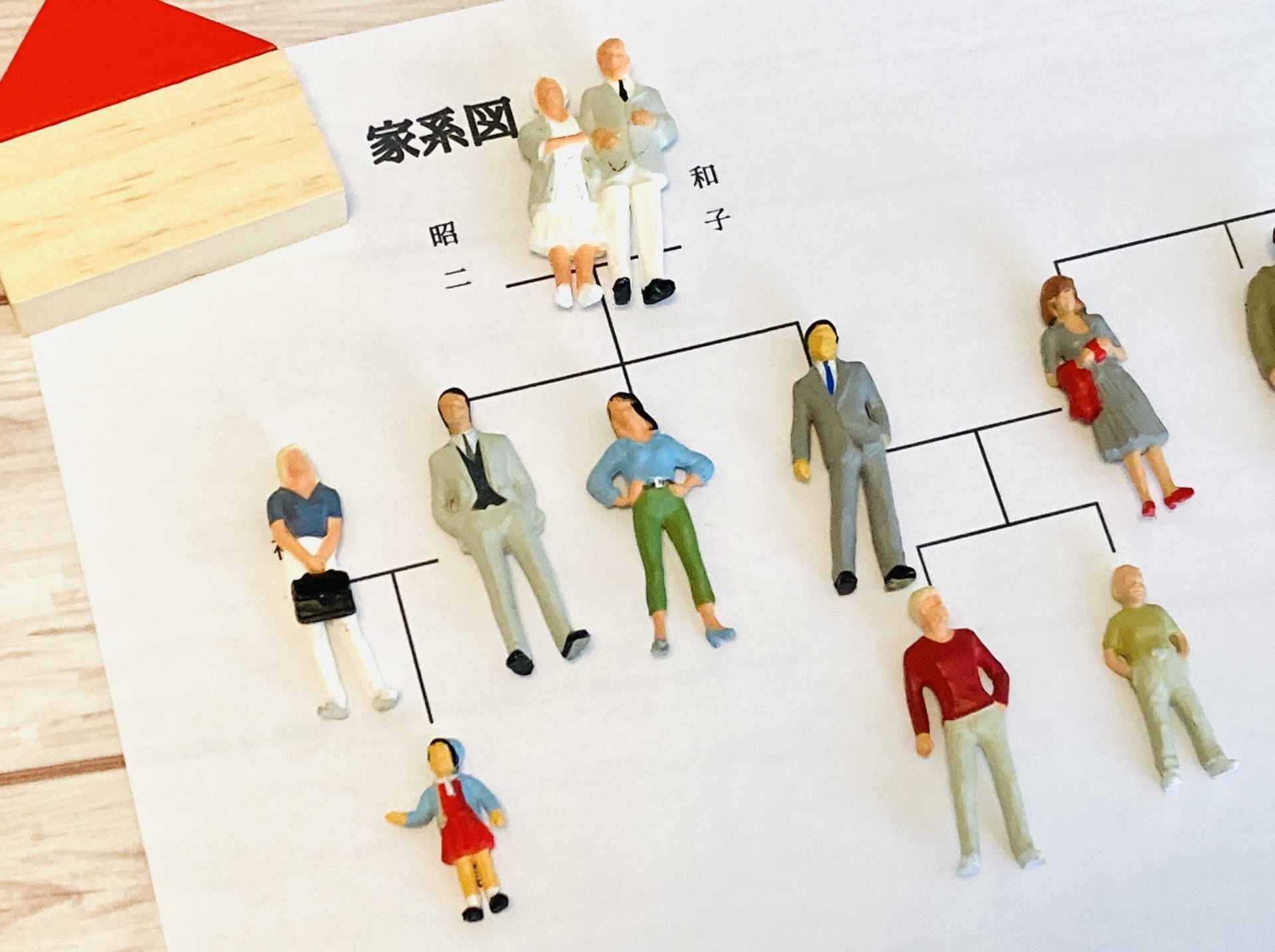はじめに:相続は「誰にでも」起こりうる身近な問題
「うちには大した財産なんてないから、相続でもめることなんてないだろう」 「相続について考えるのは、まだ先のことだ」
多くの方が、このように考えているかもしれません。しかし、相続は、財産の多少にかかわらず、誰の身にも起こりうる非常に身近な法律問題です。そして、いざその時を迎えると、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかという問題が、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。
特に、ご家族が亡くなられた悲しみの中で、複雑な手続きや話し合いを進めるのは精神的にも大きな負担となります。だからこそ、事前に基本的な知識を持っておくことが、ご自身と大切なご家族を守ることに繋がるのです。
日本の法律(民法)では、誰が相続人となり、どのくらいの割合で遺産を受け取るのかについて、基本的なルールが定められています。これを「法定相続」と呼びます。
この記事では、この「法定相続」のルールに焦点を当て、
・誰が相続人になるのか?(法定相続人)
・【パターン別】具体的な相続の割合は?(法定相続分)
・遺産に不動産が含まれる場合はどうすればいい?
・法定相続分と違う分け方はできるの?
といった疑問について、具体的な事例を交えながら、できる限り分かりやすく解説していきます。いざという時に慌てないため、そして円満な相続を実現するための一助となれば幸いです。
相続の基本ルール「誰が相続人になるのか?」
遺産相続について考える最初のステップは、「誰が相続する権利を持っているのか?」を正確に把握することです。法律で遺産を相続する権利が認められている人のことを「法定相続人」と呼びます。
配偶者は常に相続人
まず、大原則として覚えておきたいのが、亡くなった方(「被相続人」といいます)に法律上の配偶者(夫または妻)がいる場合、配偶者は常に法定相続人になるということです。内縁関係のパートナーは、残念ながら現在の法律では相続権が認められていません。
血族相続人には「順位」がある
配偶者以外の親族については、相続人になれる順位が決められています。これを「血族相続人」の順位といい、先の順位の人が一人でもいる場合、後の順位の人は相続人になることができません。
【法定相続人の順位】
・第1順位:子(およびその代襲相続人)
・第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
・第3順位:兄弟姉妹(およびその代襲相続人)
具体的に見ていきましょう。
◆ 第1順位:子 被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となります。
・実子、養子、認知された非嫡出子(婚外子)の間に、相続分での区別はありません。全員が平等に相続権を持ちます。
・被相続人が亡くなる前に子がすでに亡くなっていた場合で、その子にさらに子(つまり被相続人の孫)がいれば、その孫が親の権利を引き継いで相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。孫も亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続します(再代襲相続)。
◆ 第2順位:直系尊属(父母など) 被相続人に子や孫などの直系卑属が誰もいない場合、第2順位である被相続人の親(父・母)が相続人となります。
・父母が共に健在の場合は、2人とも相続人になります。
・父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が健在であれば、祖父母が相続人になります。このように、より世代が上の直系の親族に権利が移ります。
◆ 第3順位:兄弟姉妹 被相続人に子や孫などの直系卑属がおらず、親や祖父母などの直系尊属も全員亡くなっている場合に、初めて第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
・兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その兄弟姉妹に子(つまり被相続人の甥・姪)がいれば、その甥・姪が代襲相続します。
・ただし、子の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。甥・姪が亡くなっていても、その子がさらに代襲相続すること(再代襲相続)はありません。
この「順位」のルールを理解することが、相続割合を計算する上での大前提となります。
こちらの記事も読まれています!

【完全ガイド】ケース別・遺産の相続割合(法定相続分)
さて、誰が相続人になるのかが分かったところで、いよいよ本題である「具体的な相続割合(法定相続分)」について見ていきましょう。相続人の組み合わせによって、割合は異なります。ここでは最も一般的なパターンを網羅して解説します。
パターン1:相続人が「配偶者」と「子」の場合
最も多いのがこのケースです。
・配偶者:2分の1
・子:2分の1
子が複数いる場合は、子の取り分である2分の1を、その人数で均等に分けます。
<具体例> 夫が亡くなり、遺産が6000万円。相続人は妻と長男、長女の2人。
・妻の相続分:6000万円 × 2分の1 = 3000万円
・子の相続分全体:6000万円 × 2分の1 = 3000万円
・長男の相続分:3000万円 × 2分の1 = 1500万円
・長女の相続分:3000万円 × 2分の1 = 1500万円
パターン2:相続人が「配偶者」と「親(直系尊属)」の場合
被相続人に子がおらず、親が健在であるケースです。
・配偶者:3分の2
・親:3分の1
父母が共に健在の場合は、親の取り分である3分の1を、2人で均等に分けます(つまり、父6分の1、母6分の1となります)。
<具体例> 妻が亡くなり、遺産が6000万円。相続人は夫と、妻の母親。
・夫の相続分:6000万円 × 3分の2 = 4000万円
・妻の母親の相続分:6000万円 × 3分の1 = 2000万円
パターン3:相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合
被相続人に子も親もおらず、兄弟姉妹がいるケースです。
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合は、その取り分である4分の1を、人数で均等に分けます。
<具体例> 夫が亡くなり、遺産が6000万円。相続人は妻と、夫の兄と妹。
・妻の相続分:6000万円 × 4分の3 = 4500万円
・兄弟姉妹の相続分全体:6000万円 × 4分の1 = 1500万円
・夫の兄の相続分:1500万円 × 2分の1 = 750万円
・夫の妹の相続分:1500万円 × 2分の1 = 750万円
パターン4:配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がいない(既に亡くなっている、または独身だった)場合は、相続順位に従って、その順位の相続人が遺産をすべて相続します。
- 子のみがいる場合
- 子が遺産のすべて(100%)を相続します。複数いれば人数で均等に分けます。
- 子はおらず、親のみがいる場合
- 親が遺産のすべて(100%)を相続します。父母ともに健在なら2分の1ずつ分けます。
- 子も親もおらず、兄弟姉妹のみがいる場合
- 兄弟姉妹が遺産のすべて(100%)を相続します。複数いれば人数で均等に分けます。
【応用編】代襲相続がある場合の相続分
代襲相続が発生した場合、代襲相続人(孫や甥・姪)は、本来相続人であった人(亡くなった子や兄弟姉妹)が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。
<具体例:代襲相続> 夫が亡くなり、遺産が6000万円。相続人は妻と、既に亡くなっている長男の子(孫A、孫B)、そして長女。 この場合、相続人は「妻」「孫A」「孫B」「長女」の4人です。
・まず、基本の割合を確認します。配偶者2分の1、子2分の1です。
・妻の相続分:6000万円 × 2分の1 = 3000万円
・子の取り分は全体で3000万円です。これを長男と長女で分けるはずでした(各1500万円)。
・長女の相続分:本来の取り分である1500万円を相続します。
・孫Aと孫Bの相続分:長男が受け取るはずだった1500万円を、2人で均等に分けます。
-
- 孫A:1500万円 × 2分の1 = 750万円
- 孫B:1500万円 × 2分の1 = 750万円
このように、代襲相続が入ると少し計算が複雑になりますが、「亡くなった親の取り分をそのまま引き継ぐ」と覚えれば理解しやすいでしょう。
【最重要】遺産に不動産がある場合の分割方法と注意点
預貯金であれば、法定相続分に応じて1円単位で分けることができます。しかし、遺産の大部分が「自宅の土地・建物」といった不動産である場合、話は簡単ではありません。ナイフでケーキを切り分けるように、物理的に分割するのは困難だからです。
不動産という「分けにくい財産」をどうやって公平に分けるのか。これが相続で最もトラブルになりやすいポイントの一つです。ここでは、不動産の遺産分割における代表的な4つの方法を解説します。
1. 現物分割(げんぶつぶんかつ)
文字通り、遺産そのものを現物のまま分ける方法です。
- 例:「長男は自宅の土地・建物を、長女は別荘と預貯金を受け取る」というように、財産ごとに相続人を決める方法。
- 例:広大な土地であれば、測量して複数の土地に分け(「分筆」といいます)、それぞれを相続する方法。
メリット:不動産を売却せずに済み、相続人がそのまま利用したり住み続けたりできる。 デメリット:各相続人の法定相続分通りにきっちり分けるのが難しい。土地を分筆するには費用がかかる。
2. 換価分割(かんかぶんかつ)
不動産などの遺産を売却してお金に換え、その現金を相続分に応じて分配する方法です。
- 例:実家を3000万円で売却し、その代金を相続人2人で1500万円ずつ分ける。
メリット:各相続人の相続分通りに公平に分けられる。現金で受け取るため、その後の使い道も自由。 デメリット:売却には時間がかかり、仲介手数料や税金(譲渡所得税)などの費用が発生する。思い出のある実家を手放すことになる。希望の価格で売れるとは限らない。
3. 代償分割(だいしょうぶんかつ)
特定の相続人(例えば長男)が不動産などをすべて相続する代わりに、他の相続人に対して、その人の法定相続分に見合う現金などを支払う方法です。この支払うお金を「代償金」といいます。
- 例:価値3000万円の実家を長男が相続する。もう一人の相続人である長女には、本来の相続分である1500万円を、長男が自己資金から代償金として支払う。
メリット:家業を継ぐ人や、被相続人と同居していた人が、事業や生活の基盤となる不動産を守ることができる。 デメリット:不動産を相続する人に、代償金を支払えるだけの十分な資力(預貯金など)が必要。不動産の評価額を巡って意見が対立することがある。
※不動産の評価額※ 代償分割や現物分割で公平を期すためには、不動産の価値をいくらと見積もるかが非常に重要になります。一般的には、相続税の計算で使う「路線価」や「固定資産税評価額」、あるいは実際に市場で売買される価格に近い「時価(実勢価格)」などが基準とされます。どの評価額を用いるかは相続人間の話し合いで決めますが、ここで意見が食い違うとトラブルの原因になります。不動産鑑定士に鑑定を依頼するのも一つの方法です。
4. 共有分割(きょうゆうぶんかつ)
遺産である不動産を、複数の相続人の共有名義にする方法です。
- 例:実家を、長男と長女がそれぞれ持分2分の1ずつの共有名義で登記する。
一見、公平で簡単な方法に見えますが、専門家が最も推奨しない方法でもあります。なぜなら、将来的に非常に高い確率でトラブルの火種となるからです。
共有分割の危険性
- 売却や賃貸が困難に:不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば売れません。
- 管理方針での対立:修繕やリフォームなど、管理に関する意見がまとまらない可能性があります。
- 相続がさらに発生して複雑化:共有者の一人が亡くなると、その人の持分がさらにその相続人(配偶者や子)に引き継がれます。ネズミ算式に共有者が増えていき、関係者全員の合意形成はほぼ不可能になります。
とりあえず共有にしておく、という安易な選択は避け、できる限り上記の現物分割、換価分割、代償分割のいずれかの方法で解決するのが望ましいでしょう。
こちらの記事も読まれています!

遺言や話し合いで「法定相続分」と違う分け方はできる?
これまで解説してきた法定相続分は、あくまで法律が定める遺産分割の「目安」や「最低ライン」です。被相続人の意思や、相続人同士の話し合いによって、これとは異なる割合で遺産を分けることも可能です。
1. 「遺言書」がある場合:被相続人の意思を最優先
被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、原則としてその内容が法定相続分よりも優先されます。
- 「妻に全財産を相続させる」
- 「事業を手伝ってくれた長男に多めに財産を残したい」
- 「お世話になった内縁の妻に財産を遺贈する」
など、被相続人は法定相続人やその割合にとらわれず、自由に財産の分け方を指定できます。相続を「争続」にしないためにも、遺言書は非常に有効な手段です。
◆ 最低限の取り分「遺留分」に注意 ただし、遺言書も万能ではありません。兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言によっても侵害されない「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の遺産取得分が保障されています。
例えば、「愛人に全財産を譲る」という遺言があったとしても、残された配偶者や子は、自身の遺留分に相当する金額を愛人に対して請求することができます(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。遺留分の割合は、法定相続分の基本的に半分(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)となります。
2. 「遺産分割協議」で決める場合:相続人全員の合意が大前提
遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産がある場合は、相続人全員で誰がどの財産をどのように相続するのかを話し合って決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
この協議において、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けても全く問題ありません。
- 例:「母さんが今後も安心して暮らせるように、実家も預貯金も全部お母さんが相続することでいいよね?」と子供たちが合意すれば、配偶者が100%相続することも可能です。
- 例:長男が事業資金としてまとまった現金を必要としているため、他の兄弟が納得の上で、長男の取り分を多くすることもできます。
協議がまとまったら、その内容を証明する「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印します。この書類は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きの際に必要となる重要なものです。
もし、話し合いがまとまらない(協議が不成立となった)場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を交えて話し合いを進めることになります。
まとめ:円満な相続のために知っておきたいこと
今回は、遺産相続の割合について、基本的なルールから不動産がある場合の注意点までを詳しく解説しました。最後に、重要なポイントを振り返っておきましょう。
- 誰が相続人になるかは法律で順位が決まっている(①子 ②親 ③兄弟姉妹)。配偶者は常に相続人になる。
- 法定相続分は相続人の組み合わせによって割合が定められているが、これはあくまで目安。
- 遺言書があれば、その内容が最優先される。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には最低限の取り分である「遺留分」がある。
- 遺言書がない場合は、相続人全員による「遺産分割協議」で分け方を決める。全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方も可能。
- 遺産に不動産が含まれる場合、「換価分割」や「代償分割」など、分け方を工夫する必要がある。「共有分割」は将来のトラブルリスクが高いため慎重に。
相続は、法律や税金が絡む複雑な手続きです。特に不動産が関係する場合や、相続人同士の関係が複雑な場合は、当事者だけで解決しようとすると、かえって話がこじれてしまうことも少なくありません。
少しでも不安を感じたら、弁護士、司法書士、税理士といった専門家に相談することを強くお勧めします。専門家の客観的なアドバイスを得ることで、スムーズで円満な相続を実現するための道筋が見えてくるはずです。
ご自身の、そしてご家族の未来のために、この記事が正しい知識を得るための一助となれば幸いです。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい…現状の管理会社に不満がある…などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEでお問い合わせ可能です♪