アパートやマンションの賃貸経営は、単に家賃収入(キャッシュフロー)を得るだけでなく、税金とどう向き合うかで、その成果が大きく変わる「事業」です。経営者であるオーナーにとって、税金は最大のコストの一つであり、同時に、正しく理解すれば最強の「武器」にもなります。
しかし、不動産に関する税制は非常に複雑で、「知らなかった」では済まされないペナルティや、「知っていれば」回避できたはずの多額の税金が存在します。
この記事では、アパート・マンション経営の成功を目指すオーナー様に向けて、経営にかかる税金の全体像と、手元に資産を残すための「実践的な節税術」を、メリット・デメリット両面から徹底的に解説します。
1. なぜ税金対策が重要なのか? 賃貸経営における「税務メリット」と「リスク」
まず、賃貸経営における税金対策の「光と影」を正しく理解することがスタートラインです。節税というメリットばかりに目が行くと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
📈 メリット:税金対策がもたらす「4つの恩恵」
- 所得税・住民税の軽減(損益通算)サラリーマンオーナー(給与所得者)にとって最大のメリットの一つです。不動産経営で赤字が出た場合、その赤字を給与所得など他の所得と合算(=損益通算)できます。これにより、すでに納めた税金(源泉徴収された所得税)が戻ってくる(還付される)、あるいは翌年の住民税が安くなる効果が期待できます。
- 相続税評価額の大幅な圧縮現金や更地(さらち)で資産を持つよりも、アパートなどの「貸家」が建つ土地(=貸家建付地)として持つ方が、相続税を計算する際の評価額を大幅に下げることができます。これは、日本で最もポピュラーな相続税対策の一つです。
- 土地にかかる固定資産税の軽減土地は、更地のまま所有していると高い固定資産税がかかります。しかし、その土地にアパートやマンション(=人の居住用)を建てることで、「住宅用地の特例」が適用され、土地の固定資産税・都市計画税が最大で1/6にまで軽減されます。
- 経費計上による課税所得のコントロール事業であるため、経営にかかった費用(管理費、修繕費、借入金利子、専門家への報酬など)を必要経費として計上できます。これにより、課税対象となる所得(=儲け)を正しく圧縮することが可能です。
📉 デメリット:税金対策の「4つのリスク(注意点)」
- 税制の複雑さと改正リスク不動産税制は非常に複雑であり、かつ毎年のように改正が行われます。「去年までは有効だった節税策が、今年は使えない(あるいは効果が薄れた)」ということは日常茶飯事です。常に最新の知識が求められます。
- 申告ミスによるペナルティ経費計上の範囲を間違えたり、減価償却の計算を誤ったりすると、税務調査で指摘され、本来納めるべき税金に加えて「過少申告加算税」や「延滞税」といったペナルティ(追徴課税)が科されるリスクがあります。
- 「節税」と「経営」の混同「赤字を出して損益通算する」こと自体が目的化してしまうと、本末転倒です。赤字(キャッシュフローは黒字だが、帳簿上は赤字)なら良いのですが、本当にお金が出ていくだけの赤字経営は、資産を増やすどころか減らしてしまいます。
- 収入がなくても発生するコスト最大のデメリットはこれです。たとえ空室が続き、家賃収入がゼロであっても、固定資産税や借入金の利息(元本も)は容赦なく発生します。税金対策以前に、安定した賃貸経営(入居率の維持)が最も重要です。
2. 【第1の節税】所得税・住民税をどう抑えるか?
賃貸経営で得た所得は「不動産所得」として、毎年(2月16日~3月15日)に確定申告が必要です。この不動産所得の計算方法を理解することが、所得税・住民税節税の第一歩です。
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
この「不動産所得」が赤字(マイナス)になった場合、前述の「損益通算」が可能になります。
最大の武器「減価償却費」を使いこなす
所得税節税の鍵は「必要経費」です。その中でも最も重要かつ強力なのが**「減価償却費」**です。
- 減価償却費とは?建物や設備は時間とともに価値が下がっていきます。その価値の減少分を、法定耐用年数(法律で定められた使用可能な期間)にわたって、毎年少しずつ経費として計上していく仕組みです。
- なぜ強力なのか?減価償却費は、**「実際にはオーナーの財布からお金が出ていかないにも関わらず、帳簿上は経費として計上できる」**費用です。例えば、減価償却費が年間300万円計上できれば、他の収支がトントンでも、帳簿上は「300万円の赤字」となり、この赤字を給与所得などと損益通算できるのです。
- 構造別・法定耐用年数(例)
- 木造(W造):22年
- 軽量鉄骨造(S造、骨格材の厚さによる):19年または27年
- 重量鉄骨造(S造):34年
- 鉄筋コンクリート造(RC造):47年
<オーナーへのアドバイス>
耐用年数が短いほど、1年あたりに計上できる減価償却費は大きくなります。これが、あえて「中古の木造アパート」を購入し、短期間で大きく減価償却費を計上して節税する(=損益通算する)手法が流行した理由です。(※ただし、2020年度の税制改正により、海外中古不動産を使った節税など、一部の過度な手法には規制が入っています。)
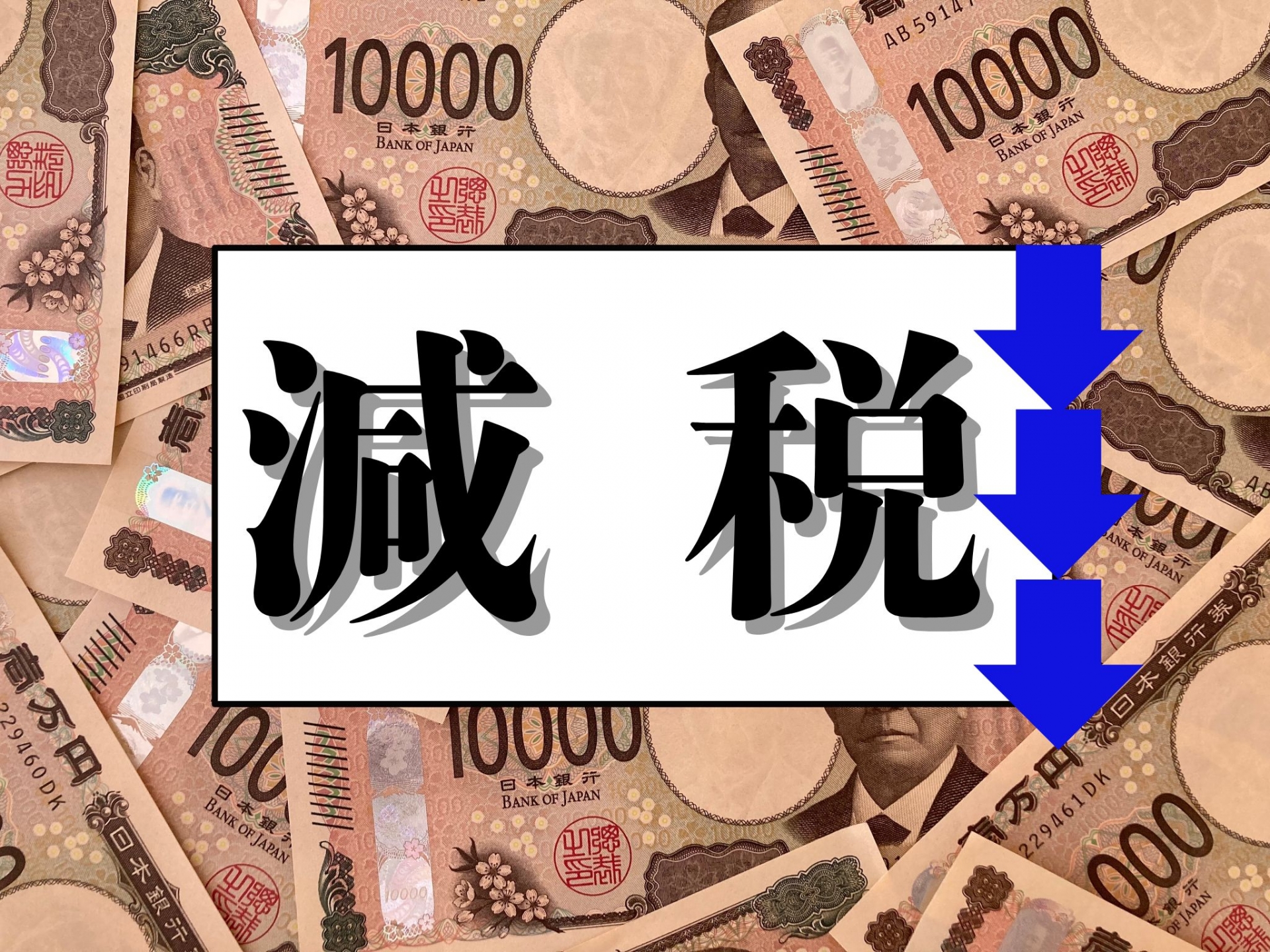
「経費」にできるもの、注意が必要なもの
どこまでが経費になるのか、その線引きは非常に重要です。
| 経費にできるもの(代表例) | 経費にできないもの(代表例) |
| ✅ 管理会社への委託料、清掃費 | ❌ 借入金の「元本」返済額 |
| ✅ 固定資産税、都市計画税、不動産取得税 | ❌ オーナー個人の所得税、住民税 |
| ✅ 損害保険料(火災保険、地震保険料) | ❌ オーナー個人の飲食代や被服費 |
| ✅ 修繕費、リフォーム費用 | ❌ 資本的支出(資産価値を高める支出)※ |
| ✅ 借入金の「利息」部分 | ❌ 交通費(プライベートとの区別が曖 F |
| ✅ 税理士、司法書士への報酬 | |
| ✅ 入居者募集のための広告宣伝費 | |
| ✅ 現地調査やセミナー参加のための交通費、通信費 |
※最重要注意点:「修繕費」 vs 「資本的支出」
- 修繕費(経費になる): 壊れたものを直す、元の状態に戻すための費用(例:壊れた給湯器の交換、壁紙の張り替え)。その年の経費として一括計上できます。
- 資本的支出(資産になる): 元の状態より良くする、資産価値を高めるための費用(例:間取りを2DKから1LDKに変更、屋上に太陽光パネルを設置)。これは「経費」ではなく「資産」とみなされ、減価償却を通じて何年にも分けて経費化(=償却)しなければなりません。
この判断を誤ると、税務調査で「これは修繕費ではなく資本的支出だ」と指摘され、一括計上した経費が否認され、多額の追徴課税が発生する可能性があります。
「青色申告」で節税を加速させる
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。不動産経営を行うなら、迷わず「青色申告」を選択すべきです。
- 青色申告の主なメリット
- 青色申告特別控除: 最大65万円(または55万円、10万円)を、不動産所得から無条件で差し引くことができます。
- 赤字の3年間繰越: 経営が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。(例:1年目▲300万、2年目+200万 → 2年目の所得は0円、残り▲100万を3年目に繰越)
- 家族への給与(青色事業専従者給与): 家族に管理業務などを手伝ってもらっている場合、その給与を全額経費にできます。(白色申告では上限あり)
- 青色申告(65万円控除)の主な要件
- 事業的規模であること(通称:5棟10室基準):
- アパートなら「10室」以上
- 戸建てなら「5棟」以上
- (※この基準を満たさなくても「10万円控除」は受けられる可能性が高いです)
- 複式簿記で記帳していること。
- e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存を行うこと。(行わない場合は55万円控除)
- 事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出すること。
- 事業的規模であること(通称:5棟10室基準):
3. 【第2の節税】固定資産税・都市計画税をどう抑えるか?
毎年1月1日時点の不動産所有者に課されるのが「固定資産税」と「都市計画税」(市街化区域内のみ)です。これらは経営が赤字でも容赦なくかかります。
なぜアパートを建てると土地の税金が安くなる?
最大の節税策は**「小規模住宅用地の特例」**を適用させることです。
人が住むための建物(アパート、マンション、戸建て)が建っている土地は、税金が優遇されます。
- 住宅用地の特例
- 200㎡以下の部分(小規模住宅用地)
- 固定資産税:評価額 × 1/6
- 都市計画税:評価額 × 1/3
- 200㎡を超える部分(一般住宅用地)
- 固定資産税:評価額 × 1/3
- 都市計画税:評価額 × 2/3
- 200㎡以下の部分(小規模住宅用地)
更地(非住宅用地)にはこの特例がないため、税額に何倍もの差が出ます。
オーナーが実践できる具体策
- 【土地活用】空き地・更地・駐車場にアパートを建てる(元のコラム具体例3)最も分かりやすい節税策です。固定資産税が更地の最大1/6になるため、税負担が激減します。長期間放置している空き地や、収益性の低い駐車場(※駐車場は住宅用地ではないため特例対象外)を持っている場合、アパート建築は税金面で非常に有効な活用法です。
- 【新築時】建物の新築軽減措置も活用する土地だけでなく、新築した「建物」にも軽減措置があります。
- 3階建て以上の耐火・準耐火建築物(マンション等):新築後5年間、建物の固定資産税が1/2
- 上記以外の一般住宅(アパート等):新築後3年間、建物の固定資産税が1/2
- 【設計時】「戸数×200㎡」を意識する(元のコラム具体例1, 4)特例が最大(1/6)になるのは「200㎡以下」の部分です。例えば2000㎡の広大な土地に1棟だけ建てても、200㎡を超える1800㎡部分は1/3(または2/3)課税です。しかし、この土地に10戸のアパートを建てた場合、「1戸あたり200㎡まで」特例が使えるため、2000㎡(=10戸 × 200㎡)の土地全体が1/6の特例対象となります。アパートの「戸数」が節税において非常に重要になるのです。
- 【併用住宅】自宅部分と賃貸部分のバランス(元のコラム具体例2)1階を賃貸、2階を自宅にするような「賃貸併用住宅」でも、住宅用地の特例は適用されます。ただし、建物の床面積のうち「居住部分の割合」に応じて特例が適用される土地の面積が変わるため、税理士やハウスメーカーと最適な設計を相談することが不可欠です。
4. 【第3の節税】相続税をどう抑えるか?
「親の相続対策でアパート経営を勧められた」という話はよく聞かれます。なぜアパート経営が相続税対策になるのか、その「3つの評価減」の仕組みを解説します。
仕組み1:建物の評価減(建築費と評価額の差)
現金を1億円持っている人が相続を迎えた場合、相続税評価額は当然「1億円」です。
しかし、その1億円でアパートを建築した場合、相続税を計算する際の建物の評価額は、建築費(時価)ではなく**「固定資産税評価額」**で計算されます。
固定資産税評価額は、建築費のおおむね50%~70%程度とされています。
つまり、1億円でアパートを建てた瞬間、相続税の評価上は「5,000万~7,000万円」の資産価値となり、3~5割の評価減が実現できます。
仕組み2:土地の評価減(貸家建付地)
さらに、そのアパートが建っている土地(元々所有していた土地)の評価も下がります。
自分で使っている土地(自用地)や更地と違い、入居者に「貸している」土地は、オーナーが自由に利用・売却できない(=権利が制限されている)とみなされます。
この制限分、評価額が割り引かれるのが**「貸家建付地(かしやたてつけち)」**評価です。
評価額は一般的に、更地(自用地)評価額の約80%程度(※地域や借地権割合による)となり、約2割の評価減が期待できます。
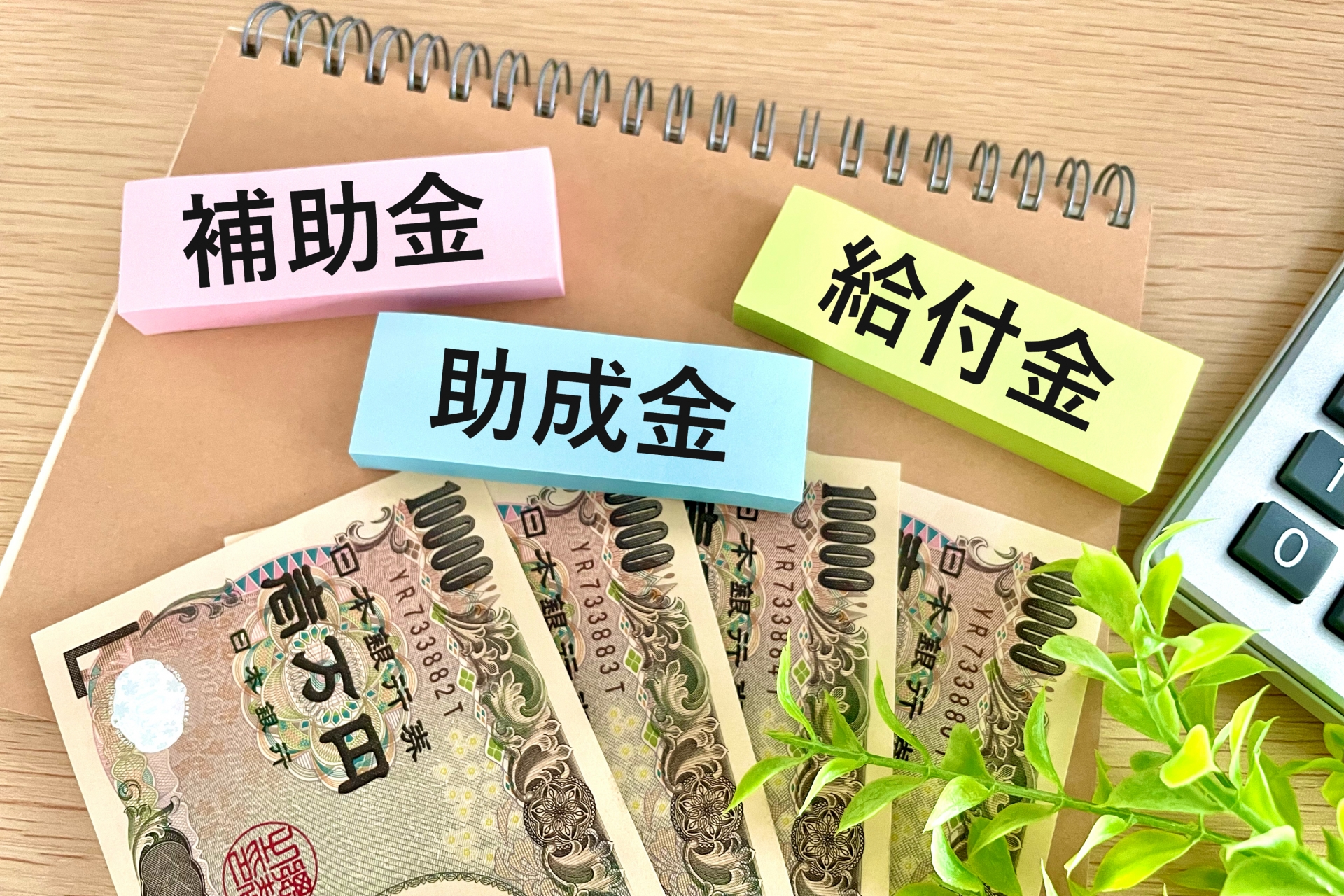
仕組み3:土地の特例(小規模宅地等の特例)
仕組み2(貸家建付地)で評価を下げた上で、さらに使える特例があります。
相続した土地で「引き続き賃貸経営を行う」場合、「小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)」が適用できれば、土地の評価額を200㎡まで、さらに50%減額できます。
<相続税対策のまとめ>
現金1億円と更地(評価額1億円)を持つAさんが、その現金で更地にアパートを建てた場合…
- 現金1億円 → 建物(評価額 約6,000万円)に【▲40%】
- 更地1億円 → 貸家建付地(評価額 約8,000万円)に【▲20%】
- さらに「小規模宅地等の特例」で土地評価額が【▲50%】
このように、複数の評価減を組み合わせることで、相続税評価額を劇的に圧縮できるのです。(※注:元コラムの「80%評価減」は自宅(特定居住用)の場合であり、賃貸用地(貸付事業用)は「50%減」が原則です。)
<オーナーへのアドバイス>
相続税対策は非常に有効ですが、危険も伴います。「相続税対策のため」だけに、入居者が見込めない土地に多額の借金をしてアパートを建てては、相続税は減っても、残された家族が空室と借金返済に苦しむ「負動産」を残すことになります。あくまで「賃貸経営」として成立することが大前提です。
5. 【上級編】いつ「法人化」を検討すべきか?
経営規模が大きくなり、不動産所得(利益)が増えてくると、個人事業主のままでは税率が非常に高くなります。
- 個人(所得税+住民税):所得が増えるほど税率が上がる「累進課税」。最大で約55%。
- 法人(法人税など):利益がいくらでも税率はほぼ一定。「実効税率」は**約25%~35%**程度。
「法人化」検討のタイミング
一般的に、不動産所得(経費を引いた後の利益)が安定して800万円~1,000万円を超えるようになってきたら、法人化(=資産管理会社を設立)を検討するタイミングです。
個人の税率が法人の実効税率を上回る「分岐点」だからです。
法人化のメリット
- 税率差の活用: 上記の通り、個人の最高税率(55%)より法人の税率(~35%)が低いため、利益が大きくなるほど節税効果が高まります。
- 経費計上の範囲拡大:
- 役員報酬: オーナー自身や家族に「給与(役員報酬)」を支払えます。この給与には「給与所得控除」が使えるため、個人で全額所得にするより税金上有利です。
- 退職金: オーナー自身や家族に退職金を支払うことができ、これは税金上非常に優遇されています。
- 生命保険料: 個人では一部しか控除できない生命保険料も、法人契約なら全額または半額を経費にできる商品があります。
- 相続対策: 個人の資産を法人に移すことで、個人の相続財産を増やさない(=将来の相続税を抑える)効果や、法人の「株価」として対策を講じることが可能になります。
法人化のデメリット(注意点)
- 設立・維持コスト: 会社設立費用や、税理士への報酬(個人より高額になる)がかかります。
- 社会保険料の負担: 法人化すると、オーナー(役員)も社会保険への加入が義務となり、その保険料負担(会社と個人で折半)が発生します。
- 均等割: 経営が赤字であっても、法人住民税の「均等割(最低でも年間7万円程度)」は必ず発生します。
6. まとめ:成功するオーナーは「経営」と「税務」を両輪で考える
アパート・マンション経営における税金対策は、知恵と工夫次第で大きな成果を生む、奥深い世界です。
しかし、忘れてはならないのは、節税はあくまで「資産形成の手段」であり、「目的」ではないということです。目先の節税(例:損益通算のための赤字経営、過度な修繕)にとらわれ、最も重要な「キャッシュフロー(手残りのお金)」を悪化させては元も子もありません。
不動産税制は、専門家である税理士でさえ判断が分かれるほど複雑で、かつ毎年変化します。
成功するオーナーとは、賃貸経営のプロであると同時に、税務の重要性を理解し、信頼できる「不動産に強い税理士」をパートナーにつけ、常に最新の情報を学び続ける「経営者」なのです。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい…現状の管理会社に不満がある…などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEでお問い合わせ可能です♪

















