-

東京都江戸川区の賃貸管理 |近隣トラブルについて
トラブル内容 〇〇東京都江戸川区の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例〇〇 先日、弊社管理物件の賃貸アパートにご入居いただいているお客様より隣の部屋の方についての相談との事で、お問い合わせをいただきました。 詳しい状況を入居者様へヒアリング... -

神奈川県川崎市の賃貸管理 | テレビが映らない不具合
トラブル内容 ○○神奈川県川崎市の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例○○ 先日、弊社管理物件のアパートにご入居いただいているご入居者様より「テレビが映らなくなった」というお問い合わせをいただきました。 画面には「E202 受信できません」... -

東京都千代田区の賃貸管理 | オートロックの故障
トラブル内容 ○○東京都千代田区の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例○○ 先日、弊社管理物件のアパートにご入居いただいているご入居者様より「オートロックの扉が自動で閉まってくれずに開きっぱなしになってしまっているので、早急に何とかして欲しい... -

東京都北区の賃貸管理 | 雨漏り被害
トラブル内容 ○○東京都北区の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例○○ 先日、当社管理物件で退去立会時に【窓枠の木の部分が腐ってしまいボロボロになっている】といった状況を確認いたしました。 退去者へどうしてこうなっていしまったのかをヒア... -

東京都江戸川区の賃貸管理 | ガスコンロの不具合について
トラブル事例 〇〇東京都江戸川区の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例〇〇 先日、弊社管理物件の賃貸マンションにご入居いただいているお客様より「ガスコンロが点かなくなった」というお問い合わせがございました。 火が点かないと言っても原因は様々... -
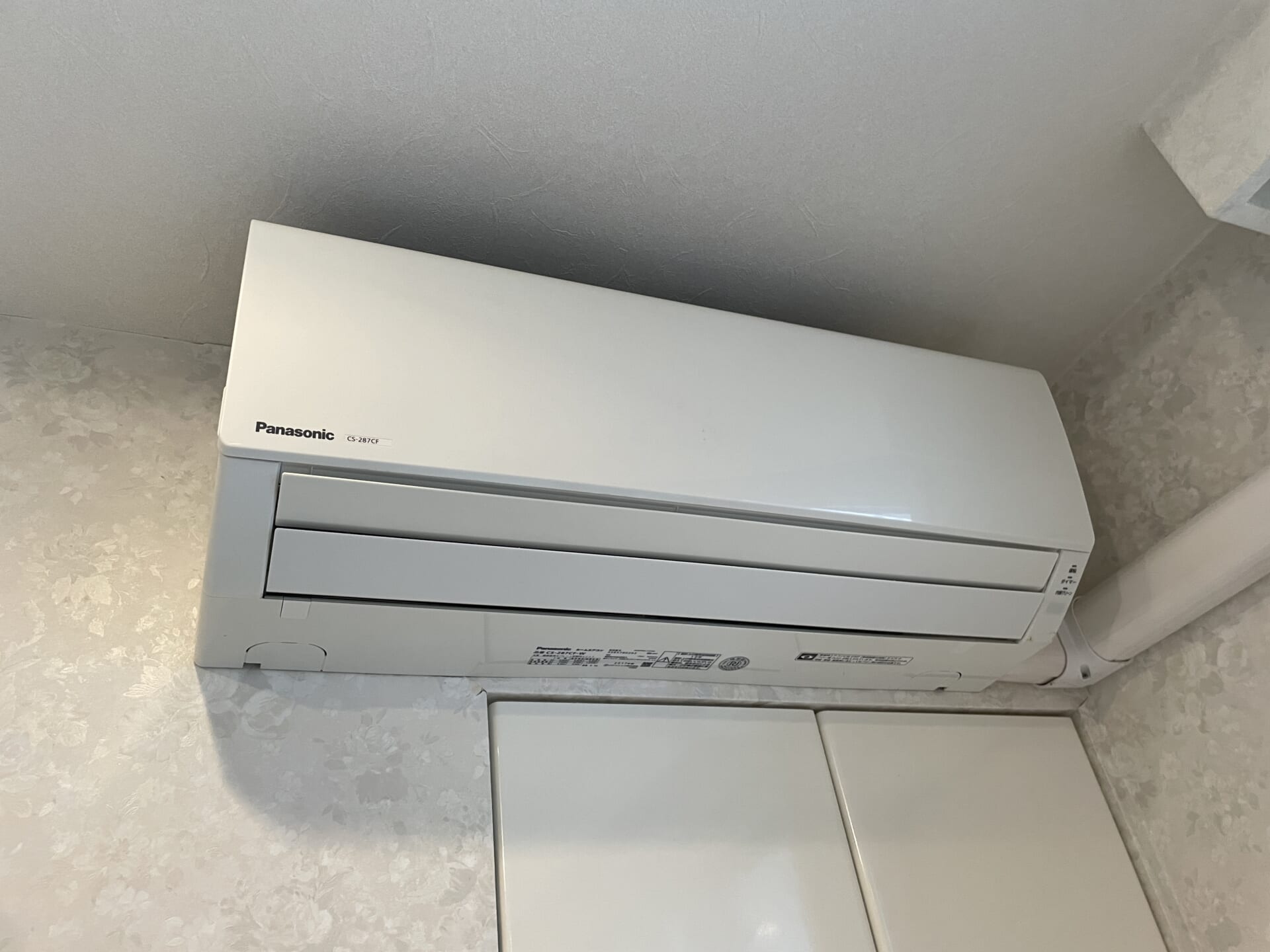
東京都足立区の賃貸管理 | エアコン不具合について
トラブル事例 〇〇東京都足立区の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例〇〇 先日、弊社管理物件の賃貸マンションにご入居いただいているお客様より「エアコンをつけてもなかなか冷えない」「エアコンから水が垂れてくる」などのお問い合わせが数多くござ... -

東京都板橋区の賃貸管理|設備不良
〇〇東京都板橋区の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例〇〇 弊社管理物件のご入居者様より、「お風呂のドアが外れてしまった」「通風孔の下部が黒ずんでいる」というご連絡をいただきました。 お風呂は四季問わず日々使うものなのでドアが締められない... -
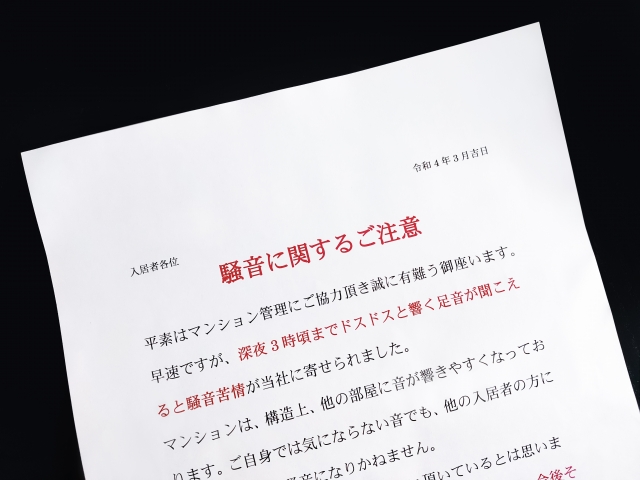
千葉県船橋市の賃貸管理 |騒音問題について
トラブル内容 〇〇千葉県船橋市の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例〇〇 先日、弊社管理物件の賃貸アパートにご入居いただいているお客様より「隣の部屋から深夜の時間帯に話し声などが響いており、眠れないレベルなのでどうにかならないか?」との事... -

東京都練馬区の賃貸管理|シーリングライトの取り付け
〇〇東京都練馬区の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例〇〇 弊社管理物件のご入居者様より、照明の調子が悪いというご連絡をいただきました。 症状としましては ・突然しばらくの間点灯しなくなり、たまに2~7日ぐらい点灯したりを繰り返している。 ・... -

神奈川県川崎市の賃貸管理|ゴミ捨て場トラブル
トラブル内容 神奈川県横浜市の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例。 先日当社管理物件のオーナー様より、ゴミ捨て場にあるゴミステーションの取っ手が壊れたので修理してほしいと依頼がありました。 日々使うものですので修理が完了するまでの間も破損...
trouble




