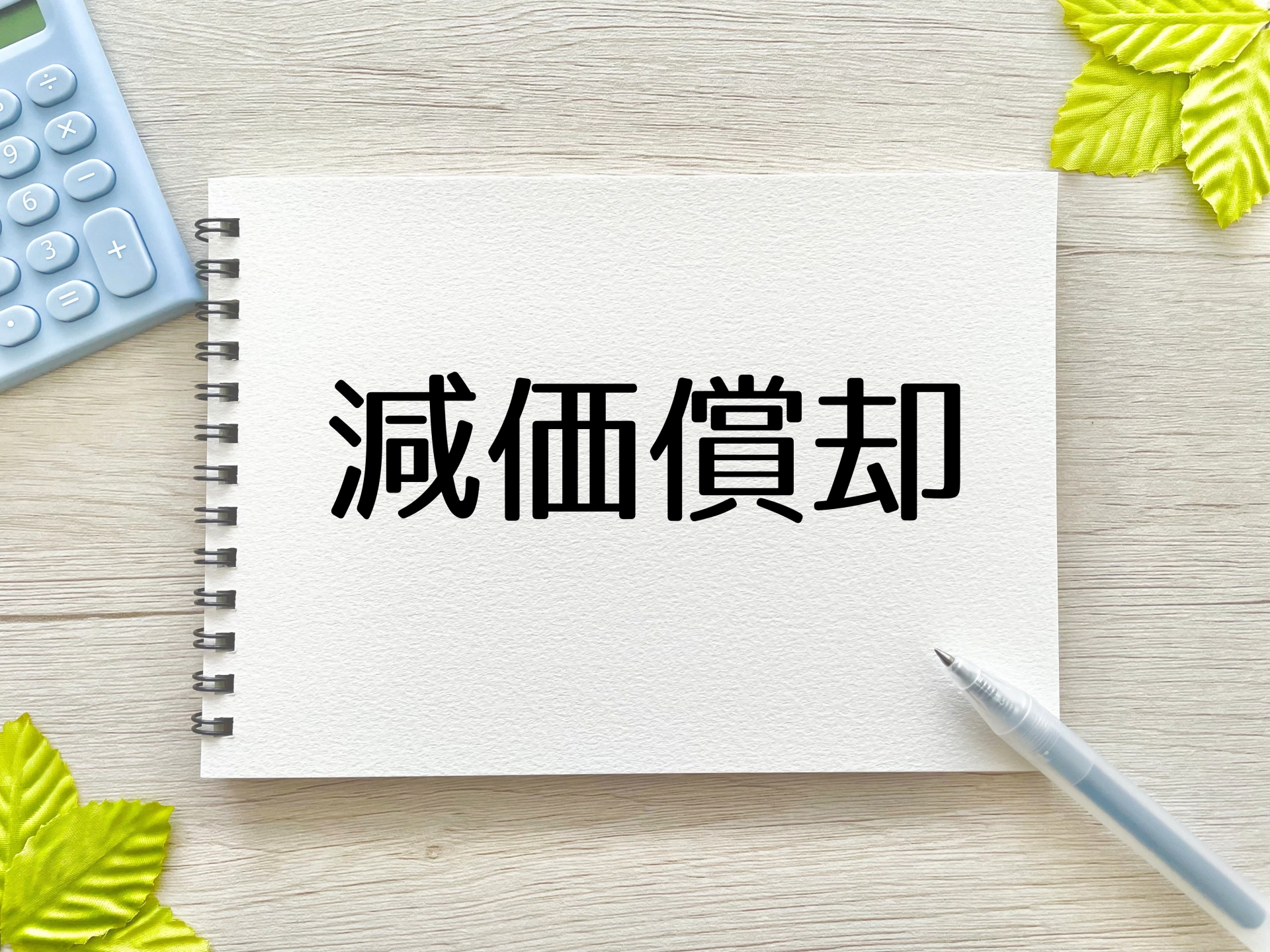はじめに:賃貸経営の新たな羅針盤としての「国の補助制度」
賃貸物件のオーナーにとって、空室リスクの低減と長期的な資産価値の維持・向上は、経営の根幹を揺るがす永遠のテーマです。少子高齢化による人口構造の変化、新築物件の供給過多、そして多様化・高度化する入居者のニーズ。これらの荒波を乗り越え、安定した賃貸経営を続けるためには、もはや「建てて貸すだけ」の時代は終わりを告げ、戦略的な物件管理、とりわけ時代に合わせた「リフォーム」の重要性が日に日に高まっています。
しかし、リフォームには当然ながら多額のコストがかかります。特に、耐震補強や省エネルギー化といった大規模な改修は、その費用対効果を見極めるのが難しく、二の足を踏んでいるオーナー様も少なくないのではないでしょうか。
そこで本コラムでは、こうしたオーナー様の悩みに応えるべく、国が主導する「賃貸物件のリフォーム支援制度(補助金制度)」に焦点を当て、その全貌と活用法を徹底的に解説します。これらの制度は、単なるコスト削減の手段にとどまりません。国の政策目標(例えば、省エネ化の推進、子育てしやすい環境整備、良質な住宅ストックの形成など)と連動しており、補助金を活用してリフォームを行うことは、入居者から選ばれる競争力の高い物件へと生まれ変わらせ、結果として長期的な経営安定化に繋がる、極めて有効な「投資」となり得るのです。
本稿が、所有物件の価値を最大化し、持続可能な賃貸経営を目指す全てのオーナー様にとって、有益な羅針盤となることを願っています。
なぜ今、賃貸物件のリフォームが求められるのか?
補助金の具体的な話に入る前に、なぜこれほどまでにリフォームの重要性が叫ばれているのか、その背景を整理しておきましょう。
賃貸市場の競争激化と入居者ニーズの変化
アパートやマンションの供給は依然として多い一方、日本の総人口は減少局面に入っています。つまり、入居者の獲得競争はますます激化していくことを意味します。かつては「立地」が最重要視されましたが、今やそれだけでは十分ではありません。在宅ワークの普及で住環境の快適性を求める声が高まり、「断熱性が高く、夏涼しく冬暖かい」「インターネット環境が快適」「セキュリティがしっかりしている」といった付加価値が、物件選びの重要な決め手となっています。
「省エネ性能」という新たな物件価値
近年の電気代高騰は、入居者の光熱費に対する意識を大きく変えました。物件情報サイトで「ZEH-M(ゼッチ・マンション)」や「省エネ」といったキーワードで検索する入居者も増えています。断熱性能の高い窓への交換や、高効率な給湯器の導入といった省エネリフォームは、月々の光熱費を削減できるため、入居者にとって家賃が数千円安いことと同等、あるいはそれ以上の価値を持つようになっています。これは、オーナーにとって家賃下落を防ぎ、むしろ付加価値として家賃設定に反映させることも可能なアピールポイントとなります。
多様化するライフスタイルへの対応
単身者、DINKS、子育て世帯、高齢者世帯など、入居者のライフスタイルは様々です。例えば、子育て世帯からは「子供の安全に配慮された設計」や「居住者同士が交流できるスペース」などが求められます。また、高齢化社会の進展に伴い、「手すりの設置」や「段差の解消」といったバリアフリー性能も、長く安心して住み続けてもらうための重要な要素です。画一的な間取りや設備では、こうした多様なニーズを捉えることはできません。
資産価値の維持・向上
建物は時間と共に物理的に劣化しますが、適切なメンテナンスやリフォームを行わなければ、その価値は加速度的に下落します。特に、見えない部分の構造躯体の劣化や、時代遅れの設備は、将来的な売却や担保価値にも大きく影響します。国の補助制度が後押しするような「性能向上リフォーム」は、目先の空室対策だけでなく、大切な資産そのものの価値を未来にわたって守り、高めるための不可欠な投資なのです。
【2025年版】オーナーが活用できる!国の主要リフォーム補助金制度
それでは、いよいよ本題である国の補助金制度について、目的別に詳しく見ていきましょう。国は現在、「省エネ」「子育て支援」「住宅ストックの長寿命化」などを柱に、様々な支援制度を用意しています。ここでは、特に賃貸物件オーナーが活用しやすい代表的な制度を4つご紹介します。
ケース①:物件の資産価値を抜本的に高めるなら「長期優良住宅化リフォーム推進事業」
【制度の目的】
この事業は、既存の住宅を長く、良好な状態で使い続けるために、建物の性能を総合的に向上させるリフォームを支援するものです。「つくっては壊す」から「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会への転換を目指す、国の住宅政策の根幹をなす制度と言えます。賃貸物件も対象であり、質の高い住宅ストックを形成することで、物件の資産価値を飛躍的に高めることが期待できます。
【対象となる工事】
この補助金を得るためには、リフォーム前に専門家による「インスペクション(建物状況調査)」を行い、見つかった劣化事象を補修することが必須となります。その上で、以下のいずれかの性能向上工事を行う必要があります。
- A:必須項目(いずれか1つ以上実施)
- 構造躯体等の劣化対策:柱や土台の防腐・防蟻処理、屋根の防水工事など
- 耐震性:耐震診断の結果に基づく補強工事(旧耐震基準の建物は必須)
- 省エネルギー対策:断熱材の追加、高断熱窓への交換など
- B:任意項目(Aと合わせて行うことで補助額が加算)
- 維持管理・更新の容易性:点検・補修がしやすい給排水管への交換など
- 高齢者等対策(バリアフリー改修):手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡幅など
- 子育て世帯向け改修:対面キッチンへの変更、防犯カメラの設置、キッズスペースの整備など
- 防災性の向上:感震ブレーカーの設置、ガラスの飛散防止対策など
【補助額】
リフォーム後の住宅性能に応じて、1戸あたり最大160万円(長期優良住宅(増改築)認定を取得する場合)の補助が受けられます。補助率は、かかった工事費の3分の1です。
【オーナーにとってのメリット】
- 資産価値の飛躍的向上:「長期優良住宅」の認定を取得すれば、国が認めた「質の高い住宅」として、売買時や融資審査で有利になる可能性があります。
- 競合物件との圧倒的な差別化:耐震性や省エネ性といった目に見えない性能を客観的な指標でアピールでき、入居者に安心感と快適性を提供できます。
- 税制上の優遇措置:認定を取得すると、固定資産税の減額措置や、所得税の特別控除などが受けられる場合があります。
- 長期的な修繕コストの抑制:計画的な維持管理が前提となるため、将来的な大規模修繕のコストを平準化しやすくなります。
こちらの記事も読まれています!

ケース②:子育て世帯を明確なターゲットにするなら「子育て支援型共同住宅推進事業」
【制度の目的】
少子化対策の一環として、子育て世帯が安心して暮らせる住環境を整備することを目的とした制度です。共同住宅(アパート・マンション)を対象に、子どもの安全確保や、居住者間のコミュニティ形成に資するリフォームを支援します。
【対象となる工事】
- 子どもの安全・安心に資する改修
- 事故防止:バルコニーへの転落防止手すりの設置、窓の補助錠、指はさみ防止機能付きドア、浴室扉の外鍵設置など
- 防犯対策:防犯カメラ、モニター付きインターホン、防犯性の高い玄関ドアへの交換など
- 見守り:キッチンからリビングが見渡せる対面キッチンへの改修など
- 子育て期の暮らしやすさに資する改修
- 家事負担軽減:宅配ボックスの設置
- コミュニティ形成:共用部へのキッズスペース、プレイルーム、談話コーナーの設置
【補助額】
対象工事費の3分の1、1戸あたり最大30万円が補助されます。
【オーナーにとってのメリット】
- 明確なターゲティングによる空室対策:「子育て世帯歓迎」というメッセージを具体的に打ち出すことができ、ファミリー層の入居希望者を効率的に集められます。
- 入居者の長期定着:子育てしやすい環境は、子どもの成長と共に転居を考える世帯を引き留める要因となり、長期入居に繋がります。
- 物件のイメージアップ:地域社会に貢献する姿勢を示すことができ、物件全体のブランドイメージ向上に貢献します。
ケース③:省エネ性能を手軽にアップし、入居者にアピールするなら「住宅省エネ2025キャンペーン」関連事業
「住宅省エネ2025キャンペーン」は、複数の省エネ関連補助事業をまとめた総称です。ここでは、特に賃貸オーナーが取り組みやすい2つの事業を紹介します。
1. 先進的窓リノベ2025事業 熱の出入りが最も大きい「窓」の断熱改修に特化した、非常に補助額の大きい制度です。
- 対象工事:既存の窓を、断熱性能の高いガラスやサッシに交換する工事。内窓の設置も対象。
- 補助額:工事内容や窓の性能・サイズに応じて定額を補助。1戸あたり最大200万円。
- メリット:冷暖房効率が劇的に改善し、光熱費を大幅に削減できます。結露の抑制にも効果があり、建物の劣化防止にも繋がります。「電気代が安くなる部屋」として、強力なアピールポイントになります。
2. 賃貸集合給湯省エネ2025事業 賃貸集合住宅の従来型給湯器を、省エネ性能の高い「エコジョーズ」や「エコフィール」に交換する費用を補助する制度です。
- 対象工事:エコジョーズ(ガス)またはエコフィール(石油)への給湯器交換。
- 補助額:追い焚き機能の有無などにより1台あたり5万円〜7万円の定額補助。
- メリット:給湯器は寿命(約10年)があるため、いずれ交換が必要になる設備です。この制度を使えば、交換のタイミングで補助を受けつつ、物件の省エネ性能を高めることができます。入居者のガス代削減に直接貢献できる、分かりやすいメリットです。
ケース④:社会貢献と安定経営を両立する「住宅セーフティネット制度」
【制度の目的】
高齢者、低額所得者、外国人、子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な方々(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない賃貸住宅を増やし、そのための改修費用を支援する制度です。
【対象となる工事】
バリアフリー改修工事、耐震改修工事、間取りの変更、共同居住用の住宅への改修など、住宅確保要配慮者の入居を前提とした幅広い改修が対象です。
【補助額】
工事費の3分の1(地方公共団体からの補助と合わせて最大3分の2)、1戸あたり最大50万円が補助されます。
【オーナーにとってのメリットと注意点】
- メリット:空室を社会貢献に活用しつつ、補助を受けて物件を改修できます。地方公共団体が入居者探しを支援してくれる場合もあり、安定した入居に繋がる可能性があります。
- 注意点:この制度で改修した住宅は、原則として住宅確保要配慮者の入居を拒むことができません。家賃滞納リスクなどへの対策を事前に検討しておく必要があります。
こちらの記事も読まれています!
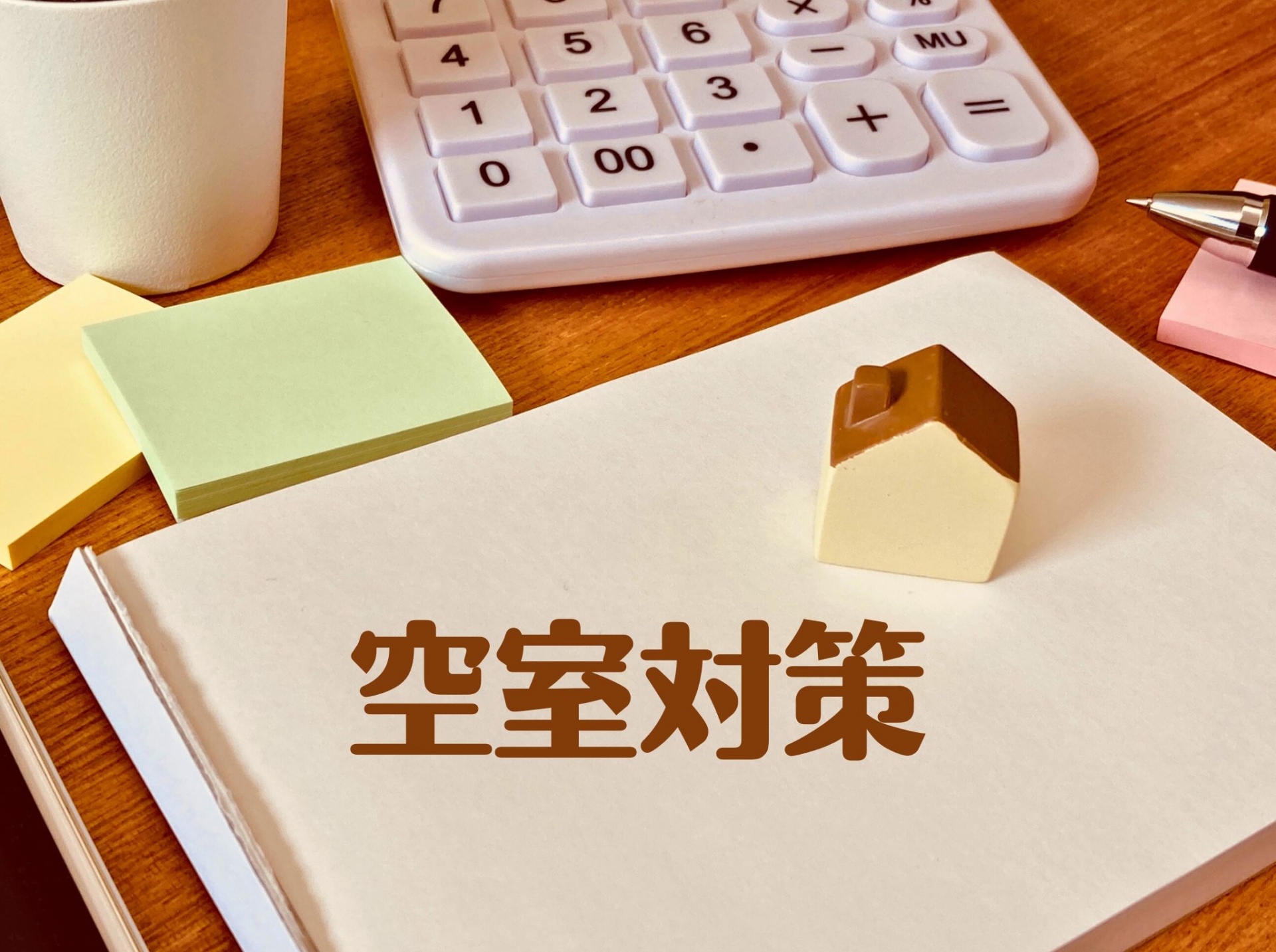
補助金活用のための「5つのステップ」と「成功へのカギ」
魅力的な補助金制度ですが、その恩恵を最大限に受けるためには、計画的な準備といくつかの注意点を押さえておく必要があります。
【補助金活用の5ステップ】
- STEP1:課題の分析とリフォーム計画の策定 まずは補助金ありきではなく、ご自身の物件が抱える課題(空室が長い、設備が古い、ターゲット層が不明確など)を洗い出します。その上で、どのようなリフォームが必要かを検討し、大まかな計画と予算を立てます。
- STEP2:利用可能な補助金制度のリサーチ 計画したリフォーム内容に合致する補助金制度を探します。国の制度だけでなく、自治体独自の補助金制度が用意されている場合も多いので、物件所在地の市区町村のホームページなども必ず確認しましょう。
- STEP3:専門家(施工業者)への相談 補助金の申請手続きは、専門的な書類作成が必要な場合が多く、非常に煩雑です。補助金申請の実績が豊富なリフォーム会社や工務店、建築士事務所に相談することが成功への近道です。この段階で複数の業者から相見積もりを取り、提案内容と費用を比較検討しましょう。
- STEP4:申請手続きと工事の実施 信頼できるパートナーが決まったら、申請手続きを進めます。多くの補助金は**「工事着工前」の申請が必須**です。絶対に自己判断で工事を始めないでください。交付が決定したら、計画に沿って工事を実施します。
- STEP5:完了報告と補助金の受給 工事が完了したら、期限内に完了実績報告書や工事写真などを提出します。審査を経て、無事に承認されると補助金が振り込まれます。
【成功へのカギとなる5つの注意点】
- 資金計画は慎重に(補助金は後払い) 最も重要な注意点です。補助金は、工事が完了し、報告書を提出した後に支払われます。リフォーム費用の支払いは先に発生するため、一時的に全額を立て替える必要があります。手元の資金繰りを十分に考慮した上で計画を立てましょう。
- 公募期間と予算上限を常に意識する 国の補助金は、多くの場合、1年ごとに公募期間が定められており、期間内であっても申請額が予算の上限に達した時点で受付終了となります。人気のある制度は早期に締め切られることも珍しくありません。常に最新情報をチェックし、早めに行動を開始することが肝心です。
- 制度の併用は可能か確認する 原則として、同じ工事に対して国の補助金を複数利用することはできません。ただし、「窓の改修はA制度、給湯器の交換はB制度」といったように、工事箇所が異なれば併用できる場合があります。また、国の補助金と自治体の補助金は併用できるケースも多いので、事前に事務局や施工業者に確認しましょう。
- 信頼できるパートナー(施工業者)を見極める 補助金申請の成否は、施工業者の知識と経験に大きく左右されます。見積もりの際に、「補助金申請のサポート体制は整っていますか?」「過去に同様の申請実績はありますか?」といった質問を投げかけ、信頼できるパートナーかを見極めましょう。
- 目的と手段を履き違えない 補助金はあくまでリフォーム費用を軽減するための「手段」です。補助金が使えるからといって、物件の課題解決に繋がらない不要な工事まで行うのは本末転倒です。常に「このリフォームが入居者満足度や資産価値の向上にどう繋がるのか」という目的意識を持つことが重要です。
おわりに:未来への投資としての戦略的リフォーム
賃貸経営を取り巻く環境は、ますます複雑さと厳しさを増しています。しかし、変化の時代は、新たなチャンスの時代でもあります。今回ご紹介した国のリフォーム支援制度は、意欲あるオーナー様にとって、この厳しい競争を勝ち抜くための強力な武器となるはずです。
これらの制度を賢く活用し、省エネ性能の向上、子育てしやすい環境の整備、建物の長寿命化といった社会的な要請に応えるリフォームを実践することは、単なる空室対策にとどまりません。それは、入居者に選ばれ、長く愛される物件を育てることであり、大切な資産の価値を未来へと繋ぐ、極めて戦略的な「投資」です。
まずはご自身の物件をじっくりと見つめ直し、どのような可能性があるのかを考えてみてください。そして、信頼できる専門家と共に、補助金を活用したリフォームという次の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。その一歩が、あなたの賃貸経営をより豊かで、より安定したものへと導いてくれるに違いありません。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい・・・現状の管理会社に不満がある・・・などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEお問い合わせ可能です♪