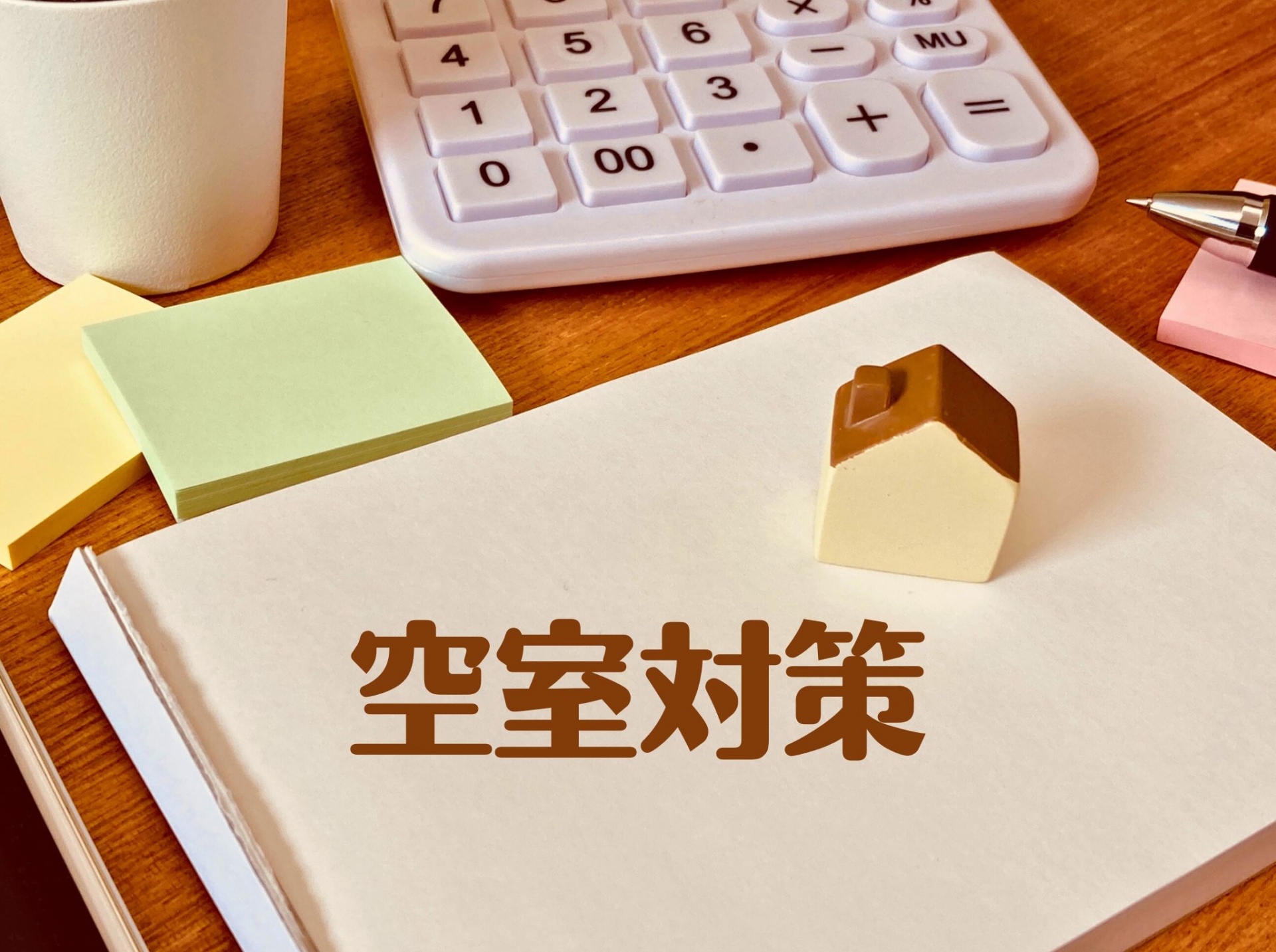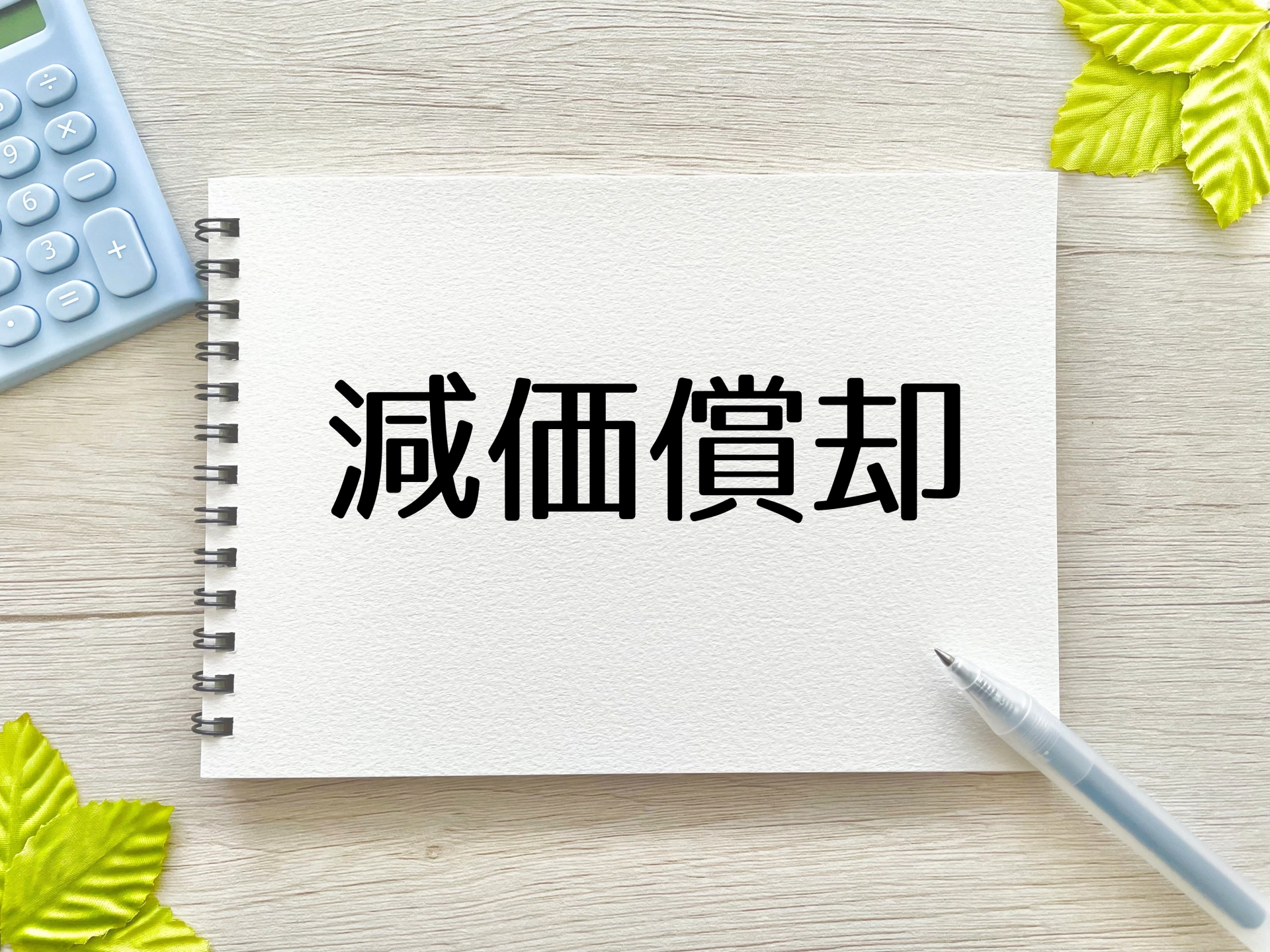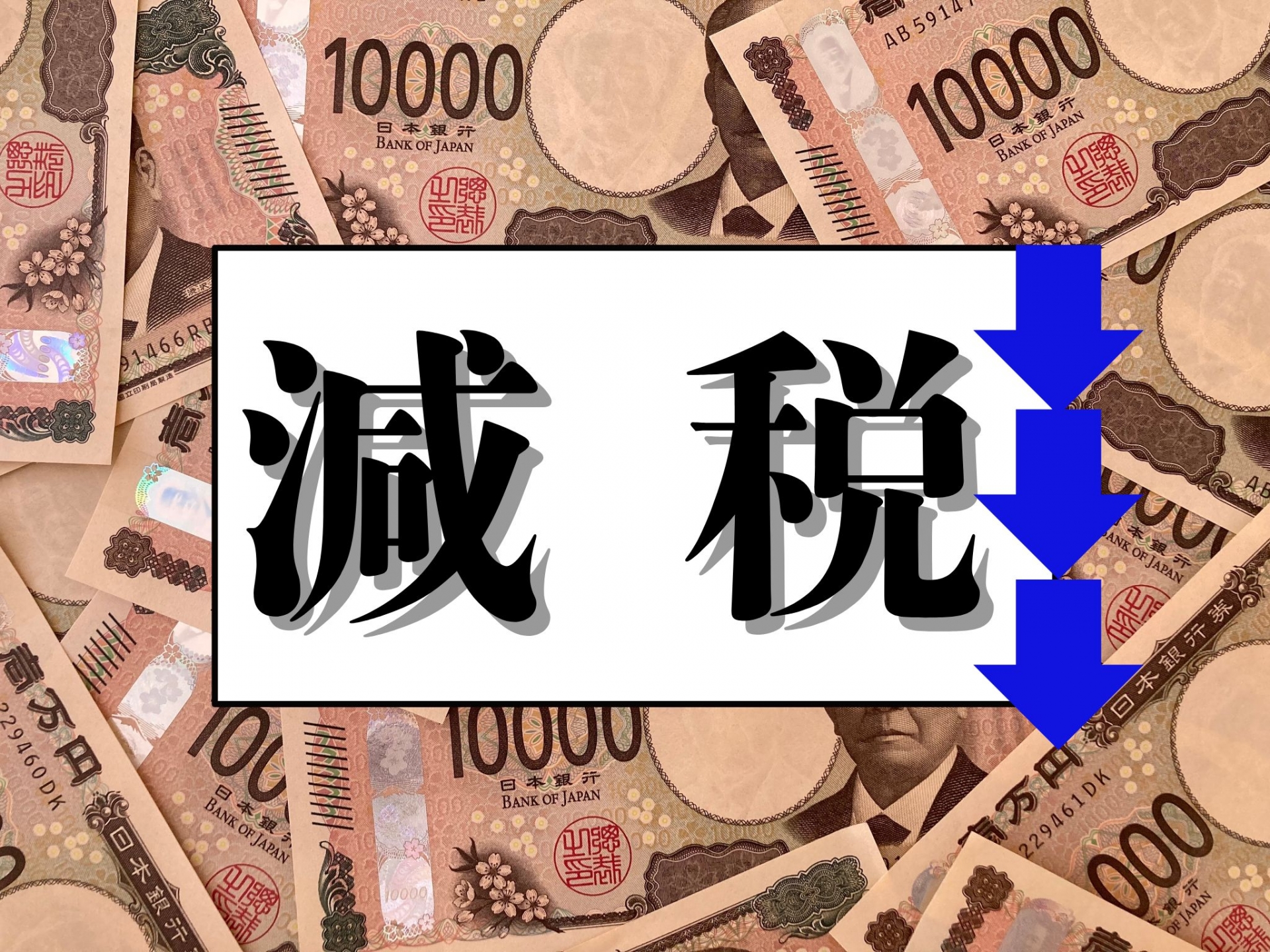はじめに
アパートやマンション経営において、入居率の維持やキャッシュフローの安定化はオーナー様にとって最大の関心事でしょう。しかし、その土台となる「建物」そのものの維持管理、特に「長期修繕計画」をおろそかにしていないでしょうか。
「まだ築浅だから大丈夫」「修繕費はその都度考えればいい」
そう考えていると、近い将来、深刻な事態に直面するかもしれません。
突発的な数千万円単位の支出、雨漏りや設備の故障による入居者クレームの多発、そして修繕が行き届かないことによる「スラム化」と資産価値の暴落…。これらは、計画的な修繕を怠ったオーナーが直面する現実的なリスクです。
逆に言えば、「正しい長期修繕計画」を持つことこそが、賃貸経営を長期的に成功させるための最強の武器となります。
この記事では、アパート・マンションのオーナー様に向けて、なぜ長期修繕計画が必要なのか、そして具体的にどのように作成・運用していけばよいのかを、5つのステップで徹底的に解説します。皆様の貴重な資産を守り、育てるために不可欠な知識です。ぜひ最後までお付き合いください。
1. なぜ「長期修繕計画」が今、重要なのか?
「長期修繕計画」とは、建物の主要な部分(外壁、屋上、給排水管、共用設備など)について、将来予測される修繕・改修工事の「時期」と「概算費用」を長期的な視点(一般的に30年以上)で取りまとめた計画書のことです。
この計画がオーナー経営にとってなぜ重要なのか、3つの側面から解説します。
① 資産価値の「維持」と「向上」
建物は「生もの」であり、竣工した瞬間から劣化が始まります。適切な時期に適切な修繕(外壁塗装、屋上防水など)を行わなければ、雨漏りやコンクリートの爆裂(内部の鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートを破壊すること)などが発生し、建物の寿命そのものを縮めてしまいます。
計画的な修繕は、建物を健全な状態に保ち、法的な耐用年数(例:RC造で47年)を超えてもなお、安全で快適な住環境を提供し続けることを可能にします。これは、金融機関からの融資評価や、将来的な売却時の査定額(資産価値)に直結します。
② 安定経営の実現(入居率の確保)
入居者が物件を選ぶ際、築年数以上に「管理状態」を重視する傾向が強まっています。エントランスが薄暗い、廊下にゴミが散乱している、外壁が汚れている、といった物件は、たとえ立地が良くても敬遠されがちです。
定期的な修繕・清掃が行き届いた物件は、入居者に「大切に管理されている」という安心感を与え、結果として高い入居率と適正な賃料水準を維持することができます。計画的な修繕は、空室リスクを回避し、安定したキャッシュフローを生み出すための「必要経費」なのです。
③ 突発的な大規模支出の回避
長期修繕計画がない場合、修繕は「壊れてから直す」という場当たり的な対応(事後保全)になりがちです。
例えば、ある日突然、屋上からの大規模な雨漏りが発生し、最上階の複数の部屋が被害を受けたとします。この場合、緊急の防水工事費用に加え、被害を受けた部屋の原状回復費用、さらには入居者への補償や仮住まいの費用まで発生する可能性があります。これら数百万円、時には数千万円にもなる支出が、ある日突然キャッシュフローを圧迫します。
長期修繕計画(予防保全)があれば、「13年目に屋上防水工事で500万円必要」とあらかじめ分かっているため、計画的に資金を準備(積立)しておくことができます。これにより、経営の安定性は飛躍的に高まります。
2. 国が示す基準「長期修繕計画作成ガイドライン」
では、この重要な計画を、オーナーはどのように作成すればよいのでしょうか。その羅針盤となるのが、**国土交通省が公表している「長期修繕計画作成ガイドライン」**です。
これは主に分譲マンションの管理組合向けに作成されたものですが、アパートや賃貸マンションのオーナーが1棟全体の計画を立てる上でも非常に有用な指針です。
このガイドラインで示されている重要なポイントは以下の通りです。
- 計画期間:30年以上
- 新築時であれば、少なくとも30年以上の計画を立てることが推奨されています。これは、建物の主要部分(特に給排水管など)の更新周期が30年を超えるものがあるためです。
- 大規模修繕の回数:2回以上を含む
- 計画期間30年であれば、一般的に12〜15年周期で行われる大規模修繕工事が少なくとも2回は含まれることになります。
- 計画の見直し:5年程度ごと
- 計画は一度作ったら終わりではなく、物価の変動、実際の劣化状況、技術の進歩などを反映させるため、5年周期で見直すことが強く推奨されています。
これらの基準を念頭に置き、次のステップに進みましょう。
3. 【ステップ1】現状の把握と建物劣化診断
正しい計画は、正確な「現状把握」から始まります。まずは、ご自身の物件のカルテ(基本情報)を整理しましょう。
竣工図書の確認
「竣工図書(しゅんこうとしょ)」と呼ばれる、建物の設計図や仕様書の束が必ずあるはずです。これらは、修繕工事の範囲や数量(例:外壁の面積、塗装の種類など)を正確に把握するために不可欠な資料です。
- 確認すべき主な情報
- 竣工日(築年数)
- 構造(木造、軽量鉄骨造、RC造など)
- 延床面積、総戸数
- 各部位の仕様(例:屋上はアスファルト防水、外壁はタイル貼りなど)
もし紛失している場合は、施工した建設会社や設計事務所に問い合わせてみましょう。
専門家による「建物劣化診断」の実施
書類上の情報だけでは、現在の「劣化の進行度」は分かりません。そこで重要になるのが、専門家による「建物劣化診断」です。
これは、建築士や建物診断の専門家が現地を調査し、目視、打診(ハンマーで叩く)、専用の機材などを使って、建物の健康状態をチェックするものです。
- 診断内容の例
- 外壁:ひび割れ、浮き、タイルの剥離、シーリング(目地)の劣化
- 屋上・バルコニー:防水層の膨れ、破れ、排水溝の詰まり
- 鉄部:共用階段や手すり、PS扉などの錆び、塗装の剥がれ
- 給排水設備:給水管・排水管の錆や詰まり(内視鏡カメラで調査することも)
- 共用部:廊下やエントランスの床、壁、照明器具の状態
この診断結果に基づき、「どの箇所が、あと何年くらいで、どのような修繕が必要か」という緊急度と修繕方針が明確になります。特に築10年を経過した物件では、一度実施することを強くお勧めします。費用はかかりますが、これは計画の精度を上げるための重要な投資です。
こちらの記事も読まれています!

4. 【ステップ2】修繕項目のリストアップと周期の設定
ステップ1の診断結果と竣工図書を基に、今後発生する修繕項目を時系列でリストアップしていきます。
「いつ、何が壊れるか」を予測するのは難しいように思えますが、国交省のガイドラインや建材メーカーの耐用年数を参考にすることで、標準的な修繕周期(サイクル)を当てはめることができます。
以下に、アパート・マンションにおける主要な修繕項目と、一般的な周期の目安を示します。
【主な修繕項目と周期の目安(例)】
アパート・マンションの主要な修繕項目と、一般的な周期の目安を以下に示します。
- 仮設工事(足場仮設など)
- 周期目安:12~15年
- 大規模修繕(外壁・屋上)と同時に実施します。
- 外装(躯体)関連
- 外壁塗装(吹付・塗替):12~15年周期。塗料のグレードにより異なります。
- シーリング(目地)打替:12~15年周期。外壁塗装と同時に行うのが効率的です。
- タイル補修・洗浄:12~15年周期。浮きや剥離の補修を行います。
- 防水関連
- 屋上防水(アスファルト、シート等):12~15年周期。防水の種類により異なります。
- バルコニー・共用廊下防水:12~15年周期。床面のトップコート(保護塗装)塗り替えが中心です。
- 共用部
- 鉄部塗装(階段、手すり等):4~6年周期。錆を防ぐため、大規模修繕より短いサイクルで必要です。
- 設備関連
- 給水管(専有部・共用部):30~40年周期(取替)。材質により異なり、それ以前に「更生工事」(15~25年)を行う場合もあります。
- 排水管(専有部・共用部):30~40年周期(取替)。定期的な高圧洗浄(1~2年)は別途必要です。
- 給水ポンプ:15~20年周期(交換)。部品交換(オーバーホール)は7~10年ごとに行います。
- インターホン設備:15~20年周期(交換)。
- エレベーター:20~25年周期(リニューアル)。法定点検・保守は別途必要です。
- 機械式駐車場:15~20年周期(リニューアル)。保守点検は別途必要です。
- その他(専有部設備など)
- 給湯器:10~15年周期(交換)。
- エアコン:10~15年周期(交換)。
<ポイント>
- 木造・軽量鉄骨造アパートの場合:
- RC造マンションに比べ、屋根(スレート、ガルバリウム鋼板など)の塗装・葺き替え、外壁(サイディングなど)の塗装・シーリングが修繕の主体となります。
- 特に鉄骨造の場合、鉄骨の錆を防ぐための塗装メンテナンスが重要です。
- 「大規模修繕工事」とは:
- 上記のリストのうち、「足場仮設」「外壁塗装・補修」「屋上防水」など、足場を組んで大掛かりに行う工事をパッケージにしたものを指し、通常12〜15年周期で行われます。
5. 【ステップ3】修繕費用の算出と総額の試算
ステップ2でリストアップした各項目が、30年間に何回発生し、それぞれいくらかかるのかを計算し、30年間の修繕費用総額を算出します。
概算費用の算出方法
最も正確なのは、ステップ1で依頼した建物診断会社や、付き合いのある施工会社、管理会社に「概算見積もり」を依頼することです。
それが難しい場合、国土交通省が公表している統計データが参考になります。
【参考:大規模修繕工事の費用相場】
国土交通省「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、
1回目の大規模修繕工事(足場、外壁、屋上など)にかかった費用は、
1戸あたり「100万円~125万円」 の割合が最も高くなっています。
また、2回目、3回目と築年数が経過するにつれ、修繕箇所が増えるため、費用は1戸あたり「125万円~150万円」、あるいはそれ以上になる傾向があります。
例えば、20戸のアパートであれば、1回目の大規模修繕で「20戸 × 110万円 = 2,200万円」程度が目安となります。
30年間の修繕費用総額を試算する
先ほどの修繕周期のリストと、概算費用を組み合わせて、30年間の計画表(キャッシュフロー表)を作成します。
(例)築5年・20戸のRCマンションの場合
例えば、築5年の20戸RCマンションで30年間の計画を立てると、以下のようなキャッシュフローが想定されます。
まず、築7年目で「鉄部塗装(1回目)」に100万円。
次に、築13年目で「大規模修繕(1回目)」(足場、外壁、屋上、鉄部など)に2,200万円。この時点で累計費用は2,300万円です。
築19年目には「鉄部塗装(2回目)」で120万円。
築20年目で「インターホン交換」に300万円。
築25年目で「給水ポンプ交換」に150万円。
そして、築26年目で「大規模修繕(2回目)」(足場、外壁、屋上、鉄部など)に2,500万円。
最後に、築30年目で「給排水管更生工事」に1,000万円がかかると試算します。
この場合、30年間(正確には計画開始から25年間)の修繕費用合計は6,370万円となります。
物価上昇率(インフレ)の考慮
上記の試算には、非常に重要な視点が抜けています。それは**「物価上昇」**です。
13年後に行う工事費用が、現在の見積額(2,200万円)と同じであるはずがありません。資材費や人件費の高騰により、年々工事費用は上昇しています。
長期修繕計画を立てる際は、必ず**年率1%〜2%程度の物価上昇(インフレ率)**を織り込んで計算する必要があります。
(例)現在の工事費2,200万円が、年率2%で上昇した場合
- 13年後: $2,200 \times (1.02)^{13} \approx 2,846万円$
- 26年後: $2,200 \times (1.02)^{26} \approx 3,681万円$
これを怠ると、いざ修繕の時期が来た時に「お金が足りない」という最悪の事態に陥ります。
こちらの記事も読まれています!

6. 【ステップ4】修繕積立計画の策定
30年間の修繕費用総額(インフレ考慮後)が算出できたら、次にその費用を「どうやって準備するか」という資金計画を立てます。
ここが、**分譲マンション(区分所有)とアパート・賃貸マンション(1棟オーナー)**で考え方が大きく異る点です。
A)分譲マンション(管理組合)の場合
管理組合として、区分所有者から「修繕積立金」を毎月徴収します。積立方式には、主に2つの方法があります。
- 均等積立方式(推奨)
- 30年間の修繕費用総額を、計画期間(30年 × 12ヶ月)で均等割りして、毎月の積立額を算出する方法。
- メリット:将来にわたって積立金額が一定(※見直しによる変動はあり)なため、資金計画が立てやすく、長期的に安定した資金確保が可能。
- デメリット:新築当初は、まだ修繕の必要がないにもかかわらず、高めの積立金となる。
- 段階増額積立方式
- 新築当初の積立額を低く設定し、5年ごと、10年ごとなど、段階的に積立額を値上げしていく方式。
- メリット:新築時の購入者(オーナー)の負担感が少ない。
- デメリット:将来、必ず大幅な値上げが必要となる。その際に区分所有者間の合意形成が難航し、必要な積立金が集まらず、修繕が実行できないリスクが非常に高い。
新築分譲時に「修繕積立金が安い」ことをアピールするために②が採用されているケースも多いですが、経営の安定性を考えれば、①の均等積立方式が圧倒的に望ましいと言えます。
B)アパート・賃貸マンション(1棟オーナー)の場合
管理組合は存在しないため、オーナー自身が修繕費用を準備する必要があります。選択肢は以下の3つです。
- 自己資金(キャッシュフロー)からの積立(推奨)
- 最も健全な方法です。ステップ3で算出した30年間の総額を基に、毎月の家賃収入から「修繕引当金」として、一定額を別口座に積み立てていきます。
- (例)30年で6,370万円必要 → 6,370万円 ÷ 360ヶ月 $\approx$ 月額 17.7万円
- この「月額17.7万円」は、賃貸経営における「コスト」として、収支計画(キャッシュフロー計算)に組み込む必要があります。これを考慮せずに「手残り(利益)」を計算してはいけません。
- 金融機関からの融資(リフォームローン)
- 大規模修繕のタイミングで、必要な資金を金融機関から借り入れる方法。
- 手元のキャッシュを残せるメリットはありますが、金利負担が発生します。また、築年数が経過していると、融資審査が厳しくなる可能性もあります。
- その都度、手持ち資金から支出
- 最も危険な方法です。他の事業や生活費と資金が混在し、いざ2,000万円が必要となった時に「お金がない」状態に陥りがちです。
1棟オーナー様は、分譲マンションの「均等積立方式」に倣い、**家賃収入から天引きする形で、修繕専用の口座に毎月積み立てる(①)**ことを強くお勧めします。
7. 【ステップ5】計画の運用と「5年ごとの見直し」
長期修繕計画は、一度作成したら金庫にしまっておくものではありません。**「定期的に見直し、育てる」**ことにこそ、その真価があります。
国土交通省が「5年程度ごと」の見直しを推奨しているのには、明確な理由があります。
なぜ「見直し」が必要なのか?
- 物価・工事費の変動
- 計画作成時に「年率2%」と想定したインフレ率が、社会情勢(例:資材ショック、円安、人手不足)によって「年率4%」になるかもしれません。5年ごとに実勢価格を反映させないと、計画上の費用と実際の見積額が大きく乖離します。
- 建物の劣化状況の変化
- 計画では「13年目に外壁塗装」としていても、実際の劣化診断で「まだ状態が良いので15年目に延期しよう」あるいは「劣化が激しいので12年目に前倒ししよう」といった調整が必要になります。
- 技術革新・仕様変更
- 5年、10年も経てば、より耐久性の高い塗料や、高性能な防水工法が登場します。次回の修繕でそれらを採用する場合、工事単価や、その後の修繕周期(例:15年周期 → 18年周期)も変更する必要があります。
- 法令の改正
- 耐震基準や消防法、省エネ基準などの改正により、計画になかった改修(例:耐震補強工事)が求められる場合もあります。
見直しの具体的なタイミング
見直しに最適なタイミングは、以下の2つです。
- 定期的な見直し(5年ごと)
- 大規模修繕工事の「実施直後」
特に、大規模修繕の実施後は絶好のタイミングです。「計画では2,500万円だったが、実際は2,800万円かかった」「今回、給排水管の調査も併せて行ったら、予想より劣化が進んでいた」といった**「実績」と「新たな診断結果」**を、残りの計画期間にフィードバック(修正)します。
この見直し作業(メンテナンス)を怠ると、せっかく立てた計画が「絵に描いた餅」となり、10年後には全く役に立たないものになってしまいます。
8. まとめ:賢明なオーナーは「未来への投資」を怠らない
アパート・マンションの「正しい長期修繕計画」の作り方と運用方法を解説してきました。
長期修繕計画の作成は、確かに手間とコストがかかります。専門家への診断依頼や、複雑なシミュレーションも必要です。しかし、これは「コスト」ではなく、ご自身の貴重な資産を守り、長期的な収益を最大化するための**「未来への投資」**です。
場当たり的な修繕でキャッシュフローを悪化させ、資産価値をすり減らしていくのか。
それとも、未来を見据えた計画で建物を健全に保ち、安定した経営を実現するのか。
賢明なオーナー様であれば、答えは明確なはずです。
もし、まだご自身の物件の長期修繕計画をお持ちでないなら、まずは信頼できる管理会社や建物診断の専門家に相談することから始めてみてください。それが、10年後、20年後の「経営の差」を生み出す、確実な第一歩となります。
本コラムが、オーナー様の長期安定経営の一助となれば幸いです。
長期修繕計画の作成について、さらに具体的なご相談(例えば、お持ちの物件のタイプに合わせた修繕項目のご提案や、概算費用のシミュレーション)も承っております。お気軽にお声がけください。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい・・・現状の管理会社に不満がある・・・などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEお問い合わせ可能です♪