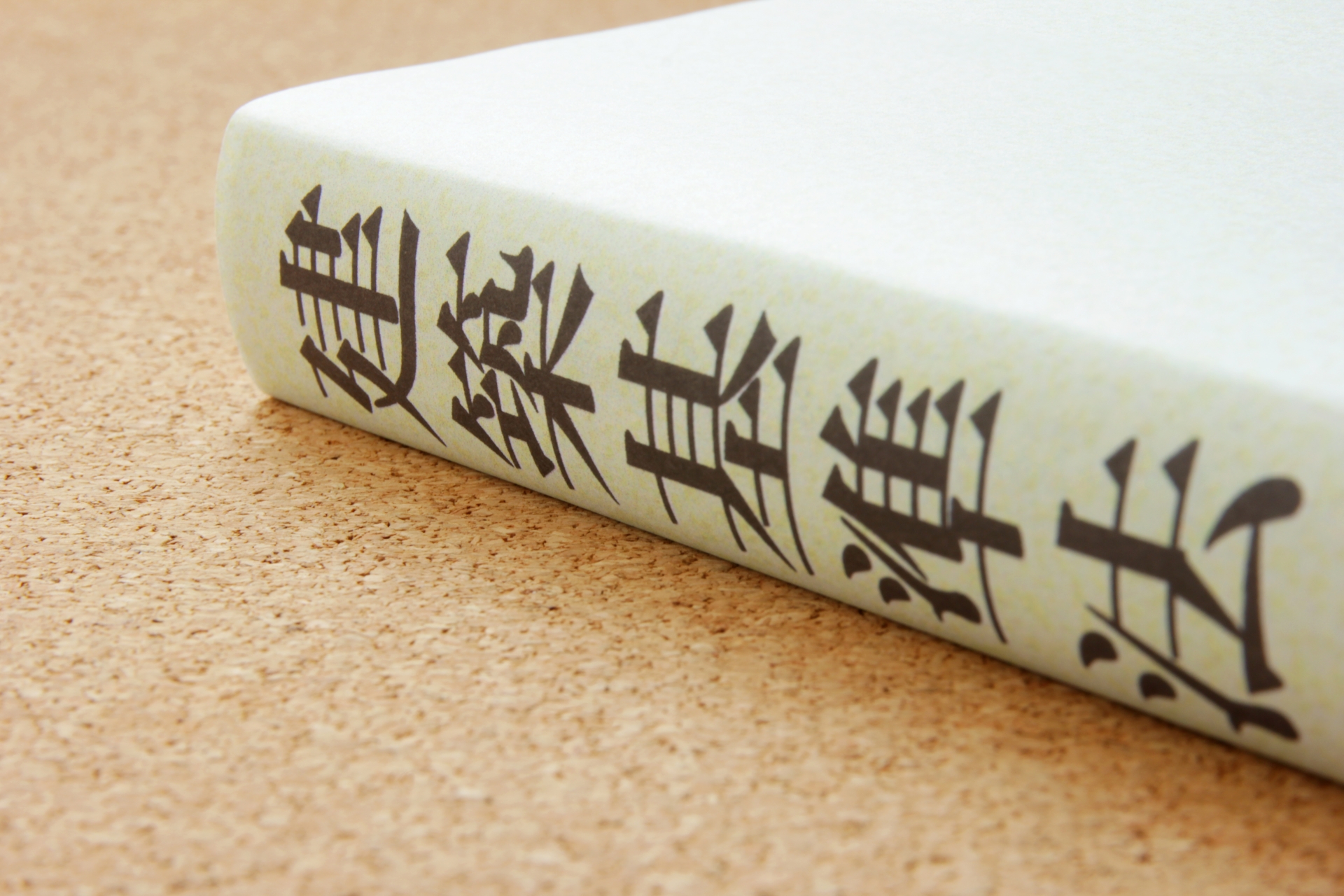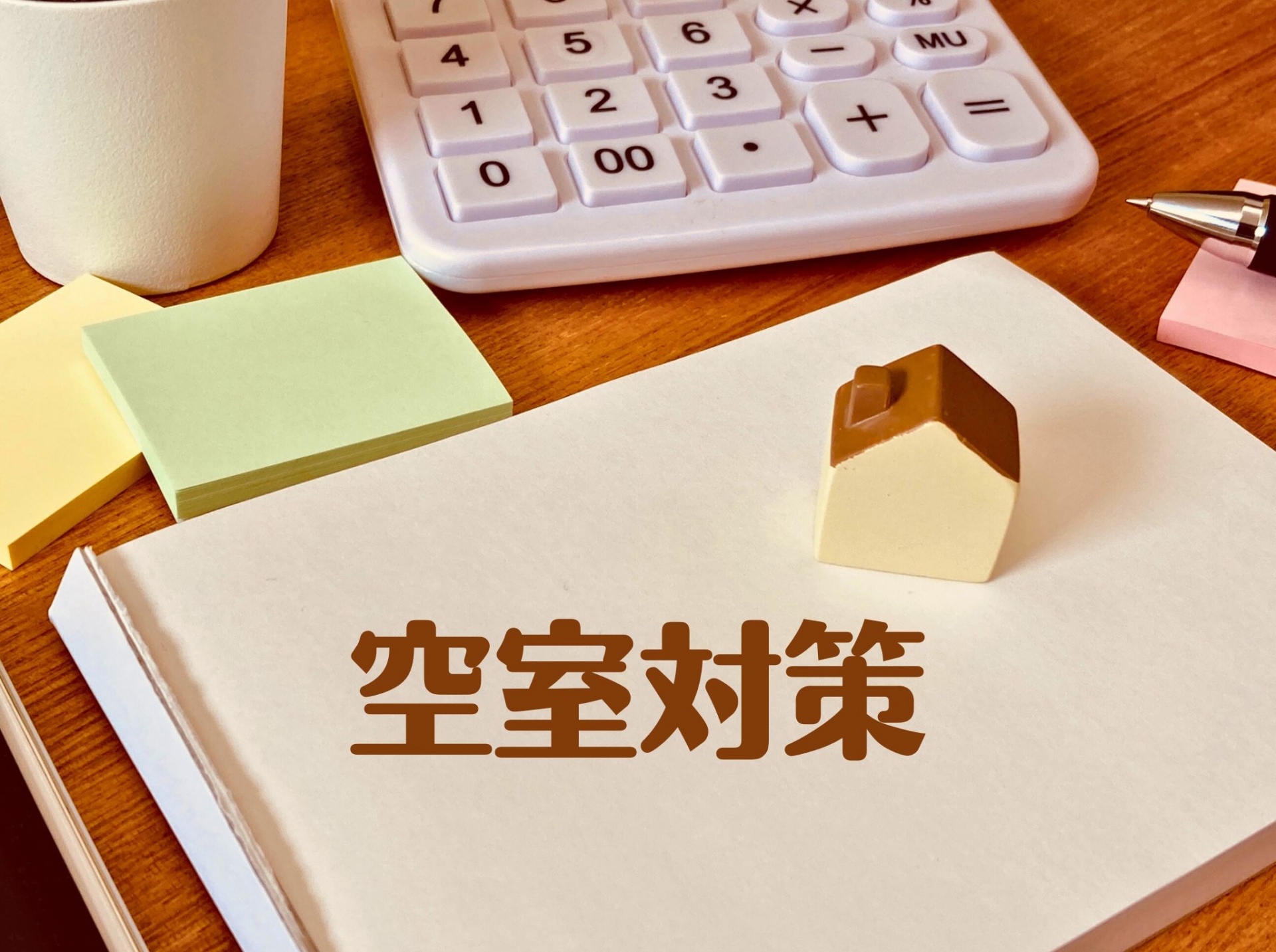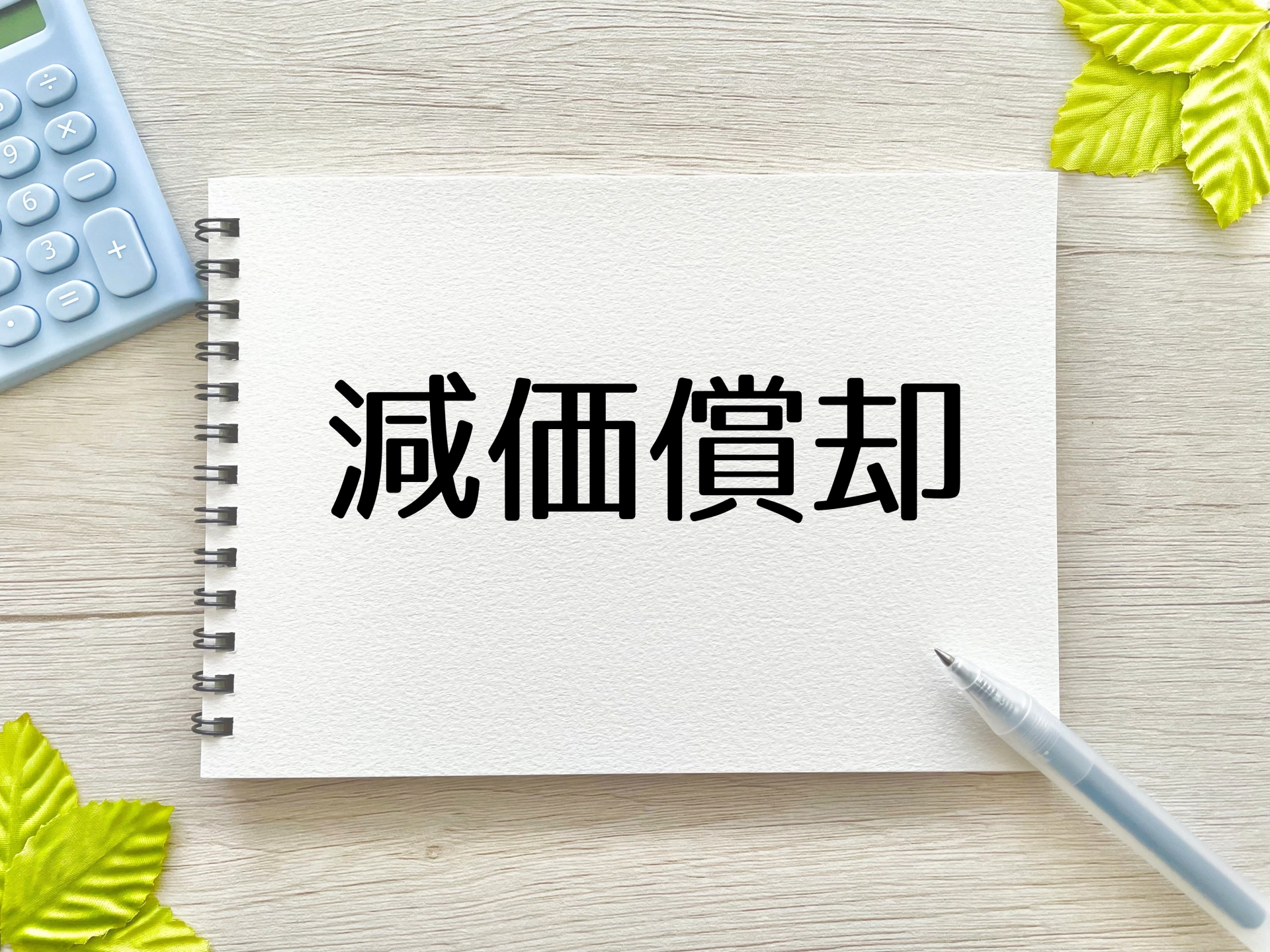はじめに
2025年4月、私たちの住まいに関わる大きな法改正、改正建築基準法が施行されます。この改正は、脱炭素社会の実現に向けた住宅の省エネ化と、より安全な建物を増やすことを目的としたものです。
「新築の話で、リフォームには関係ないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、実はこの法改正、今後のリフォーム計画に大きな影響を与える可能性があります。特に、これまで手続きが比較的簡単だった木造住宅のリフォームや、大規模なリノベーションを検討している方は必見です。
このコラムでは、2025年の建築基準法改正がリフォームにどのような影響を及ぼすのか、その核心となる「2つの大きな変更点」を軸に、メリット・デメリット、そして私たちが今から準備すべきことまで、分かりやすく解説していきます。
なぜ今、建築基準法が改正されるのか?
今回の法改正の背景には、大きく2つの社会的な要請があります。
一つは、**「2050年カーボンニュートラル」**の実現です。家庭からのCO2排出量は全体の約15%を占めており、その削減は急務です。エネルギー効率の悪い住宅は、冷暖房などで多くのエネルギーを消費し、光熱費の負担増だけでなく、環境にも大きな負荷をかけています。そこで、住宅の断熱性や設備の効率を高める「省エネ化」をスタンダードにする必要が出てきました。
もう一つは、**「建物の安全性向上」**です。日本は地震や台風などの自然災害が多い国です。既存の住宅の中には、現在の耐震基準を満たしていないものや、専門家による適切なチェックを受けずに増改築が繰り返され、安全性が不明確になっているものも少なくありません。建物の品質を確保し、安心して長く住み続けられるストックを増やすことが求められています。
この「省エネ」と「安全」という2つの目標を達成するため、建築基準法が大きく変わります。そして、その変化の波は、これからリフォームを考えるすべての人に関わってくるのです。
具体的にリフォームに影響するのは、以下の2つのポイントです。
- 省エネ基準への適合義務化
- 4号特例の縮小(手続きの厳格化)
次章から、この2つのポイントが私たちのリフォーム計画にどう関わってくるのか、詳しく見ていきましょう。
【影響その1】省エネ基準への適合義務化:快適でお得な住まいへの必須条件
今回の法改正で最も注目されているのが、省エネ基準への適合が原則すべての新築住宅で義務化される点です。
これまで、小規模な住宅では省エネ基準への適合は「努力義務」に留まっていました。しかし2025年4月以降は、断熱材の性能や窓の仕様、給湯器などの設備効率が一定の基準をクリアしていないと、家を建てることができなくなります。
どんなリフォームが対象になる?
「これは新築の話だから、リフォームには関係ない」と考えるのは早計です。この省エネ基準適合義務は、「増築」や「改築」を伴うリフォームにも適用されます。
- 対象となるリフォーム: 床面積が増える「増築」や、一度取り壊して建て直す「改築」を行う場合。
- ※ただし、10㎡以下の小規模な増築は対象外です。
- 対象とならないリフォーム: 間取り変更、キッチンや浴室の交換、内外装の張り替えといった「大規模な修繕・模様替」は、原則として省エネ基準適合の義務化の対象外です。
重要なのは、増改築を行う場合、**「増改築する部分」**が新しい省エネ基準を満たす必要があるという点です。例えば、リビングの隣に部屋を一つ増築する場合、その新しい部屋の壁や天井には十分な断熱材を入れ、窓は断熱性の高い製品(ペアガラスやトリプルガラスなど)を使う必要があります。
省エネリフォームのメリットとデメリット
省エネ基準を満たすためのリフォームには、当然ながらメリットとデメリットがあります。
メリット
- 光熱費の大幅な削減: 断熱性が高まることで、冷暖房の効率が格段にアップします。夏は涼しく、冬は暖かい家になり、毎月の電気代やガス代を大きく節約できます。
- 快適性と健康の向上: 部屋ごとの温度差が少なくなるため、冬場のヒートショックのリスクを軽減できます。また、結露の発生を抑え、カビやダニの繁殖を防ぐ効果も期待できます。
- 資産価値の向上: 「省エネ性能が高い住宅」は、今後の住宅市場で大きな付加価値を持ちます。将来、家を売却したり貸したりする際に、有利な条件につながる可能性があります。
デメリット
- 初期費用の増加: 高性能な断熱材や窓、高効率な給湯器などは、従来の建材や設備に比べてコストが高くなります。リフォーム全体の費用が膨らむ可能性があります。
費用を抑えるための賢い選択:補助金の活用
初期費用の増加は大きな懸念点ですが、国や自治体は住宅の省エネ化を強力に後押ししており、手厚い補助金制度を用意しています。
代表的なのが、経済産業省、国土交通省、環境省が連携して実施する**「住宅省エネ2025キャンペーン」です。このキャンペーンには、断熱窓への改修を支援する「先進的窓リノベ事業」や、高効率給湯器の導入を支援する「給湯省エネ事業」などが含まれており、工事内容によっては最大で200万円以上**の補助を受けることも可能です。
これらの補助金をうまく活用することで、費用負担を大幅に軽減し、高性能なリフォームを実現できます。リフォーム会社を選ぶ際には、こうした補助金制度に詳しく、申請手続きをサポートしてくれるかどうかも重要なポイントになります。
こちらの記事も読まれています!

【影響その2】4号特例の縮小:安全性を高めるための手続き厳格化
もう一つの大きな変更点が、「4号特例」の縮小です。これは少し専門的な話になりますが、リフォームの費用や工期に直接関わる重要なポイントなので、ぜひ理解しておきましょう。
「4号特例」とは?
建築基準法では、建物を規模や用途によって1号から4号までに分類しています。このうち「4号建築物」とは、木造2階建て以下で延べ床面積が500㎡以下などの条件を満たす、比較的小規模な建物を指します。多くの一般住宅がこれに該当します。
「4号特例」とは、この4号建築物を建てる際に、建築確認申請(工事の計画が法律に適合しているかを事前に審査する手続き)の一部の書類提出や審査を省略できるという制度でした。これにより、設計や申請にかかる時間とコストを抑えることができていました。
何が変わるのか?
2025年4月からは、この4号特例の対象範囲が縮小されます。 これまで4号建築物だったもののうち、
- 木造2階建て
- 木造平屋建てで延べ床面積が200㎡を超えるもの
これらは新たに**「新2号建築物」**という区分になります。そして、この「新2号建築物」は、4号特例の対象から外れます。
リフォームへの具体的な影響
この変更がリフォームにどう影響するのでしょうか。最も大きな影響を受けるのは、「新2号建築物」に該当する住宅で「大規模な修繕・模様替」を行うケースです。
- 対象となる住宅: 木造2階建て、または200㎡超の木造平屋
- 対象となるリフォーム: 大規模な修繕・模様替
- これは、建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)のうち、一種別以上について、その半分以上を改修する工事を指します。
- 具体的には、間取りを大幅に変更するために柱や壁を撤去する、屋根を全面的に葺き替える、床をすべて張り替えるといった、いわゆるスケルトンリフォームやフルリノベーションが該当する可能性があります。
これまで、こうした大規模なリフォームでも、4号特例のおかげで建築確認申請が不要な場合が多くありました。しかし、法改正後は、原則として建築確認申請が必要になります。
手続き厳格化のメリットとデメリット
建築確認申請が必要になることには、もちろん良い面と注意すべき面があります。
メリット
- 建物の安全性が向上する: 建築士が設計し、行政(または指定確認検査機関)が図面を審査することで、建物の構造的な安全性が客観的にチェックされます。耐震性などが現行の基準に適合していることが確認されるため、安心して住むことができます。
- 悪質な工事のリスクが減る: 第三者のチェックが入ることで、手抜き工事や法律に違反するようなリフォームを防ぐ効果が期待できます。
- 資産価値が明確になる: 検査済証が交付されることで、その建物が適法な手続きを経て安全基準を満たしていることの証明になり、将来の売却時などにも有利に働きます。
デメリット
- 費用が増加する:
- 確認申請手数料: 行政や検査機関に支払う手数料が発生します。
- 設計料・構造計算料: 建築士による詳細な図面の作成や、場合によっては構造計算が必要になり、そのための費用がかかります。
- 工期が長くなる: 確認申請の準備から許可が下りるまでに、数週間から数ヶ月かかる場合があります。その期間は工事に着手できないため、リフォーム全体のスケジュールが長くなる可能性があります。
- リフォームの自由度が下がる可能性: 特に、既存不適格建築物(建てられた当時は適法だったが、現行の法律には適合しない建物)の場合、大規模なリフォームを機に、建物全体を現行法に適合させるよう求められることがあります。例えば、接道義務を満たしていない「再建築不可物件」では、これまで黙認されていた大規模リフォームが、確認申請を通せず、実施できなくなるケースが出てくると予想されています。
こちらの記事も読まれています!

リフォームを検討している私たちが今から準備すべきこと
では、これからリフォームを計画している私たちは、この法改正にどう向き合えばよいのでしょうか。慌てる必要はありませんが、いくつかのポイントを押さえて準備を進めることが大切です。
1. 自宅の現状を把握する
まずは、ご自宅の「履歴書」を確認しましょう。
- 建築確認通知書・検査済証: 建てた時の書類が残っているか確認しましょう。特に検査済証は、建物が適法に建てられたことを証明する重要な書類です。
- 設計図面: リフォームの計画を立てる上で不可欠です。紛失している場合は、家を建てた工務店やハウスメーカーに問い合わせてみましょう。
- 築年数と構造: 木造2階建てか、平屋か、築何年か、といった基本情報を整理しておきましょう。
2. 専門家への早めの相談
計画しているリフォームが法改正の影響を受けるかどうかは、専門家でなければ判断が難しい部分が多くあります。リフォームの規模や内容を問わず、まずは信頼できるリフォーム会社や建築士に早めに相談しましょう。 その際、以下の点を確認すると良いでしょう。
- 2025年の法改正の内容を正しく理解しているか。
- 建築確認申請の手続きに慣れているか。
- 補助金制度の活用について詳しいか。
3. 余裕を持った資金計画とスケジュール
4号特例の縮小により、これまで不要だった申請費用や設計料が追加で必要になる可能性があります。また、申請期間を見越して、工期にも余裕を持たせる必要があります。リフォーム会社と相談しながら、追加費用や期間の延長も想定した、無理のない資金計画とスケジュールを立てることが重要です。
4. 補助金などの情報を積極的に収集する
省エネリフォームに対する補助金制度は、今後も継続・拡充されることが予想されます。国だけでなく、お住まいの自治体が独自に行っている支援制度もあります。アンテナを高く張り、利用できる制度は積極的に活用しましょう。
まとめ:法改正は、より良い住まいへの「未来への投資」
2025年の建築基準法改正は、リフォームを考える私たちにとって、手続きが増えたり、費用がかかったりと、一見するとハードルが上がるように感じられるかもしれません。
しかし、その本質は、日本のすべての住宅を**「安全で、快適で、環境に優しく、資産価値の高いもの」**へとアップデートしていくための重要なステップです。
省エネリフォームは、短期的な支出は増えるかもしれませんが、その後の光熱費削減や健康的な暮らしという形で、必ず元が取れる「投資」です。また、手続きが厳格化されることは、私たちの生命と財産を守る建物の安全性を、専門家の目で客観的に担保してくれることに他なりません。
この変化の時を、単なる「規制強化」と捉えるのではなく、自分の住まいの価値を見つめ直し、未来に向けてより良くしていく絶好の機会と捉えてみませんか?
そのためには、正しい知識を身につけ、信頼できるパートナー(リフォーム会社や建築士)を見つけることが何よりも大切です。今回の法改正をきっかけに、ぜひご自宅の未来について、じっくりと考えてみてください。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい・・・現状の管理会社に不満がある・・・などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEでお問い合わせ可能です♪