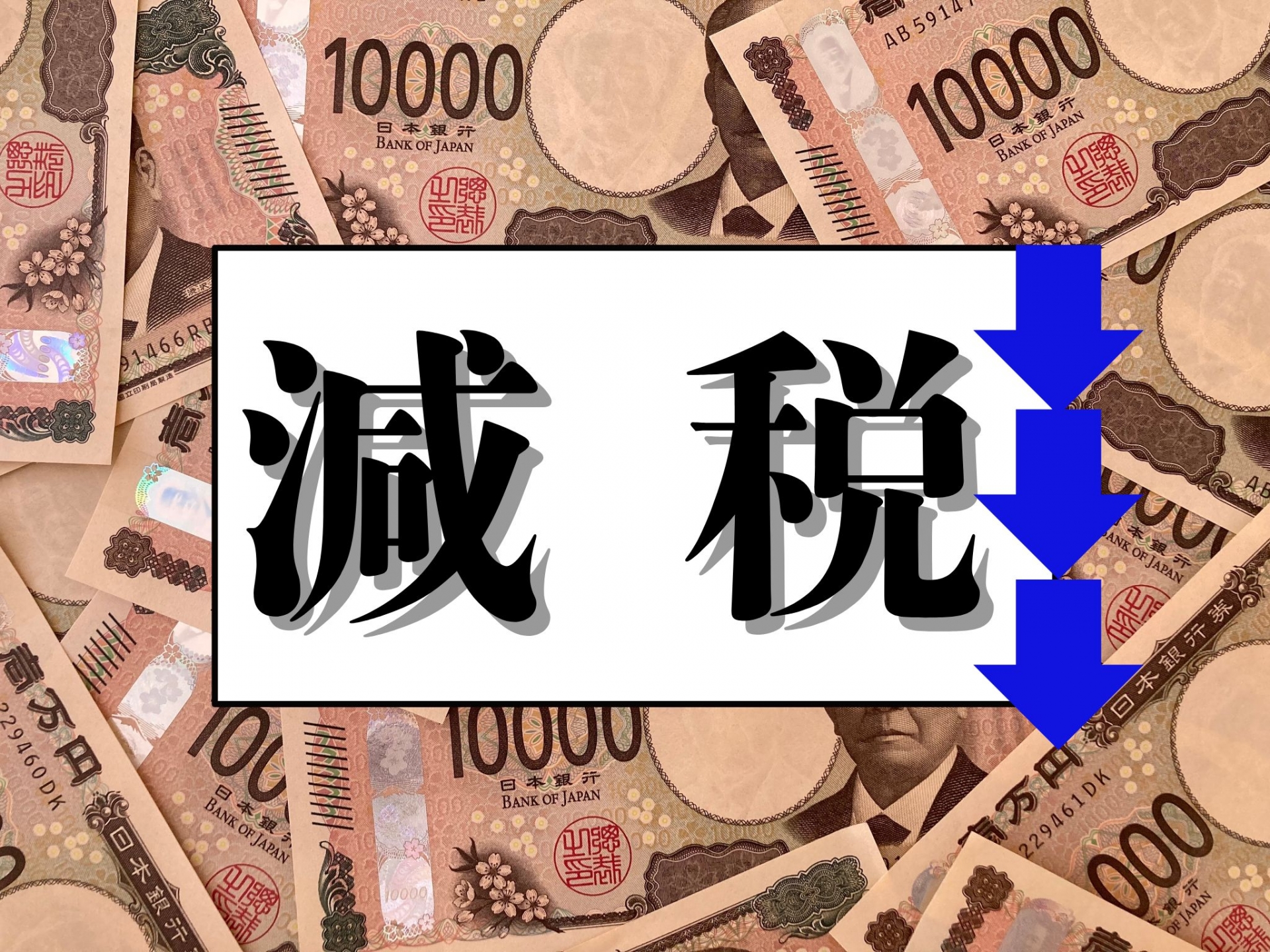はじめに
副業解禁の流れや将来への備えとして、サラリーマン大家さんが増えています。安定した家賃収入は魅力的ですが、不動産投資の成功は「いかに手残りを最大化するか」にかかっていると言っても過言ではありません。そして、その鍵を握るのが「経費」のコントロールです。
「経費の裏ワザ」と聞くと、何かグレーな手法を想像するかもしれません。しかし、本コラムで紹介するのは、脱税ではなく、法律で認められた範囲で賢く税金を抑える「節税」のテクニックです。正しい知識を身につけ、経費を漏れなく、そして効果的に計上することが、不動産投資の収益を最大化する最短ルートなのです。
本記事では、不動産投資における経費の基本から、サラリーマン大家さんが見落としがちな応用テクニックまで、徹底的に解説します。あなたの不動産経営を次のステージへ引き上げるための知識を、ぜひここで手に入れてください。
不動産投資における「経費」の基本
まずは、何が経費になり、何が経費にならないのか、その基本をしっかり押さえましょう。不動産所得は、以下の計算式で算出されます。
総収入金額 − 必要経費 = 不動産所得
この「必要経費」が多ければ多いほど、課税対象となる「不動産所得」は圧縮され、結果として所得税や住民税を抑えることができます。
1.1. 経費にできるものの代表例
不動産投資で経費として認められるものは多岐にわたります。以下に代表的なものをリストアップします。
- 租税公課
- 固定資産税・都市計画税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
- 損害保険料
- 火災保険料
- 地震保険料
- ローン関連費用
- 借入金の金利部分(建物・土地)
- ローン保証料、手数料
- 管理・運営費用
- 管理会社への委託管理費
- 入居者募集のための広告宣伝費、仲介手数料
- 賃貸管理ソフトの利用料
- 建物の維持管理費用
- 減価償却費
- 修繕費(原状回復費用、小規模な修繕など)
- 共用部分の水道光熱費
- 清掃費、消耗品費
- 専門家への報酬
- 税理士への確定申告依頼費用
- 司法書士への登記依頼費用
- 弁護士への相談料(滞納トラブルなど)
- その他
- 不動産投資に関連する交通費、通信費、新聞図書費
- 情報収集のためのセミナー参加費、コンサルティング料
1.2. 経費にできないものの注意点
一方で、以下のような支出は経費として計上できません。誤って計上しないように注意しましょう。
- 所得税、住民税:これらは個人が納める税金であり、事業の経費にはなりません。
- 借入金の元本部分:ローン返済のうち、元本は「負債の返済」であり、経費にはなりません。金利部分のみが経費対象です。
- 個人的な支出:事業に関係のない飲食代や旅行費、衣類の購入費などは当然経費にできません。
- 罰金・科料:駐車違反などの罰金は経費になりません。
こちらの記事も読まれています!

【本題】サラリーマン大家さんのための経費計上「5つの裏ワザ」
基本を押さえたところで、いよいよ本題の「裏ワザ」的テクニックをご紹介します。これらはすべて合法的な節税手法ですが、知識があるかないかで納税額に大きな差が生まれるポイントです。
裏ワザ1:減価償却の仕組みを極める
不動産投資における最大の経費項目であり、節税のキモとなるのが**「減価償却費」**です。減価償却とは、不動産(建物や設備)の取得費用を、その資産が使用できる期間(法定耐用年数)にわたって分割して経費計上していく会計処理のこと。
最大のポイントは、**実際にお金が出ていくわけではない「ペーパー上の経費」**であるという点。キャッシュフローを悪化させることなく、所得を圧縮できる非常に強力な節税策です。
中古×木造で償却効果を最大化する
減価償却費は「取得価額 ÷ 耐用年数」で大まかに計算できます(定額法の場合)。つまり、耐用年数が短いほど、1年あたりの減価償却費は大きくなります。
建物の法定耐用年数は構造によって決まっています。
- 木造:22年
- 軽量鉄骨造(骨格材の厚さ3mm以下):19年
- 軽量鉄骨造(骨格材の厚さ3mm超4mm以下):27年
- 重量鉄骨造:34年
- 鉄筋コンクリート(RC)造:47年
ここで注目すべきが中古物件です。中古物件の耐用年数は、以下の簡便法で計算できます。
(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
もし法定耐用年数をすべて経過した物件(例:築25年の木造アパート)を購入した場合、耐用年数は**「法定耐用年数 × 20%」**で計算します。
- 木造:22年 × 20% = 4.4年 → 4年
- RC造:47年 × 20% = 9.4年 → 9年
築古の木造物件なら、わずか4年という短期間で建物価格の全額を償却できるのです。これにより、購入初期に大きな減価償却費を計上し、不動産所得を赤字にすることも可能になります。サラリーマンの場合、この不動産所得の赤字を給与所得と損益通算することで、給与から天引きされた所得税の還付を受けることができるのです。これが、中古物件を活用した節税の王道パターンです。
建物と設備の比率を最適化する
不動産の購入価格は「土地代」と「建物代」に分かれますが、減価償却できるのは「建物代」のみです。さらに、建物は「建物本体」と、給排水設備やガス設備、冷暖房設備などの「建物付属設備」に分けられます。
この**「建物付属設備」は、建物本体よりも短い耐用年数(多くは15年)で償却できます**。
売買契約書に建物と設備の価格内訳が明記されていればそれに従いますが、総額でしか記載がない場合、合理的な基準で按分することが可能です。不動産鑑定士に評価を依頼したり、固定資産税評価額を参考にしたりして、設備部分の価値を適切に評価し、按分比率を高めることで、より多くの金額を短期間で償却でき、初期の節税効果を高めることができます。
裏ワザ2:「修繕費」か「資本的支出」か?運命の分かれ道
物件の古くなった部分をリフォームしたり、設備を交換したりした際の費用。これを「修繕費」として処理するか、「資本的支出」として処理するかで、その年の納税額は大きく変わります。
- 修繕費:壊れたものを元に戻す(原状回復)ための費用。支出した年に全額を経費にできます。
- 例:壊れた給湯器を同等のものに交換、外壁のひび割れ補修、畳の表替え
- 資本的支出:資産の価値を高めたり、耐久性を増したりするための費用。資産として計上し、減価償却によって数年かけて経費化します。
- 例:通常の外壁塗装を、耐久性の高い高級塗料で行う、部屋に新たな機能(追い炊き機能など)を追加する
当然、その年の税金を抑えたいなら「修繕費」として一括で経費計上したいところです。国税庁は、この判断基準をいくつか示しています。
- 20万円未満の支出:明らかに資本的支出であっても、金額が20万円未満であれば「修繕費」として処理できます。
- おおむね3年以内の周期で行われる修繕:これも「修繕費」と判断されます。
- 金額で判断できない場合:その支出が「維持管理・原状回復」目的なのか、「価値の向上」目的なのかで実質的に判断します。
この判断は非常に重要です。例えば、150万円かけて外壁塗装を行った場合、これが「修繕費」と認められれば150万円全額がその年の経費になります。しかし、「資本的支出」と判断されると、建物の耐用年数に応じて長期間にわたって少しずつしか経費にできません。
少額減価償却資産の特例を活用する
青色申告をしている場合、取得価額が30万円未満の資産であれば、購入した年に全額を経費にできる「少額減価償却資産の特例」が使えます(年間合計300万円まで)。
例えば、30万円未満のエアコンや給湯器、モニター付きインターホンなどを設置した場合、本来なら資産計上して減価償却するところを、この特例を使えば一括で経費にできます。大規模修繕のタイミングなどでうまく活用したい制度です。
裏ワザ3:見落としがちな「家事按分」を徹底活用する
サラリーマン大家さんが最も見落としがちで、かつ税務調査でも指摘されやすいのが**「家事按分(かじあんぶん)」**です。これは、プライベートと事業の両方で使っている支出について、事業で使った分だけを合理的な基準で分けて経費に計上することを言います。
自宅の家賃・光熱費・通信費
自宅の一部を不動産事業の事務所として使っている場合、その部分に対応する費用を経費にできます。
- 家賃:自宅の総面積のうち、事業用に使っているスペースの面積割合で按分します。
- 例:家賃15万円、総面積70㎡の自宅のうち、10㎡の書斎を事業用に使用。
- 15万円 × (10㎡ ÷ 70㎡) ≒ 21,428円/月 が経費に。
- 例:家賃15万円、総面積70㎡の自宅のうち、10㎡の書斎を事業用に使用。
- 通信費(インターネット、携帯電話代):使用時間や日数で按分するのが一般的です。
- 例:月の携帯代が1万円。平日は事業で使い、土日はプライベート利用の場合。
- 1万円 × (5日 ÷ 7日) ≒ 7,142円/月 が経費に。
- 例:月の携帯代が1万円。平日は事業で使い、土日はプライベート利用の場合。
- 電気代:使用時間や、事業で使うコンセントの数などで按分します。
重要なのは、「なぜその割合で按分したのか」を第三者に客観的に説明できることです。作業日報などで業務時間を記録しておく、間取り図に事業用スペースを明記しておくなど、根拠資料を準備しておきましょう。
自動車関連費
物件の視察や管理会社との打ち合わせ、金融機関訪問などで自家用車を使う場合、その関連費用も家事按分できます。
- 対象費用:ガソリン代、駐車場代、自動車税、保険料、車検代、そして車両本体の減価償却費も対象です。
- 按分基準:走行距離で按分するのが最も合理的です。業務で使った日の運転記録(行き先、目的、走行距離)をしっかりつけておきましょう。
車両本体の減価償却費まで経費にできることは意外と知られていません。仮に300万円の車(耐用年数6年)を業務で30%使用しているとすれば、年間で「300万円 ÷ 6年 × 30% = 15万円」もの経費を計上できるのです。
交際費・新聞図書費
- 交際費:管理会社の担当者や、他の大家さんとの情報交換のための飲食代も、業務に関連するものであれば「会議費」や「交際費」として経費になります。領収書の裏に「誰と、何の目的で会ったか」をメモしておく習慣をつけましょう。
- 新聞図書費:不動産投資に関する書籍、専門新聞、有料のウェブマガジンなども立派な経費です。
これらの「小さな経費」も、積み重なれば大きな節税につながります。日頃から事業用のクレジットカードを使うなどして、漏れなく記録することが重要です。
こちらの記事も読まれています!

裏ワザ4:青色申告で節税メリットを最大化する
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。不動産投資を行うなら、手間をかけてでも**「青色申告」**を選択すべきです。そのメリットは絶大です。
事業的規模なら「65万円控除」
青色申告の最大のメリットは**「青色申告特別控除」です。 不動産投資が「事業的規模」**と認められ、複式簿記で記帳し、電子申告(e-Tax)を行えば、所得金額から最大で65万円を控除できます。
「事業的規模」の目安は、**「5棟10室基準」**と呼ばれ、戸建てなら5棟以上、アパート・マンションなら10室以上を貸し付けている状態を指します。
仮に課税所得が500万円の人の場合、所得税率20%と住民税率10%を合わせると、65万円の控除によって「65万円 × 30% = 19.5万円」も税金が安くなる計算です。
事業的規模でない場合でも、10万円の控除は受けられます。
赤字を3年間繰り越せる
不動産所得が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せるのも青色申告の大きなメリットです。 例えば、1年目に大規模修繕で200万円の赤字が出た場合、2年目以降に黒字が出ても、この赤字と相殺して所得を圧縮できます。これにより、複数年にわたって安定した節税が可能になります。
裏ワザ5:家族への給与で所得を分散する
事業的規模で青色申告をしている場合、生計を一つにする配偶者や親族に支払った給与を**「青色事業専従者給与」**として全額経費にできます。
- 要件
- 青色申告者と生計を同一にする配偶者、その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- 原則として、その年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事していること。
- 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること。
例えば、妻に物件の清掃や家賃の入金管理などの業務を任せ、月8万円(年間96万円)の給与を支払ったとします。この96万円がまるまる経費になり、大家さん自身の所得を圧縮できます。
さらに、給与を受け取った妻は、給与所得控除(最低55万円)があるため、年間の給与が103万円以下であれば所得税はかかりません。結果として、世帯全体で見た場合の手取り額を増やすことができるのです。
ただし、給与額は仕事内容に見合った妥当な金額でなければなりません。名義貸しのような実態のないものは認められないため注意が必要です。
やってはいけないNG節税(=脱税)
これまで紹介したテクニックはすべて合法的な節税策ですが、一線を越えてしまうと「脱税」となり、重いペナルティが課されます。
- 架空経費の計上:使ってもいない経費や、偽の領収書で経費を水増しする行為。
- プライベート支出の経費化:家族旅行の費用を「視察」と偽るなど、明らかに事業と関係ないものを経費にすること。
- 収入の除外:礼金や更新料などを申告しない行為。
税務調査では、銀行口座の入出金履歴やクレジットカードの明細など、あらゆる角度から徹底的にチェックされます。不正は必ず発覚すると考えましょう。追徴課税はもちろん、悪質な場合は重加算税(最大40%)が課され、社会的信用も失いかねません。
まとめ:賢い経費計上で不動産投資を成功に導こう
不動産投資における「経費の裏ワザ」とは、特別な魔法ではありません。法律で認められた制度を正しく理解し、それを最大限に活用する知識と実行力に他なりません。
- 減価償却を制し、キャッシュフローを傷めずに所得を圧縮する。
- 修繕費と資本的支出を正しく見極め、最適なタイミングで経費化する。
- 家事按分を駆使し、見落としがちな経費を一つ残らず拾い上げる。
- 青色申告を選択し、特別控除と損失繰越のメリットを享受する。
- 専従者給与を活用し、世帯単位で所得を最適化する。
これらのテクニックを実践するには、日々の地道な記録(領収書の保管、業務日誌の作成など)が不可欠です。また、会計ソフトを活用すれば、複式簿記のハードルも大きく下がります。
不動産投資は、物件選びと同じくらい、購入後の「経営」が重要です。そして、その経営の中核をなすのが税務戦略です。本記事で得た知識を武器に、ぜひあなたの不動産投資を成功へと導いてください。もし判断に迷うことがあれば、決して自己判断せず、不動産に強い税理士などの専門家に相談することをお勧めします。賢い知識と備えが、あなたの資産を守り、育てていくのです。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい…現状の管理会社に不満がある…などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEでお問い合わせ可能です♪