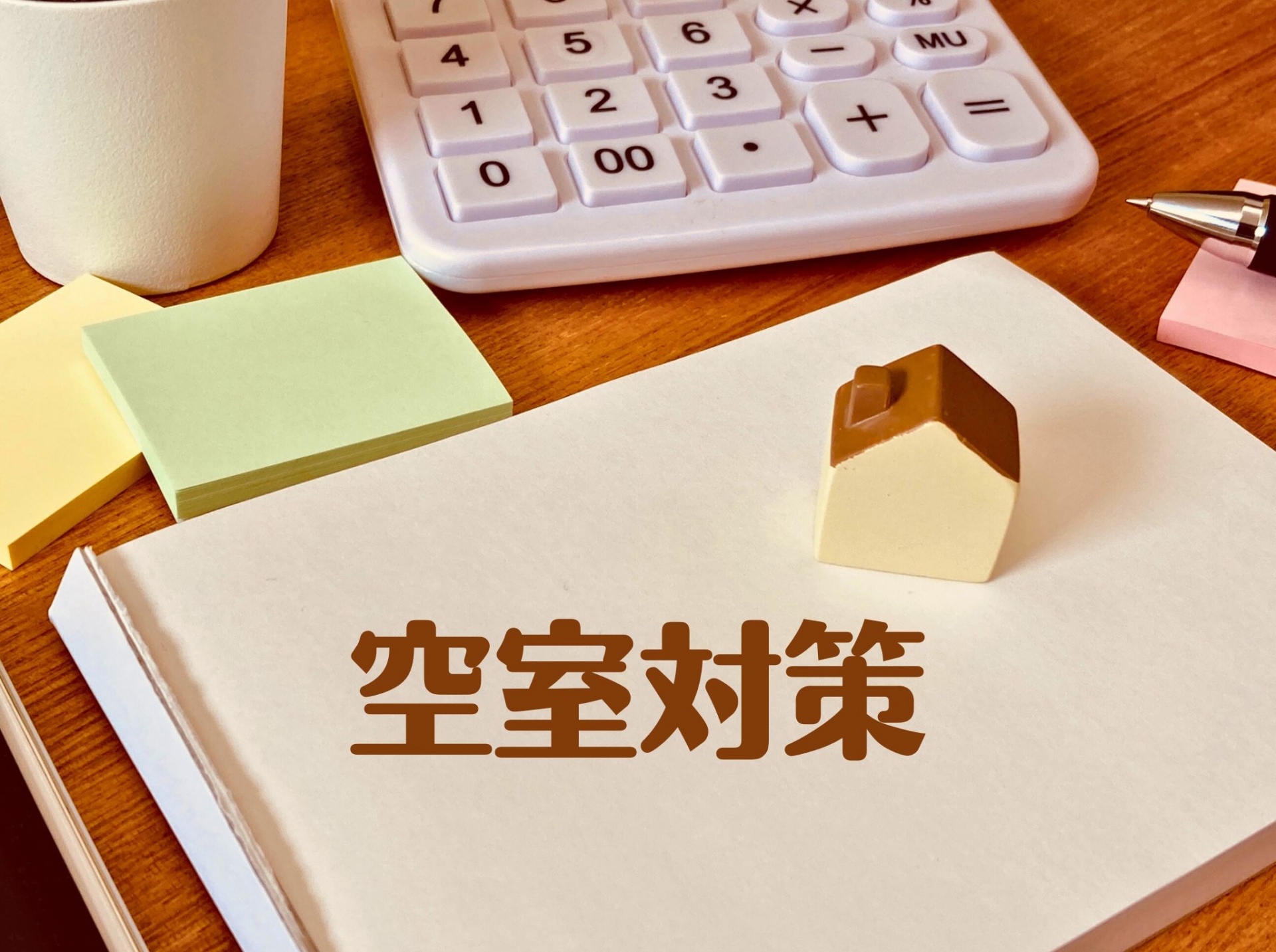はじめに
賃貸経営において、誰もが直面したくないものの、避けては通れない事態の一つに「賃借人の死亡」があります。親しい間柄でなくとも、これまで家賃を払い続けてくれた入居者様が亡くなることは、まずはそのご冥福をお祈りする気持ちが先に立つことでしょう。しかし、感傷に浸るだけでなく、オーナー様としては、その後の賃貸借契約の取り扱い、そして退去費用や原状回復義務など、実務的な対応について冷静かつ適切に進める必要があります。
このコラムでは、賃借人死亡時の賃貸借契約の法的側面、具体的な手続き、そして退去費用に関するトラブルを未然に防ぐための対策まで、オーナー様が知っておくべき情報を分かりやすく解説します。あらゆるケースを想定した実践的な内容をお届けしますので、ぜひ最後までお読みいただき、今後の賃貸経営にお役立てください。
賃借人死亡と賃貸借契約の基本的な考え方
賃借人が死亡した場合、賃貸借契約はどのように扱われるのでしょうか。まず、ここでの基本的な考え方を理解しておくことが重要です。
賃貸借契約の相続性
日本の民法において、賃貸借契約は「一身専属的な契約」ではありません。つまり、個人の特別な能力や性格に依存する契約ではないため、原則として相続の対象となります。賃借人が死亡した場合、その賃貸借契約上の権利義務(部屋を使用する権利や家賃を支払う義務など)は、法定相続人に包括的に承継されます。
多くのオーナー様は、「賃借人が亡くなったら契約は終了する」と考えがちですが、これは誤りです。相続人がいる限り、契約は自動的に終了するわけではないことをまず認識してください。
相続人の特定と連絡の重要性
相続人が契約を承継するということは、誰が相続人なのかを特定し、連絡を取ることが最初のステップとなります。
・法定相続人の範囲:
✓常に相続人となるのは配偶者です。
✓第一順位は子(子が死亡している場合は孫など直系卑属)。
✓子や孫がいない場合は、第二順位として父母(父母が死亡している場合は祖父母など直系尊属)。
✓子、孫、父母、祖父母がすべていない場合は、第三順位として兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子)。
・連絡先の確認:契約書に緊急連絡先や保証人の情報が記載されている場合は、そこから相続人につながる可能性があります。まずはこれらの情報をもとに連絡を試みましょう。
・住民票の除票の確認:死亡した賃借人の本籍地や最後の住所地の役所で、住民票の除票を取得できる場合があります。除票には、世帯主との関係が記載されていることがあり、そこから配偶者や子などの存在が判明する手がかりとなることがあります。ただし、個人情報保護の観点から、オーナーが直接取得するのは難しい場合が多いです。
ポイント:賃貸借契約書に緊急連絡先や親族の連絡先を複数記載してもらうこと、そして契約時に入居者本人の身分証明書や住民票を確認することは、万が一の事態に備える上で非常に重要です。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合、賃貸借契約上の権利義務は共同相続されます。つまり、複数の相続人全員が、その部屋を使用する権利を持ち、同時に家賃を支払う義務を負うことになります。
ただし、実務上、共同相続人全員が引き続き入居を希望することは稀です。多くの場合、共同相続人のうちの一人が代表して手続きを進めるか、全員が契約の解除を希望することになります。
賃借人死亡後の賃貸借契約の具体的な対応
賃借人が死亡したことが判明したら、オーナー様は具体的にどのような対応を取るべきでしょうか。
まずは冷静に、そして迅速に
ご遺族への配慮を忘れず、しかし対応は迅速に行うことが重要です。遺品の整理や退去費用など、時間が経つほど問題が複雑化する可能性があります。
相続人との連絡と状況確認
前述の通り、まずは相続人の特定と連絡に努めます。連絡が取れたら、以下の点を確認しましょう。
・賃借人の死亡の事実と死亡日:正確な死亡日を確認することで、家賃の発生期間などを明確にできます。
・今後の契約に関する意向:相続人が引き続き入居を希望するのか、それとも契約の解除を希望するのかを明確に確認します。
✓継続入居を希望する場合:相続人の中から代表者を決め、その者との間で新たに賃貸借契約を締結することが一般的です。この際、改めて入居審査を行うべきです。
✓契約解除を希望する場合:退去に向けた具体的なスケジュールや、残置物の処分、原状回復義務について話し合いを進めます。
・保証人の有無と連絡先:連帯保証人がいる場合は、その保証人にも連絡を取り、状況を共有します。保証人は相続人と同様に賃借人の債務を負うことになりますが、相続人が優先されます。
賃料の取り扱い
賃借人が死亡した場合でも、部屋が占有されている限り、原則として家賃は発生し続けます。死亡日までの家賃は賃借人の財産から、死亡日以降の家賃は相続人が承継する債務として発生します。
・自動引き落としの場合:賃借人の銀行口座が凍結されると、引き落としができなくなります。早めに相続人に連絡し、今後の家賃の支払い方法について取り決めましょう。
・滞納家賃の請求:もし死亡時点で滞納家賃があった場合、その債務も相続人が承継します。相続人に請求することになります。
残置物の取り扱いと室内への立ち入り
賃借人が死亡し、室内に残された家財道具などの「残置物」の扱いは、最もデリケートな問題の一つです。
・勝手に処分してはいけない:オーナー様が勝手に故人の残置物を処分することは**絶対にしてはいけません。**これは不法行為となり、損害賠償責任を負う可能性があります。残置物は相続人の財産だからです。
・相続人による処分が原則:残置物は相続人が引き取り、処分するのが原則です。相続人に、いつまでに残置物を撤去するか、明確な期限を設けて伝えましょう。
・遺品整理業者と相続人:相続人が遠方に住んでいる場合や、遺品整理に手間がかかる場合、遺品整理業者を手配することがあります。この場合も、必ず相続人の指示・立ち会いのもとで行われるようにしてください。
・室内への立ち入り:賃借人が死亡しても、勝手に室内に入ってはいけません。鍵が開いていても、賃貸借契約は続いているため、不法侵入となる可能性があります。相続人の承諾を得て、立ち会ってもらうのが原則です。
・孤独死など特殊なケース:孤独死などで長期間発見されず、室内が汚損・腐敗している場合でも、勝手に清掃業者を入れたり、残置物を処分したりしてはいけません。警察や管理会社と連携し、相続人の特定を急ぐとともに、相続人の承諾を得てから、特殊清掃などを行う必要があります。この場合、緊急性があるため、相続人への連絡を試みつつ、やむを得ず対応するケースもありますが、その場合でも必ず証拠(写真など)を残し、費用明細を明確にしておきましょう。
ポイント:残置物に関しては、相続人との間で「残置物に関する覚書」などを締結し、処分方法や費用負担について明確に合意しておくことを強くお勧めします。
賃貸借契約の解除手続き
相続人が契約の解除を希望する場合、通常の手続きと同様に、解約通知書の提出を求めます。解約の意思表示は、相続人全員が行うか、相続人から委任を受けた代表者が行うことになります。
・解約通知書の提出: 解約通知書を相続人から受け取り、解約日を確定させます。
・敷金の清算: 死亡した賃借人が預けていた敷金は、原則として相続人に返還されます。ただし、滞納家賃や原状回復費用、残置物撤去費用などが発生した場合は、敷金から差し引いて清算します。
・明け渡しと鍵の返還: 合意した解約日に、相続人立ち会いのもと、部屋の状況を確認し、鍵の返還を受けます。
こちらの記事も読まれています!

退去費用と原状回復義務
賃借人死亡後の退去費用、特に原状回復義務は、トラブルになりやすいポイントです。
原状回復義務の承継
賃借人が死亡した場合でも、その原状回復義務は相続人に承継されます。つまり、故人が負担すべきだった原状回復費用は、相続人が支払う義務を負うということです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基本とし、通常損耗や経年劣化による修繕費用はオーナー負担、賃借人の故意・過失による損傷や善管注意義務違反による汚損などは賃借人(相続人)負担となります。
特殊なケース:孤独死と原状回復
孤独死などで長期間発見されず、室内が著しく汚損(腐敗臭、体液の染み付きなど)している場合、通常の原状回復費用では済まないケースが多くなります。
・特殊清掃の必要性:一般的なハウスクリーニングでは対応できない、専門業者による特殊清掃が必要となる場合があります。
・消臭・脱臭工事:腐敗臭が壁や床材に染み付いてしまった場合、消臭・脱臭のための工事が必要となることもあります。
・建材の交換:体液の染み付きなどにより、フローリングや壁紙、畳などの建材を広範囲に交換する必要が生じることもあります。
これらの特殊清掃や消臭・脱臭、建材の交換費用は、賃借人(相続人)の善管注意義務違反による損害とみなされることが多く、原則として相続人が負担すべき費用となります。
どこまで請求できるのか?
請求できる範囲は、基本的に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠します。
・ガイドラインの遵守:ガイドラインに沿って、損傷箇所や汚損箇所の写真を詳細に記録し、見積もりを取得します。
・見積もりの透明性:清掃業者や工事業者から複数の見積もりを取り、比較検討することも重要です。相続人にも見積もりを提示し、納得してもらえるよう努めましょう。
・損害の「発生時期」:孤独死の場合、死亡から発見までの期間が長いほど、損害が拡大します。この拡大した損害も、原則として賃借人(相続人)の責任とされます。
・入居時の状況の記録:入居時の写真やチェックシートがあれば、原状回復の範囲を明確にする上で非常に役立ちます。
注意点: 特殊清掃や消臭費用が高額になる場合、相続人が支払いを拒否するケースも考えられます。訴訟に発展する可能性も考慮し、証拠保全を徹底することが重要です。
敷金との相殺
発生した退去費用(滞納家賃、原状回復費用、残置物撤去費用など)は、預かっている敷金から差し引いて清算します。敷金を超える費用が発生した場合は、相続人に不足分を請求します。
・清算書の作成:詳細な清算書を作成し、各費用の内訳を明確にします。
・残高の返還または請求:敷金で足りる場合は残高を返還、不足する場合は不足分を請求します。
オーナーが取るべき対策と予防策
賃借人死亡という事態に直面した際に、オーナー様が円滑に対応し、トラブルを最小限に抑えるための対策と予防策を考えます。
賃貸借契約書の明確化
契約書はトラブル回避のための最も重要なツールです。
・緊急連絡先の複数記載:賃借人本人だけでなく、親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)の緊急連絡先を必ず複数記載してもらいましょう。連絡が取れる可能性が高まります。
・「孤独死対応特約」の検討:契約書に「孤独死特約」や「原状回復特約」を盛り込むことを検討しましょう。
✓孤独死特約の例:賃借人の死亡により、特殊清掃や消臭、原状回復に多大な費用を要した場合、賃借人(またはその相続人)がその費用を負担することを明記する。また、一定期間連絡が取れない場合の安否確認に関する規定なども盛り込むことがあります。ただし、あまりにオーナー側に有利な特約は消費者契約法に抵触する可能性もあるため、弁護士と相談の上、慎重に作成してください。
・残置物に関する取り決め:賃借人の死亡により残置物が多量に残された場合、一定期間経過後も相続人による撤去がされない場合は、オーナーが処分できる旨の規定を盛り込むことも考えられます。ただし、この場合もあくまで相続人の財産であるため、相続人との合意形成が必須です。
連帯保証人の重要性
連帯保証人は、賃借人が負う債務を連帯して保証する義務があります。
・保証能力の確認:契約時に連帯保証人の収入状況や資力を確認することが重要です。
・緊急連絡先としての機能:連帯保証人は、賃借人と連絡が取れなくなった際の重要な窓口となります。
・相続人への請求が難しい場合:相続人がいない、または相続放棄した場合など、相続人への請求が難しいケースにおいて、連帯保証人に請求することになります。
注意点:近年では、高齢化や親族間の関係希薄化により、連帯保証人を立てられないケースも増えています。その場合、家賃保証会社への加入を必須とするなど、別のリスクヘッジを講じる必要があります。
家賃保証会社の活用
家賃保証会社は、賃借人の家賃滞納だけでなく、死亡時のリスクヘッジとしても非常に有効です。
・家賃の保証:賃借人死亡後も、相続人が特定され、退去するまでの間の家賃を保証会社が立て替えてくれます。
・原状回復費用や残置物撤去費用:契約内容によっては、家賃だけでなく、原状回復費用や残置物撤去費用、孤独死に伴う特殊清掃費用なども保証対象となる場合があります。
・相続人との交渉代行:保証会社が相続人との交渉を代行してくれるケースもあり、オーナーの負担を軽減できます。
ポイント:保証会社のプラン内容をよく確認し、賃借人死亡時の対応範囲がどこまでカバーされているかを確認しておくことが重要です。
賃貸管理会社との連携
賃貸管理会社に管理を委託している場合、賃借人死亡時の対応は管理会社が行うことになります。
・迅速な情報共有:賃借人の死亡が判明したら、すぐに管理会社に連絡し、情報共有を行います。
・対応プロセスの確認:管理会社が賃借人死亡時にどのような手順で対応するのか、事前に確認しておきましょう。
・専門家との連携:管理会社は、弁護士や司法書士、遺品整理業者など、関連する専門家とのネットワークを持っていることが多く、スムーズな問題解決に繋がります。
定期的な入居者の状況把握と見守り(高齢者向け)
特に高齢の入居者様の場合、孤立死のリスクが高まります。
・見守りサービスの利用:高齢者向けの見守りサービスや、自治体の安否確認サービスなどを利用してもらうことを促す。
・定期的なコミュニケーション:家賃集金の際に声かけをする、郵便受けの溜まり具合を確認するなど、無理のない範囲で日常的な見守りを心がける。ただし、プライバシー侵害とならないよう、配慮が必要です。
・緊急連絡先の更新:定期的に緊急連絡先の変更がないか確認する。
これらの対策は、賃借人死亡時のオーナー様の精神的・経済的負担を軽減し、円滑な賃貸経営を継続するために不可欠です。
こちらの記事も読まれています!
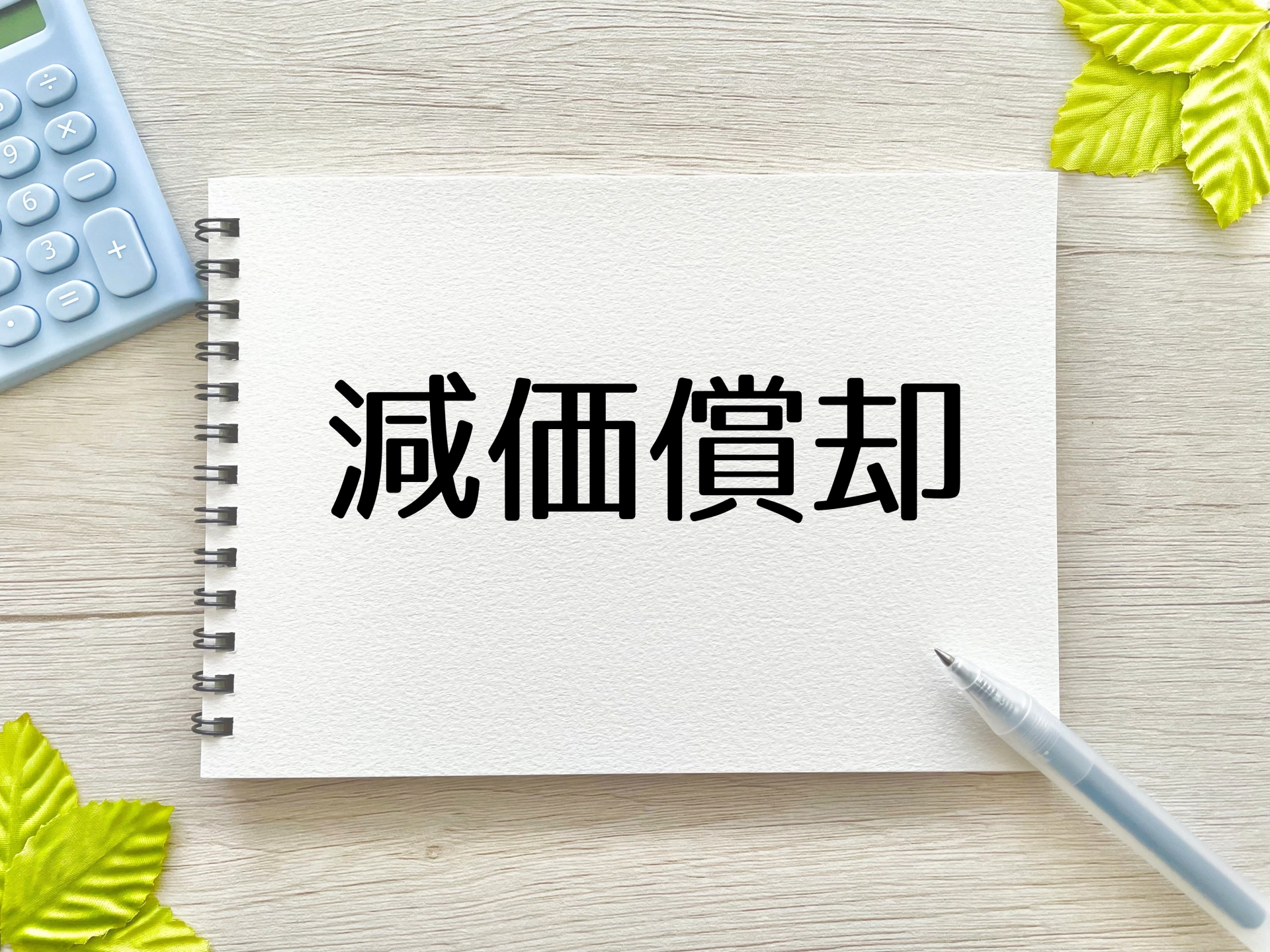
万が一トラブルになったら
いくら対策を講じても、賃借人死亡後の対応でトラブルになる可能性はゼロではありません。
専門家への相談
・弁護士:相続人との交渉が難航する場合、原状回復費用の請求に応じない場合など、法的な紛争に発展しそうな場合は、迷わず弁護士に相談しましょう。賃貸借契約、相続、不法行為など、幅広い知識を持つ弁護士が力になってくれます。
・司法書士:相続人の特定や、相続放棄に関する情報など、法務局での手続きが必要な場合に相談できます。
・行政書士:合意書の作成など、書類作成に関する相談ができます。
証拠の保全
トラブルになった場合、最も重要となるのが「証拠」です。
・写真、動画:死亡発見時の状況、残置物の状況、汚損・破損箇所の詳細を、日付入りで写真や動画に残しましょう。
・書類:賃貸借契約書、重要事項説明書、解約通知書、遺品整理や清掃の見積もり・請求書、領収書、相続人とのやり取りの記録(メール、手紙など)はすべて大切に保管してください。
・客観的な記録:警察や消防、救急隊などが現場に入った場合は、その記録などもあれば、状況を裏付ける証拠となり得ます。
賃貸不動産経営管理士や宅地建物取引士への相談
地域の賃貸不動産経営管理士会や宅地建物取引業協会などでも、賃貸経営に関する相談を受け付けている場合があります。実務的なアドバイスや、過去の判例などを参考に解決策を模索できることがあります。
まとめ:冷静な対応と事前準備が鍵
賃借人の死亡は、オーナー様にとっても、残されたご遺族にとっても、非常に辛い出来事です。しかし、感情的になることなく、冷静かつ適切に対応することが、その後の賃貸経営を円滑に進める上で何よりも重要です。
このコラムで解説したように、賃貸借契約の相続性、残置物の取り扱い、原状回復義務、そして家賃保証会社の活用や契約書の明確化といった事前準備は、万が一の事態に備えるための不可欠な要素です。
いつ何が起こるか分からないのが人生です。もしもの時にも慌てず、適切な対応が取れるよう、このコラムの内容を参考に、今一度ご自身の賃貸経営におけるリスク管理を見直してみてください。適切な知識と準備があれば、どんな困難な状況にも冷静に対処し、円滑な賃貸経営を継続していくことができるでしょう。
★★★当社の特徴★★★
弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい・・・現状の管理会社に不満がある・・・などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!
家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
【お電話でのお問い合わせはこちら】
03-6262-9556
【ホームページからのお問い合わせはこちら】
管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪
【公式LINEからのお問い合わせはこちら】
お友達登録後、LINEお問い合わせ可能です♪